具体的な勉強法・教育法について色々と調べていくと、必ず突き当たる問題があります。
それは、「ノウハウや学習メソッドが溢れかえっていてどれが正解か分からない」という疑問です。
中には、AさんとBさんとで全く逆の方法を主張している場合もあります。
では、どうすれば良いのでしょうか?
それぞれの情報を取捨選択した上で、自分に合ったコツだけ良いとこ取りをすれば良いのです。
ポイントは「自分にとって使える手段なのか」という観点です。この観点がないと情報に振り回され続ける事態に陥りかねません。
効率的な学習方法は人それぞれ個体差で変わる

まずは、なぜ人によって主張するノウハウが違ってくるのかについて考えていきます。
「東大合格生のノートはかならず美しい」は嘘?人によっては役に立つ
例えば、一昔前に『東大合格生のノートはかならず美しい』という本が話題になりました。
一方で、前回記事ではノートを使った学習法について一石を投じました。
実際問題として、ノート作りを一切やらないで東大に合格する人間はいくらでもいます。何よりも私自身もその一人です。(当時最難関だった文Ⅰから出願先を変えていれば)
著者が本当に東大生であれば、尚更こうした実情を知らないはずはありません。
現実的な話を言ってしまうと、「東大合格生のノートはかならず美しい」というのはマーケティングの為のキャッチコピーということです。
もしも仮に本のタイトルを「東大合格生のノートは美しい場合がある」と正直に書いていたら、あそこまで話題には上らなかったことでしょう。
それでは、タイトルが事実に反しているから中身も全て間違いかと言うと、話は全く違います。
この本は、「東大合格生のノートが美しい」ではなく、「美しいノートを書いている東大合格生のノート作り」こそが主題であると言えます。
そうであれば、「ノートを作って勉強している方にとっては」参考になるかも知れません。
前回記事でノート不要の立場から説明しつつも、ノート作り自体を否定しなかったのは、自分に合った学習スタイルはあくまでも人それぞれだからです。
※ただし、ノートがキレイなだけで頭に何も残っていなければ、合う合わない以前に意味はありません。
視覚優位型と聴覚優位型、認知構造が違えば効率的な方法も個人差で変わる
改めて確認しますが、勉強というのはあくまでも目標達成のための手段です。
山頂に登るためのルートは人それぞれで当たり前の話です。
加えて、人間はその認知構造も能力の適正もクセも性格も、何もかも個体差が大きい生き物です。
例えば、視覚優位型のタイプであれば、参考書や教科書などを目で追って学習していくスタイルのほうが身につきやすいかも知れません。場合によっては参考書などのページをそのまま映像記憶として覚えられるかもしれません。
逆に、視覚に偏ったタイプであれば音読や音声での学習は効果的でないかも知れません。
一方で、聴覚優位型のタイプであれば話を聞いたり音読したりすることでより理解しやすくなるかも知れません。記憶も、映像として見るよりも音声情報の方が頭に入りやすいかも知れません。
そうした方は、例えば文章を読む時には、視覚情報よりも脳内で音声が流れる感覚の方がしっくりくるかも知れません。
もちろんバランス型も居るでしょうし、両方とも高い水準のタイプも居るでしょうし、あるいは身体感覚が優位のタイプも居ることでしょう。

個々人の認知機能に個体差があれば、その人に合った手段も必要な方策も当然ながら違ってくるということです。
だからこそ発達障害の場合は専門家による療育が最善の方法
人それぞれという点は、近年話題となっている発達障害の方にとってより顕著なものとなります。
発達障害とは、一括りに言ってしまうと、平均的な人と比べてある一部の能力だけが著しく苦手で生活上の困難を抱えているような状態です。
個人的には、障害というよりも個体差が著しく大きいと表現したほうが適切のように思われます。
実際のところ、一口に発達障害と呼んでも、まさに人それぞれ全然違ってきますので、まずはそうした様々なケースについて知ることが大切です。知ることにより、当事者としてだけではなく、周囲の方への理解も深まることと思います。
近年では、オンラインのインターネット学習教材も発達しつつあります。
無学年制教材!対話型アニメーション、インターネット教材【すらら】
元講師である私の経験上、個別指導塾でも特別な知識やノウハウが無いと個々に応じた適切なサポートは非常に難しいです。
一方、こちらのプログラムは日本e-Learning大賞・文部科学大臣賞受賞となっており、国からもお墨付きを得たビジネスであると言えます。
このような活動が慈善事業ではなく実際にビジネスとして成り立っているという点は非常に重要です。
なお、学習面に限らず日常生活上でも辛さを感じているのであれば、お早めに医療機関や教育機関等をはじめとした専門家によるサポートを受けるのが最善の道だと個人的には思います。
これはいわゆるクオリティ・オブ・ライフ(人生の質)の向上にもつながります。
単純に学習メソッドのレベルが自分に合っていないだけの可能性も
なお、よくあるケースとして、学習法が今の自分自身のレベルに合っていないというものもあります。
例えば、別記事では英単語学習について独自の視点から解説しました。
ザックリと言えば、「英語は長文読解問題を軸にして、ついでに英単語も覚えていく」ような学習スタイルです。
英単語帳の暗記勉強はスキマ時間で回す!英語の学習法は長文読解優先|勉強法・教育法㉕
ですが、上の記事でも触れているように、「初歩的な単語も分からなくて2~3行の英文でも厳しい」という状態であれば逆効果になってしまいます。この段階で長文問題に取り組んでしまうと、逆に分からなさすぎて混乱をきたします。
よって、「そのような学習段階の人にとっては」1~2行の例文や一問一答レベルから始めるのが合っています。
一方で、英単語や基礎文法がそこそこ分かっているにも関わらず「なかなか長文読解に取り組もうとしない人」も居ます。
長文問題の出ない試験を受けるならばそれでも良いのですが、そうでなければ英単語帳や一問一答だけやっていても長文読解はいつまで経っても出来ません。論理的読解力や文脈判断、訳語の選択などは英単語帳ではカバー出来ないからです。
よって、「そのような学習段階の人にとっては」長文読解演習にウェイトを掛けるべきである、ということです。

学習法もステップアップが大切ということですね。

極端な例を挙げると、大学受験が幼児教育と全く別物であることと同じような話です。
言葉の定義が違うと解説の中身も変わってしまう
また、これは勉強法に限らないことですが、説明する人の言葉の定義によって話の意味が違ってくるという問題があります。(国語的な「定義」問題については過去記事で詳しく解説しています)
例えば、長文読解で賛否のあるテクニックに、パラグラフリーディングがあります。
このパラグラフリーディングは、「精読が苦手でもキーセンテンスを拾うだけで文章の全てが分かり問題も解ける魔法の裏ワザ」のように捉えるならば、批判が出るのも当然です。私としてもそのような方法であれば推奨しません。
一方、以前の記事では私自身の観点からパラグラフリーディングについて解説しました。
パラグラフリーディングのコツは文章構成のパターン化!長文読解をマクロ視点から分析|論理的思考のコツ⑰
この記事の中で私が述べているパラグラフリーディングとは、マクロ視点から文章構成を分析していくことでロジックの組み立て方のパターンが見えてくるという技術です。
これはミクロ視点の精読と同時に成り立つものですし、他の記事でもミクロ・マクロ両視点からの読み方を推奨しています。

学習メソッドについて考える場合は、理由も考えるのが良いです。そうすれば、表面的な言葉の違いだけでなく本質に気付けます。
学習方法の取捨選択から競争は始まっている、情報格差と教育格差
前回記事でも繰り返し述べたように、結局のところ、勉強法で大切なのは目的=点数アップに至るための手段として効率的・合理的かという点です。
そして、実際は勉強法を取捨選択するところから競争は始まっています。
単純な話として、経済力があるならば有名進学塾や予備校に通いつつ優秀な家庭教師も雇うのが勉強法としては限りなく最高効率に近い道であることでしょう。
なぜならば、「その道の上級者たちが経験則から取捨選択を繰り返した結果」に基づいて学習指導をしているためです。

学校と塾と家庭教師で勉強!?そんなまさか。

その「まさか」は実際にあります。それも小学生の時点で毎日塾に通わせつつ家庭教師も雇うようなご家庭もあります。

毎日……だと……?遊べなくて可哀想だなあ。

遊びの話は置いといて、独学で頑張っている人からしたら不平等感があるかも知れませんね。

そうしたケースは一部に限られますが、勉強は手段を問わないわけですから、教育格差というものは現実問題として否定できません。
そうは言えども、現代では書籍でもネットでも情報源は溢れかえっています。ですので、情報力・判断力次第で差を埋めることは可能です。
逆に言うと、情報が溢れかえっているがゆえに「自分に合った学習法」がなおさら分からないという事態が生じているとも言えます。
情報リテラシーが大事であるという話は、こうして勉強法それ自体からも論理的に明らかになってきます。

情報格差(デジタルディバイド)が小論文や長文読解のテーマになると、教育・経済など他の要素にもリンクしていきます。
情報は道具、資源として利用価値を判断する
自分に合った勉強法が分からず迷っている方にとって助けとなるかもしれない考え方があります。
それは、「情報は目的のための道具だ」と認識することです。
ビジネスの世界では常識なのですが、従来のヒト・モノ・カネに加えて、情報も資源として認識されています。近年になってよく聞かれるビッグデータの活用というのも、この文脈の話です。
つまり、情報を道具・資源としての利用価値から判断するという観点です。
勉強法で言えば、自分にとって利用価値が高いと思ったらそのメソッドを「道具として」利用すれば良いという捉え方です。
例えば、万人にオススメできる基本的な学習スタイルとして、問題演習&解き直しのサイクルについて以前解説しました。
ここでは、基本方針として「まずは問題演習を実際にやって、それから間隔をあけて3周解き直しをする」と述べました。
ですが、簡単な問題演習は後回しにして応用問題だけを先にやったり、あるいは解き直しを2周に減らしたり逆に4周5周と回したりと、自分に合わせてアレンジするのは自由です。
結局は、自分にとって役に立つ手段であればそれで良いということです。
もしも当記事が利用価値の高い道具だと思ったらそれを利用すれば良いだけです。
あるいは、「ある段落の話は使えるが別の段落のトピックは使えない」と思ったら、使えると思った部分だけを道具として利用すれば良いということです。
または、経済的余裕があるのであれば、評判の高い予備校や学習教材にお金を使うというのも合理的な選択肢の一つです。
ケイスケホンダの記事で紹介した超人T君のように、高校生でありながら自力で教育費を稼ぐようなことですら選択肢としてありえます。中高生は例外的ですが、高校卒業後であればそれは全く当たり前の自己投資です。

もちろん私の見解を採用せず他の方の考えを受け入れるのも個々人の判断次第です。そうして良いとこ取りをしていきましょう。
「やらない学習メソッド」より「やる詰め込み勉強」
ただし、どんな方法も実際にやらないと意味が無いという点にはくれぐれもご注意下さい。
先ほどの『道具』という表現には、「実際にあなた自身がそれを使わないと意味が無い」という意味も含まれています。
いくらお金を掛けて最先端の教育を受けたところで、受け身で聞き流すだけでは学習効果も限定的です。
どんなに素晴らしい学習メソッドを知ったとしても、実践しなければ何の意味もありません。
それならば地道に詰め込み勉強をした方が確実に成長できます。

やらなきゃ意味ないよ。できませんでしたじゃ済まされないぞ。

できなければ原因を自己分析して別の方法を取れば良いですし、それでも分からなければアドバイスを求めれば良いのです!
加えて、実際にやってみないと自分に合っているかどうかも分からないという現実もあります。
よって、自分で試行錯誤をしつつ学習の質も量も高めるのが一番です。
まとめ
情報化が急速に進むにつれて、学習・教育に関する有益な情報へのアクセスも非常に容易になりつつあります。(当サイトもその一つであれば幸いです。)
一方で、人によってオススメする学習メソッドが違うというのもまた事実です。
これは、人間に個体差があるために当然起きることです。つまり、絶対的に正しい学習法など無いということです。解き直しですら合わない人が居るかも知れません。
そこで大切になってくるのが情報の取捨選択です。
学習法に限らず、情報を道具・資源として捉え、利用価値に基づいて合理的に取捨選択するという意識です。
そうして良いとこ取りをしていくことによって、ご自身に合った学習メソッドが自然と出来上がっていくことでしょう。

あとは個々人の試行錯誤が大切になってきます。
※なお、金銭面の都合がつく方はオンライン家庭教師を利用するのが最も確実です。
上は難関大や医学部レベルまでカバーできますし、オンラインですので先生側も生徒側も余計な移動時間や出費が格段にカットできます。
あわせて読みたい
解き直しこそがコスパ最強の復習勉強!模試やテストに限らず問題演習から解き直す|勉強法・教育法②
勉強できないことが怖い?むしろ間違えた問題の復習こそが学習効果を高める|勉強法・教育法④



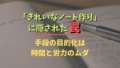


コメント