国語の設問に答えるためには「本文読解がすべての根拠になる」という話は随所で説明しています。
しかし、それ以前に「これ、質問に対する答えになってる?」という解答が国語の苦手な生徒さんのなかで特によく見られます。これは英語・数学・理科・社会、更には面接でも重大な問題です。
正しい答え方というのはパターンを意識すればカンタンに身につきますし、余計な減点を回避できるようにもなりますので、ここで明確にしておきましょう。
重要なポイントは、まずは「何を問われているのか」という意識、そして答える際には文末表現が核になります。

重量級の記事が続いたので、ライトでカンタンなトピックです。
ただし絶対厳守の事項です。
文末表現の具体例:質問と答えの対応

このトピックは実例を挙げたほうがわかりやすいので、問答の例を見てみましょう。
まずは英語での「質問と回答」の対応例からコツをつかむ

では最初にカンタンな英語の例で考えてみましょう。英語の方が問答のパターンを意識的に習うためピンと来やすいかも知れません。
First

Why did you do that?

Because I was angry.
「なんであんなことをしたの?」「怒ってたから。」
英語において、Why→Becauseは実に初歩的なパターンですね。
実際、この問答は質問と答えの形式をセットで習ったことと思います。
Becauseの同意語を持ってくるケースもありますが、日本語的に考えても「なぜ?」→「~だから。」「~ため。」とパターンになっています。社会の暗記に比べれば何ということもなく覚えられるはずです。
Next

How long will you stay here?

About two weeks.
「どのくらい(の期間)ここに滞在するつもりですか?」→「二週間くらいです。」
期間の長さ(How long)を聞かれたので、期間の長さで答えました。ただそれだけです。
国語での具体的な答え方、文末表現の基本は体言止めorである調
日本語でも英語でも、質問に対応する形で回答するという点は試験に限らず大切です。
本来は、日常会話においても質問と答え方が対応しているはずです。
- 「どの色が好き?」→「この色です。」
- 「どう思いますか?」→「こう思います。」
- 「どうやって行くの?」→「このようなルート・交通手段で行きます。」
- 「あれは誰だ?」→「あれは不動明だ。」
実に単純な話です。質問で聞かれたことを答えるだけです。
しかし、現実には出来ていないケースが非常に多いです。
参考までに、主要な質問文の形式を列挙してみます。
- 「下線部はどういう意味か答えなさい。」→「~という意味。」
- 「どういうことか説明しなさい。」→「~ということ。」
- 「○○とはどういう○○か答えなさい」→「~という○○。」「~のような○○。」
- 「なぜか、理由を答えよ。」→「~から。」「~ため。」「~という理由。」
- 「Aについて、Bと対比して説明せよ。」→「Bは~であるのに対して、Aは~である。」
- 「白組のボルトくんの最高速度は時速何キロメートルか、少数第1位を切り捨てて答えよ。」→「A.時速44km(少数第1位切り捨て)」
これだけの話ですが、出来ていない受験生が意外に多いですので、今日から意識して正しく答えましょう。正しく答えるために、質問文を慎重かつ正確に読みましょう。
なお、「下線部について簡潔に説明しなさい」とただ書かれてあるだけのケースでは書き方に迷うかも知れません。この場合は「聞かれている下線部が具体的に何か」でも話が違ってきますので、ケースバイケースです。
下線部が体言止めであれば、下線部に関係する体言で止めるのが分かりやすいでしょう。
例えば、「下線部『コミュニケーション能力』について説明しなさい」と問われれば、「他者と円滑に意思疎通をする能力。」と答える、といった要領です。
あるいは「どういう意味か」と問われれば、「○○という意味。」と答えれば良いということです。
体言止めでなければ『である調』の終止形が基本です。例えば、「筆者は、○○は△△であると主張している。」などです。

ケースバイケースが分からんとです。「説明せよ」とか「意義を答えよ」とか、どういうこと?

判断がつかなければ「~ということ。」に繋げるのが一番無難です。
※「意義を答えよ」の場合は、「~という意義。」という解答もアリです。
ですが、意義という言葉自体がしっくり来ないのであれば、「~ということ。」に繋がるように記述すれば自然な記述にしやすいという側面もあります。
応用:「理由を答えよ」→「~だから」「~ため」
設問の中でも、理由を答える問題というのは国語に限らず頻出であり、重要です。
そこで、もう少し具体的に考えてみましょう。

Q.二酸化炭素の排出量を規制するのはなぜですか?

A.温室効果ガスです。

A.温室効果ガスの削減につながるからです。
「なぜ?」≒「理由を答えよ」→「~(だ)から。」「~ため。」「~という理由。」
こうした文末表現が抜けただけで質問文に対する解答として不適なので減点とされてもおかしくありません。
採点基準が厳しめの試験ならば、前者の「温室効果ガスです」という解答は問いに対する答えの体をなしていない、あるいは設問の指示を無視していると捉えられて0点になっても文句は言えません。
(つまり『答えが理由になっていない』ということ)

理由を問われているのであれば「理由を答えるための文末表現」を使えば良い、というシンプルな話です。
参考:試験の記述問題での文末は「ですます調」よりも「である調」
言葉遣いについては別記事で詳しく特集していますが、せっかくですのでここで終止形の文末について取り上げます。
終止形であれば、「ですます調」と「である調」に大きく二分されます。
「ですます調」というのは、ズバリ当記事での文末の書き方です。
つまり、終止形を「~です。」「~ます。」のような形で書くことです。
ですが、試験問題で求められる言葉遣いは基本的にアカデミックな言葉遣いと捉えた方が良いです。カンタンに言えば、大学の論文などで使うような言葉遣いです。
よって、お硬い文体の「である調」を使う方が一般的です。
例
- 筆者である荒木氏は、人間賛歌を主題として提示している。(『提示しています』)
- ドイツの科学力は世界一である。(『世界一です』)
- その話は嘘だと思われる。(『思われます』)
的外れな解答を無くし「設問に答える」という共通課題
以上はほぼ形式的な文末表現に関する話です。
しかし、問題は形式的な側面にとどまりません。
たとえば数学の文章題で、ただ前提条件を並べている前半部を読んだだけで勝手に式を立てて勝手に答えはじめたり、後半部にある設問とは的外れな解を求めたり……。
国語で「本文に即して」と書いてあるのに本文に書いてすらいないことを書いたり……。
社会の記述問題で設問の指示する条件を無視してただ周辺知識を羅列しはじめたり……。
国語の問題以前に設問が読めていないケースは非常に多いです。
国語はすべての基本というモットーは、実はこの段階から既に始まっています。
バリバリの理系学部ですら国語力の問われない分野はほぼ皆無といえます。
設問の取り違えはケアレスミスではなく単なる実力の差です。出題側のミスであるケースは非常にレアです。

耳の痛い話ですね……。

私も本当に腑に落ちるまではちょくちょくやらかしていました。
だからこそ過去の自分への自戒の念も込めて手厳しく解説しています。
その際に、前半部の形式的な文末表現を足がかりに考えることで「質問と回答のキャッチボール」というコツが掴みやすくなるはずです。
コミュニケーションも設問も会話のキャッチボール
これらは、世間で重要視されているコミュニケーション能力でも同じ話です。
もちろん社交性や話の上手さといったものは人それぞれ個性で違います。
それでも最低限の基本として、相手の話を聞いて質問に応じて答えるだけでもコミュニケーションはある程度成り立ちます。(場を盛り上げたりコネクションを拡げたりするようないわゆる『コミュ力』は本来はもっと高度な話です。)
しかし、その最低限の基本が障壁になっているケースが多いように思われます。
まず何よりも、他者の話の意図を把握することは一般に思われている以上に難しいということです。この点は「定義の問題」に絡めて別記事で解説していますが、もちろん私自身も含めて誰にでも通ずる話です。
こうしたコミュニケーション上の問題は本文や設問を読めていないという話と同じような構造ですが、問題文の方が論理的な文字情報として明示されている分、主観の絡むコミュニケーションよりも遥かに分かりやすいものです。(もし文字を認識すること自体に困難を感じている場合は、「ディスレクシア」で検索してみて下さい。)
対面の質問でも問題文の設問でも、まず質問の意味が理解できてはじめて問題について考えることが出来ます。
自分勝手な答えだとキャッチボールになりません。ドッジボールです。
言葉のキャッチボールというのは、相手の要求に応じる形で投げ返すということです。
試験問題において言えば、問題作成者の投げかけた質問に合うように解答を投げ返すということです。
たとえば個別指導では「何が分からないかも分からないから質問のしようがない」という生徒さんが多いのですが、「なら、何が分かって何が分からないか一緒に確かめよう!カンタンな例題を解いてみせて」といったように、受け手側のリアクション次第で問題点の糸口を引き出すような試みもできます。
まとめ
以上は、一般常識の話です。
まずは書かれたままに読むことです。そして問われるままに答えることです。
これらができれば形式的な文末表現は勝手についてきますが、それが難しければ、今回の記事のように文末表現から先に考えてみることをオススメします。
こうした「当たり前」を試験で出来る人と出来ない人との一番の違いは、これらのことを自覚した上で意識的に訓練しているかどうかの差です。これはケアレスミスではなく実力差です。
今この記事を読んで心当たりのある人は、今日の宿題から意識をはじめましょう。

頭で分かったか分かっていないかの話ではなく、実際に出来ているかがすべてです。それがアウトプットです。
※なお、「本文に即して~」「筆者の主張を踏まえて~」などの問いは特殊ですので、次回の記事で特集しています。

※「具体的に説明せよ」のような質問がよく分からない場合は、まずは具体と抽象の両面の理解が必要です。

※「論理的な読解力」についてよく分からない方は、以下のシリーズがおすすめです。


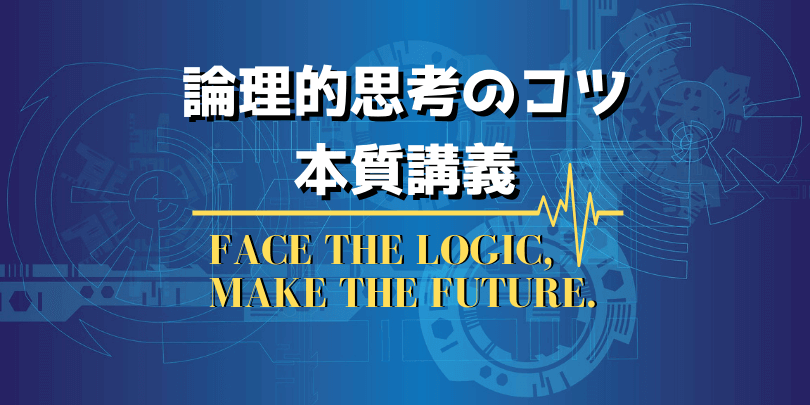



コメント