国語・現代文では、「かぎかっこ」は一般に思われているよりも重要です。
「鉤括弧(かぎかっこ)は会話文を表す」というのは常識ですが、実際は会話文以外でも多用されます。
特に注意すべきは、筆者が特別の意味を込めてカギカッコで括っている言葉です。
こうしたケースは、本文の主旨に関わる重要なワードである可能性があります。それはつまり、長文読解問題としても普段の活字を読むときでも注意して解釈すべき部分であるということです。
(当記事では「かぎかっこ」の表記を漢字・カタカナ・ひらがなのいずれも使っていますが、意味は変わりません。)
かぎかっこの一般的な意味の使い分け

まずは前提として、各種カギカッコの使い分け方をザックリと見ていきましょう。
かぎかっこの一般的に使われる意味
はじめに、通常の「かぎかっこ」についてまとめます。
会話文のカギカッコ
まずは、基本中の基本である会話文のカギカッコです。
普通の文章であれば、会話文か否かの判断は言葉遣いや前後の文脈から分かるかと思われます。
(追記)念の為、会話文のカギカッコの付け方についてカンタンに述べます。
これは、音声で考えれば一発で分かります。要するに、その人が実際に声に出して喋った言葉をカギカッコで括れば良いというだけの話です。
ただし、国語の物語文においては登場人物の行動の具体的な理由や心情を解釈するための直接的な根拠となりうるため、会話文は会話文で非常に重要です。
特に物語文が苦手な方の場合、発話者の取り違えは致命的なミスになりえます。
引用のカギカッコ、アバウトな要約としても
そして、他の文献からの引用としてカギカッコが使われることもあります。
引用のルールは提出用の作文や論文では極めて重要ですが、持ち込み不可の試験ではそもそも引用をする機会自体がまず無いかと思われます。
なお、先ほどの会話文でのカギカッコというのは、機能的には引用に近い側面があります。会話文の場合は、音声言語・話し言葉を文字起こしして引用しているようなものです。(だからこそ地の文では使わない方言や話し言葉が会話文中ではそのまま書かれる)
あるいは、冒頭の
のような使われ方であれば、具体的な誰かの引用や会話文というよりも、一般論をアバウトに要約しているような機能になります。
強調
そして、当記事のメインテーマである強調の用法です。
国語・現代文の長文読解においては、この強調の用法が最も重要になります。
詳しくは後半で解説します。
長い一文を節や句で括る
このカギカッコは英語で言うthat節や長い句を括っているようなイメージです。これにより、一つの意味のカタマリを分かりやすくする効果があります。
目的としては、文の構造を読みやすくするため(可読性の向上)です。論述試験などのフォーマルな文章には適さない使い方かも知れませんが、一般向けのライトな文章であれば割と見掛けるテクニックです。(当サイトでもよく活用しています)
二重鉤括弧の使い方
次に、『二重かぎかっこ』について述べます。
出典となる参考文献のタイトル名
まずは、参考文献を引用する際の出典を示す場合です。
三兎セッコ『論理的思考のコツ・本質講義』, 民明書房, 2019年, p.33.
参考文献・引用元の明示は、作文や論文を提出する際には必須です。具体的な出典の書き方は上記のケース以外にも様々ありますが、いずれにしましても、出典を書かずに引用するのは盗用・剽窃にあたるため厳禁です。
とは言え、持ち込み不可の学力試験であれば、特に考える必要のない部分です。
会話文の中でかぎかっこを使う時
会話文のなかで更にカギカッコを使ってしまうと、文の構造が紛らわしくなってしまいます。
プログラミングであればインデント(字下げ)を変えるような方法がありますが、通常の文章ではそうもいきません。
よって、会話文の内側にある方のカギカッコを二重にします。
この短文だけでも一目で区別が付きやすくなりますし、会話文が長くなればなるほど機能します。
その他、通常のカギカッコと同じような使い方
その他、人によっては先ほどの一重の「カギカッコ」と同じように『二重カギカッコ』を使うケースもあります。特に、「強調」と「長い一文を括る」ケースとしても使われることもあります。
ただし、各種試験ではこのような使い方はあまりオススメできません。小論文や作文では、あくまでも通常のカギカッコと役割を分けた方が無難です。
国語・現代文で注意すべき「カギカッコの意味合い」
筆者の強調はそもそも文章読解で重要となる箇所
まず、当シリーズでも繰り返し述べているように、文章読解問題においては「強調」という時点で重要箇所となる見込みが高いです。
なぜなら、筆者自身が強調しているということはすなわち「筆者自身が強く言いたいこと」そのものであるからです。
この「実際に」という表現の意図は、ただ単に学習メソッドの知識を集めるだけではなく「実際に」使うべきだとあえて強調して念を押すためのカギカッコです。
実際問題、ただ勉強法の知識を集めるだけで「実際に」自分で活用できていない受験生の方を多数見てきました。この「実際に」という部分がまさにカギです。
よって、特に読み流さずに注目して欲しい部分であるが故にあえてカギカッコをつけています。
「筆者独自のニュアンス・定義付け」の鉤括弧、センター国語の具体例
国語・現代文においては、強調から更に踏み込んで考えるべきケースが多々あります。
それは、本文中で『筆者独自のニュアンスや定義付け』が言葉に含められている場合です。
具体例で言えば、2018年センター試験の第1問が非常に分かりやすいです。→過去問(外部リンク)
本問のキーワードは「デザイン」ですが、以下のように、世間一般の人が考える「デザイン」という言葉とは定義が全く異なります。
デザインとは「対象に異なる秩序を与えること」と言える。

私であれば、この『○○とは~』という定義の文が出てきた時点で四角囲みにします。それだけ定義は重要です。
その上で、段落15では、カギカッコ付きで「デザインした現実」という表現が出てきます。
この「デザインした現実」というのを、『ああ、オシャレなデザインで囲まれた生活ってことね』のように世間一般の感覚で読んでしまうと筆者の意図と全く掛け離れた解釈になってしまいます。
なぜならば、筆者自身が「デザイン=対象に異なる秩序を与えること」という定義を本文で書いているからです。
ここから更に、カギカッコにダッシュを付けるような筆者独自の表現が出てくるのですが、当記事の趣旨とズレるため割愛します。
一つ言えることは、筆者が世間一般と同じ感覚で読んでほしくない言葉だからこそ「カギカッコ」などの記号を付けて区別しているということです。
なお、言葉の定義付けも非常に重要なテーマですので、別記事で掘り下げて解説しています。
例外:「実は筆者の主張と相違する第三者の意見」をカギカッコで区別
強調とは逆に、筆者の意見とは異なる言葉をカギカッコで括るというケースもあります。
この例文のカギカッコはアバウトな引用ですが、もしも筆者が「むしろ日本人はもっと自己主張せよ」という意見であれば、このカギカッコ内の一般論はむしろ筆者にとっての反対説となります。
(「自己主張せよ」vs「自己主張を控えよう」)
いわば、カギカッコによって筆者自身の主張と切り分けているといえます。(この例文ではそもそも『世間では』と前置きもしている)
なお、以前の記事でも述べたように、カギカッコに関係なく一般論はむしろ筆者の反論の前フリに使われることが多々あります。
論説文の一般論は筆者の反対説!?筆者の主張・反論の前フリという意味|論理的思考のコツ⑧
小論文・作文・論述試験で安易に鉤括弧を多用しない
ここまで、カギカッコについて様々な用法を見てきました。
こうした使い分けは、小論文や作文でもよくよく意識しておくべきです。
読み手である採点官は、もしも答案にカギカッコがあれば、当記事のような使い方の違いを大なり小なり意識します。
そこで、果たしてそのカギカッコは採点官側から見ても意味のあるカギカッコなのかという視点は持っておいた方が良いです。
何となくの気分でカギカッコを多用してしまうと、解釈を取り違えられたり、あるいは不適切なカギカッコの使い方として減点される可能性も否定できません。減点式の試験ではセーフティに行くのが定石です。
※当記事のような情報サイトの文章とは違い、「学力的な視点から採点される」という部分がポイントです。
よって、論述試験においてカギカッコを使う時は、会話文・引用・出典といった原則的な使い方に留めるのが安全です。(引用というのは問題の本文からの引用も含む)
一方で、特に強調の鍵括弧を何も考えずに多用するのはリスキーです。
まとめ
まずはカギカッコの基本的な使い分けを整理します。
- 会話文(基本)
- 引用(基本)
- 強調(応用)
- 長い一文の一部を括る(応用)
- 二重鉤括弧は出典のタイトル名かカギカッコの中のカギカッコとしてつかう(基本)
その上で、国語・現代文において非常に重要となるのは「強調」のケースと「筆者独自のニュアンスや定義付け」を含むケースです。
これらはいずれも、筆者自身の主張に直接的に関わってくることが多い用法です。筆者自身の主張に関わるということは、当然ながら本文の主旨にも絡み、そして設問にも絡んでくるということです。

専門家や文筆家が文章を書く際は、カギカッコの付け方も意図的であるのが普通です。そして、問題作成者も採点官も明確に意識します。
※当記事でご紹介した関連記事
定義とは、言葉の意味の共通認識!数学の定理と違い筆者が定義づける|論理的思考のコツ⑬
論説文の一般論は筆者の反対説!?筆者の主張・反論の前フリという意味|論理的思考のコツ⑧
※国語・英語の読解力を伸ばしたい方には以下のシリーズがオススメです。


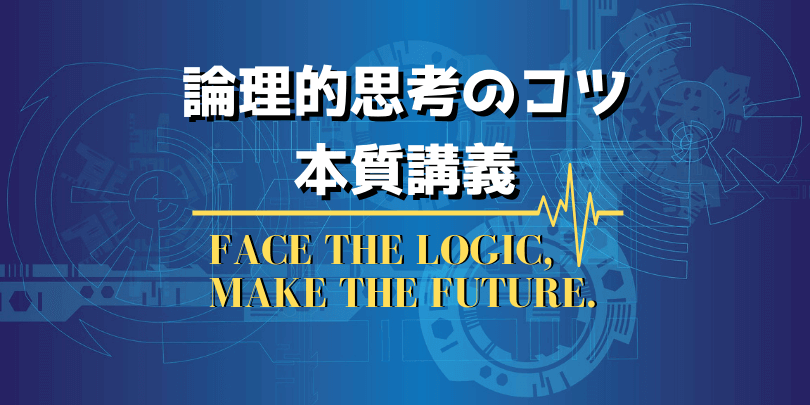



コメント