国語でも英語でも、長文読解の解き方として「斜め読み」「速読」「パラグラフリーディング」といったキーワードを聞くことがよくあると思います。

そりゃあ読むスピードは早い方がいいに決まってるんじゃない?

普段の読書をするときでも、読むスピードが上がればたくさんの本を読めるようになれますね。

ところが試験問題においては、ことはそう単純ではありません。
「斜め読み」「速読」「精読」について、単純にどれが良いという話ではなく、それぞれの意味や実際の機能から考えていきましょう。
ポイントは、各々の学習ステップです。
斜め読み・速読・精読とは?その意味と文章読解での機能

まずは、「当記事における」言葉の意味を定義した上で、実際の読解でどのように機能するかを分析していきましょう。
※定義の重要性については過去記事を参照してください。あくまでも言葉の使い分け方は人によって変わってきます。
「斜め読み」「飛ばし読み」こそが狭義のパラグラフリーディング
まず、「斜め読み」とは、「飛ばし読み」とほぼ同じ意味で、文章全体の中から大事な部分、欲しい情報をピンポイントに拾いつつ読んでいくような方法です。
今の時代であれば、ネットで調べ物をする際に、欲しい情報だけ拾う時の読み方が代表的です。

今回のイベントで一番効率的な回り方は、っと。検索検索ゥ!

その際には、先にサイトのレイアウトなどを把握してから目当ての攻略記事を探し当てるはずです。

いつものwiki見るか……お、新イベントの特設ページあるじゃん?
……メニューのここだ、『オススメ攻略ルート』!

マクロのサイト構造からミクロの情報を探してるってことですね!

それがまさに本来のパラグラフリーディングのコツそのものです!
そして各サイトにある目次がそのままアウトラインです。
詳しくは後の段落で見ていきます。
「速読術」はスピードアップ効果こそが目的、深い理解力は別問題
次に、「速読」については、語る人によってその意味するところが非常に多岐にわたるでしょう。
ですので、ここでは公約数的な捉え方をしてみます。
そうすると、数々の速読術に共通して言えることは、シンプルに「読む文章量のスピードを上げる」ことを目的とした手法であるように見えます。
すなわち、時間あたりの読書量を増やそうという観点から使われている言葉だと見受けられます

スピードは大切だからやっぱり速読術って使えるのか?

速読術を使って『実際に国語・英語の成績が伸びているなら』それでも良いでしょう。しかし速読自体を最初から目的にしたらむしろ遠回りになることが多いでしょう。

……なんで?

逆に問いますが、精読しても解けない問題を速読で解けますか?

うーん……どっちにしても解けないけど、時間が足りないならいっそ速読術で……。

ちょっと待って、解けないなら時間短縮しても一緒じゃない?
まずはゆっくりでも読み解けるようにならないとその先は……。

巷にあるテクニックはあくまでも手段です。
それらが自分の目的に適う手段かを確認しましょう。
精読とは『論理的読解力』の本質であり全ての基本
最後に、「精読」です。
精読とは、基本的に一字一句レベルまでていねいに追う読み方です。

精読は、これまで解説してきたミクロスケールの語彙や文法から一文ごとに読み込む読解法にほかなりません。
ミクロスケールの読解というのは、一文単位のロジックは当然として、一字一句を文法力・語彙力から全て理解できるレベルが理想のゴールです。
なぜなら、これまでの記事で見てきたように、たった一つの品詞がその一文の重要性すら変えうるからです。

復習も兼ねて、単純なケースを具体例として挙げます。
- 「よって少子化対策の観点から、診療報酬における妊婦加算を廃止するべきである。」
- 「よって少子化対策の観点から、診療報酬における妊婦加算を廃止するはずである。」
上の文は、「よって~べきである」となっており、これまでの論理展開を踏まえて筆者の主張となる見込みが高いです。
「べき」という助動詞によって筆者の強い推奨の意味となれば、文章全体の中でも重要な提言部分になります。(筆者自身が読者に強く推奨している=筆者の主張、という単純な話です)
よって「べき」には注意するべきです。
一方で下の文は、「べき」が「はず」となっただけで推奨するようなニュアンスではなくなり、筆者の論理的な推測のようなニュアンスへと変わるはずです。
そうなると、この文は事実関係の分析のようなパートとなり、筆者の主張となる見込みは比較的低いです。問題として関わるとすれば、本文の趣旨を問うような大きな問題ではなく、論証過程の途中部分を問うようなピンポイントな問題になるはずです。
むしろ「普通に考えればこうなるはずである。しかし、実際は~」と、逆接への前フリにすらなる可能性も十分にあります。

それでもオイラなら……オイラなら最初からパラグラフリーディングも出来るはず……!

その前に一問一答を解けるようにするべきなんじゃないの?

あっ、はい。(ぐうの音も出ない)

実際にこれらの一文がどのような位置付けになるかは文脈で変わりますが、それ以前に品詞レベルからの理解が必要です。そして品詞レベルの分析がパラグラフリーディングの判断にも影響を与えます。
論理的読解力というものは、まずは精読で読めることが前提になります。
問題作成者はマクロからもミクロからも本文分析している
これまでの記事でも解説してきたように、国語力というのは、ミクロ・マクロ両面の論理構造を理解する能力が核になります。もちろんそれは英語力でも同じです。
国語・英語における読解問題というのは、学力としての論理的思考力・読解力が前提となります。
具体的には、ミクロではボキャブラリー(語彙力)・文法・漢字、マクロでは文章構成・パラグラフ分析といった要素が含まれます。
一方、問題作成者は、同じように文章の論理の組み立て方をミクロ・マクロ両面から緻密に分析した上で問題作成しています。よほどの突貫工事でもない限り必ず分析しているはずです。
よって、問題作成側と同じようにミクロ・マクロ両面から論理的な思考プロセスを経て解答するのが合理的であり理想であるといえます。

逆に採点官が記述問題を採点する際には、ロジックのあやふやな答案は一瞬で見抜かれますのでまず自分の中でロジックを明確にしましょう。
斜め読み・パラグラフリーディングの前提こそミクロ視点の「精読」
前述したように、「斜め読み」や「パラグラフリーディング」というのはマクロ視点から文章を理解する手法です。

なら、最初からパラグラフリーディングを目指せばミクロからもマクロからも読めるようになるのではないでしょうか?

それが出来るならば理想的ですが、実際のところ斜め読みで文章のマクロ構造もミクロの文も認識するというのは非常にハイレベルです。
パラグラフリーディングの話を聞いてすぐにそのまま実用化できる人というのは、『マクロ・ミクロ両面からの理解力』が生まれつき高いという稀な頭脳の持ち主くらいのものだと思います。
あるいは、ミクロスケールの基礎的な読解力は既に上級レベルまで到達していたような人でしょう。
もしパラグラフリーディングの訓練だけで『安定して上位に入るレベル』に到達しているならば、それで文句無しです。そのまま他教科も固めて志望校を目指しましょう。
しかし、どれだけ訓練をしてもその水準に達しないのであれば、結局はミクロレベルの文の分析力が不十分であるという公算が大きいです。
なぜなら、センター国語をはじめとした長文問題はミクロスケールのロジックも精密に解読できないと解けないような問題だらけだからです。『本文と同じ言葉が出てる選択肢だから』というような短絡的な理由で解くとカンタンに罠に掛かります。
記述式の問題であればなおさら誤魔化しは効きません。

ちなみにパラグラフリーディングも『「しかし」が来たから逆接で重要だ』のような短絡的な当てはめだけでは理解できません。

えっ、「しかし」は逆接で重要じゃないの?

逆接であれば、アウトラインで言うとどのレベルの逆接かを判断する必要がありますし、文次第ではそもそも逆接ですらないかも知れません。

逆接じゃない「しかし」ってあるんですか?

『しかし、海は良きものである。』
逆接ではなく感嘆です。辞書にも載っている使い方です。
もちろんパラグラフリーディング・斜め読みの訓練から得られる単純な解答スピードの向上は大切ですし、マクロ構造からの文章理解ももちろん重要です。
しかし、それらは「精読力」の成長を前提として得られる能力なのです。
パラグラフリーディングは裏ワザ的な小手先のテクニックではなく、あくまでも国語力・英語力の一側面として追々磨くべき能力です。

もちろん、パラグラフリーディングと銘打ちつつも、ミクロスケールの読解面からも正攻法に鍛えるような良書があれば最初から手を付けてもアリだと思います。

でしたら先生が解説してみてはいかがですか?

おっしゃる通りですが近年は著作権の関係で過去問の利用が難しくなっています。そこが公開サイトで講義をすることのネックですね。

先生が本文ごと書いてしまうという手もありますよ?

それはもはや専業ライターか予備校講師の道ですね。
実践的な解説はいずれ活動の展望が拓ければ検討したいところです。
長文読解のためのオススメ精読勉強法・学習方針

ここまでの考察を踏まえ、私の推奨する学習方針を整理してみます。
まずはミクロの精読訓練から、丁寧かつ量をこなす
まずは着実に一文単位のミクロレベルで文章を読めるようになる、という水準が土台となります。
私の経験上、国語・英語を苦手とする生徒さんの多くは一字一句を追うのに精一杯で、そもそも文を頭の中にインプットすること自体が苦手なケースが多いように思われます。
そうなると、社会や数学などの他科目でも問題の読み間違いが多くなりがちなはずです。このようなミスはケアレスミスではなく単純な読解力不足です。
そのようなケースに心当たりのある方は、最優先で精読する経験を積むべきです。
単純にインプット訓練の絶対量が少ないことが原因であれば、読書は非常に有効な訓練方法です。(読書についての考察は過去記事を参照。)
ただし半睡状態でネットサーフィンをする時のような『流し読み』は精読力の訓練に向きません。上手く読めない部分を毎回流してしまっては進歩が難しいからです。
また、『活字が苦手』というのは一朝一夕で克服できるものではありませんので、趣味として楽しむような姿勢の方が結果的に長続きするでしょう。

取っ掛かりは文字の多めなライトノベルなどでも構いませんので、読み飛ばさずに一文ずつ丁寧に読んでみましょう。そして分からない言葉はその都度ググりましょう。(ググる習慣については過去記事を参照)
一字一句を読み飛ばさずに目で追い、分からない言葉や漢字は読み飛ばさずにググり、そして内容を自分の頭で考えながら読み進めます。
自信がなければ、焦らずに1行ずつ読んで意味が理解できているかを「1行ずつ」考えてみることが大切です。さらに言えば、古文に限らず現代文でも品詞分解をしてみるのも方法の一つです。
そうして活字を読むこと自体に慣れてきたら、長文読解のカンタンな問題集に取り組んでみましょう。ここでもまだパラグラフリーディングなどを意識する必要はありません。
時間は後回しでまずは一文ずつ読めるようになることが大事です。

ここから先はパラグラフリーディング系の説明ですが、そうした訓練に手を出さずにそのまま精読一本で訓練し続けるのも一つの道です。
マクロ視点のパラグラフリーディングは基礎力がついてから
そうしてフォーマルな文書もある程度読めるようになったら、あるいは最初から一定以上の精読ができるのであれば、並行してマクロの文章構造を意識するようにしてみましょう。
※マクロ視点から見た文章構造等については、過去記事で解説しています。→文章構造図 パラグラフリーディング
マクロ構造の訓練に取り組む場合は、逆に書籍のようなボリュームの文章は向きません。
そのまま中高生向けの長文問題を練習台として利用するのが良いと思います。
難易度の一段階低い問題集から始めるのも一つの手ですし、パラグラフリーディング系の書籍を検討しても良いです。
まずは単純な対比構造や明らかな逆接、問題提起、結論といったようなカンタンな部分だけでも構いませんので自力で分析してみましょう。
そして解説を慎重に読むと、マクロな文章構成の観点からの説明が書かれてあることに気付くはずです。(逆に、そこが解説に載っていないような問題集は長文読解の訓練としてオススメできません。)
そうして経験を積んでいくと、マクロスケールのカンタンなパターンの組み合わせが一つずつでも分かってくるはずです。
結果として、一つのパラグラフが全体の文章構成の中でどのような位置づけにあるかも少しずつ分かってくるはずです。
例えば、「ああ、これは反論の前フリのための一般論か」などです。
そうすると一文一文の情報の位置付け・重要性も高い精度で速く判断できるようになり、ミクロの読解スピード、『速読力』も向上していきます。
※特に長文読解で時間の足りない方は先にパラグラフリーディングに手を出しがちですが、むしろ精読が本当にスムーズに出来ているか確認するのが先決ではないでしょうか。

語彙力・文法力・知識力不足はパラグラフリーディングや速読術では解決できません。その時は基礎に戻りましょう。
読書での読解力向上法:三日坊主の文学より興味あるライトノベル

本当にラノベで読む練習になるの?賛否ありそうだけど。

興味のない推薦図書や文学などを嫌々読んで三日で挫折するパターンが一番無意味です。逆に読書離れに拍車をかけるだけだと思います。

あるある過ぎて困る。教育的に云々言われるほど萎える。

それこそがモチベーションの問題です。むしろ、賛否など気にせずライトノベルを読み漁った方が遥かに有益です。

……ちょっと本屋に行ってくる。
読みたくない文学を無理やり1冊読まされる時間と労力と苦痛を考えると、興味の湧くライトノベルを集中して自発的に何冊も精読した方がより合理的に読書経験を増やせるのではないでしょうか。
それに、そもそも読書嫌いになってしまっては何の意味もありません。
本来は『ライトじゃないノベル』に手を出すのは後でも構わないはずです。

私は推薦図書でも楽しく読めます。
読み始めたらついつい感情移入してハマってしまいます。

そう感じる人ならそれで良いのです。大切なのは「継続」です。

ちなみに、先生は中学校の読書の時間に何を読んでたのですか?

えーっと……あっ、そういえば漢検の問題集をやっていましたね。
知的好奇心から、気付いたら自発的に取り組んでいました。

とってもタイムリーなチョイスですね!
では、私たちにオススメの本を1冊紹介するとすれば何ですか?

今の時代ならばITパスポートの解説本がオススメです。
有用性でも論理性でも右に出る推薦図書はそうそう無いと思います。
※ITパスポートとは、IT初級者にとって必要となる幅広い知識を問う国家試験のこと。

ありがとうございました!
……ヒトって根本は変わらないものですね。
まとめ
以上より、まずは正攻法の『精読』を通じて活字自体に慣れ、語彙力を高め、一文一文の意味・ロジックを読解できるようになるというステップアップの積み重ねが大切です。
もしも『精読』が苦手のままであれば、数学や社会などの他科目でも問題文の読解ミスが頻発し続けることでしょう。国語力不足がすべての科目にマイナスの影響を及ぼしかねません。もちろん英語も問題自体が日本語ベースであれば同じ話です。
そして、『速読』『斜め読み』『パラグラフリーディング』というのは裏ワザ的なテクニックではなく、『精読力』すなわちミクロスケールの読解をマクロ視点からも同時に捉えて補助する技術です。
あくまでも『精読』が読解力の基礎です。
だからこそ、いかに正攻法である一文一文の論理的読解力を効果的に磨くかが国語・英語学習の焦点となります。そしてパラグラフリーディングは精読力と組み合わさることにより真価を発揮するのです。

そのための基盤となる情報を提供してきたのがこれまでの私の記事です。……もっとも、ここまでの記事を全て精読していただけたのであれば、それだけで間違いなく相当の訓練になっています。
NEXT →






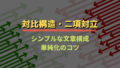

コメント