論説文では、「世間一般ではこう言われている」「このような意見もある」というような、いわゆる一般論がよく使われます。
この一般論の部分を筆者がどのように利用しているかが分かれば一気に文章読解がはかどっていきます。
逆にここを意識しないと、筆者の主張とそれ以外との区別がつかなくなっていきます。特に、主語が明示されていないケースでは読み流されがちです。
例えば一般論がただの道具だったならば

では前回の続きに入ります。
次の文章を読んで問いに答えよ。
②その主眼となるのが、温室効果ガスの削減である。二酸化炭素の削減もこれに含まれる。温室効果ガスを削減することによって、温暖化が食い止められると識者は主張している。
③この点について、よく議論する必要がある。
問1、以下の選択肢の内容が筆者の主張として適当か否か答えなさい。
(1)地球温暖化対策を推進していくべきである。
(2)温室効果ガスを削減することによって、地球温暖化が食い止められる。
(1)は前回・前々回で解説しています。
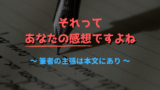
他人の主張を「利用」するのが論戦の場
「(2)温室効果ガスを削減することによって、地球温暖化が食い止められる。」
筆者の主張としてはもちろん×ですね。

ちょっと待って!?これ、本文にそのまま書いてあるよ!

「識者は」って言ってるけど、実質は筆者の主張じゃないんですか?

言う通り、「識者の主張」です。「識者の主張」だから筆者の主張とは違います。

えっ、じゃあなんでこの筆者はわざわざ温室効果ガスの削減がどうのとか書いてるの?

筆者の主張に「利用」するために引き合いに出しているだけです。
そして、この例題の文章だけでは、識者の主張をどのように利用しているのかがまだ分かりません。

「利用」?よくわからないなあ……。
この辺りは論説・論文に慣れないとなかなかつかみにくい部分だと思います。
一般論の意味、反対説としての一般論の機能
では、この問いを考える前に、本文を論理的に読解していきます。
問題提起と一般論

では、この段落①は筆者の主張ですか?

うーん、なんか主張してる感じじゃないな~。
これはいわゆる「問題提起」の段落です。
問題提起というのは文字通りこれから考えていくべき問題を持ち出すことで、要するに前振りです。
例えば、地球温暖化問題の全般を語るのに序盤がいきなり
「メタンは温室効果ガスである。水蒸気にも温室効果がある。大気中の濃度は……」
と具体的で細かいデータを延々と語られても、「えっ?メタンの話題?気体の話題?化学?」と、話題にしたい方向性があいまいになります。本来そのような各論は論証を進めるなかで挿入されていく部分です。
そこで最初の段落が
となっていれば、「ああ、世界的に問題となっている地球温暖化対策についての文章なのだな」とこれから話題にするメインテーマが読者にハッキリと伝わるわけです。
基本的に、最序盤のパラグラフに問題提起が来るというのが王道パターンです。
そして、この段落①こそが当記事の冒頭で話題提起した「一般論」を使っているのです。

「世界的に問題になってますよね?ね?一般論でしょ?みんなそう思ってるでしょ?じゃあみんながこう思ってるであろうことに対して私の考えを主張しますよ」
一般論とはイメージ的にはこのような感じです。
論説文を書くような専門家からすると、一般論とは「専門外の一般人の多数意見」、あるいは「他の専門家がよく主張している論理」といったようなものです。
「最初に問題提起・話題提起」が頭にあれば、逆にパターン崩しにも気付きやすくなります。国語の本文というのは本の一部から切り取って引用している場合が多いため、本来の第1段落とズレた段落から始まっているケースもありえます。
一般論は「利用」しやすい
論説文において筆者が一般論を出してきたときは、ほとんどのケースで以下の3パターンの展開になるはずです。
- 一般論から順当に話を拡げて筆者の主張を上乗せするケース(援用)
「弾幕はブレインと言われる。そう、相手の動きを予測し計算するのだ!」
- 一般論も一理あると認めつつもより良い対案として筆者の主張を持ち出すケース
「弾幕はブレインと言われる。一理あるが私はむしろアートだと考える。」
- 一般論を否定するために出しておいて筆者の主張の方が正しいと持っていくケース
「弾幕はブレインと言われる。しかし、本当は弾幕はパワーなのだ!」
特に重要なのは3つ目の一般論や他者の意見を否定するパターンで、これは(not 他人の意見) but 自分の考えの構造そのまんまです。
なお、2つ目は(not only 他人の意見) but also 自分の考えの構造です。
これらに当てはまらないイレギュラーでも、この3ケースが頭にあれば「あ、この一般論、どういう立ち位置?」みたいな具合に注意ができます。(そのイレギュラーを狙って出題に絡めてくる可能性もあります。)
反論に「利用」するための反対説
はい、この段落②は問題提起①の具体化ですね。
冒頭の「その主眼」というのが前文である段落①を受けています。
ここで指示語が何を指しているかがポイントになるのですが、指示語も超重要論点ですので次の記事で解説します。ちなみに段落③も指示語がポイントになります。

では、この段落②は誰の主張でしょうか?

段落①が問題提起の一般論で、そこから具体的な温室効果ガスの話になって……識者の主張につながる?

そうです。一般論の延長として識者を出してきているだけです。ここでいう「識者」も筆者からすると一般論と同じような位置付けです。

うーん、でもやっぱり筆者の主張と何が違うか分からない……。

それでは、実際に分かりやすい例を見てみましょう。
では、もしも元の文がこのように続いたらどうなるでしょうか。


あー、フルボッコに批判するために吊るしてただけだったのか……。

そうです。「筆者が挙げたから即ち筆者の主張」ではないのです。
これは古今東西で使い古されてきた常套手段です。
すなわち、反対説を取り上げて否定することで自説の正しさを強調する手法です。
自説のためなら反対派でも利用する、それが国語の世界、ひいては論戦の世界なのです。
ここまで全面的に否定しなくとも、一般論が出たときは大抵が「みんなの思ってることはごもっともだが俺の考えは違った」といった感じで筆者独自の主張を際立たせるような使い方が多いです。

なぜなら、一般論にそのまま主張を付け足すだけの素直な文章構成では問題がカンタンになりすぎるからです。
※他にも、出題元の書籍としては読者の気を惹くという重要な役割もあります。

メタな事情ですね。

国語や英語などの長文読解で良い問題というのは、何となくでは絶対に解けず、ロジックを正確に分析できてはじめて解けるような問題です。だからこそシンプルな構造の文章は選ばれにくいです。
まとめ
このように、言論の世界では筆者の主張とは違う主張も道具として平然と使われていきます。
一般論はそうした道具の一つに過ぎないことの方が多いです。逆に、道具として利用価値が無ければわざわざ一般論を挙げる意味がありません。
だからこそ、そのパラグラフ(段落)が誰の主張なのか、ただの具体例提示なのか、筆者がどのように利用しているのかを整理して読むことが大切です。
NEXT →






コメント