
『学習目標を立てましょう』とか言われても、理由が分からん。

ああいうのって、気持ちの問題なんじゃないの?

でも、そもそも目標の立て方が分からないんだよなあ。

では、目標を立てる目的とカンタンな目標の立て方を解説しましょう。
ポイントは前回記事と同じく、自分の向かっている方向性を掴むことです。
加えて、今回は時系列・スケジュール感覚が重要になってきます。
目標を立てる意味・目的はロードマップ(行程表)にあり
はじめに、そもそもなぜ目標を立てる必要があるのでしょうか。
――それは、ロードマップ(行程表)に計画を落とし込むためです。

……ロードマップ?なにそれ?

では、ロードマップについて具体例で考えてみましょうか。
例えば、実際に今いる場所からどこか遠く離れた場所へ移動すると考えてみましょう。
ここでは、「長崎から大隈講堂(早稲田)へ行くには?」でシミュレーションしてみます。
長崎の部分は実際にお住まいの地域に置き換えてください。(逆に首都圏の方はそちらから長崎へ行くには?と考えてみて下さい。)

そんなの、テキトーに旅行会社に申し込めばいいんじゃね?

そんなニッチな旅行プランは無いんじゃない……?

では具体的に移動ルートを示してみて下さい。

うーん、飛行機?バス?なんかあるんじゃない?

言われてみると、具体的にどうやって辿り着くかはよく分からないですね。
それでは、長崎から大隈講堂へ移動する為のロードマップの一例を具体的に示してみます。
- 空港行きのバス乗り場へ徒歩で移動する。
- バスで長崎空港へ移動する。
- 飛行機で長崎空港から羽田空港へ移動する。
- 東京モノレールで羽田空港から浜松町駅へ移動する。
- 山手線で浜松町駅から高田馬場駅へ移動する。
- 東西線で高田馬場駅から早稲田駅へ移動する。
- 早稲田駅から徒歩で大隈講堂へ到着。

ここでは省略しましたが、実際は空港であれば手荷物検査を完了させておくべき時刻、鉄道であれば所要時間も必要になってきます。

うわ、面倒だなあ……。

でも、ルートを一つずつ進んでいかないと目的地には辿り着けないんじゃないの。

そのとおりです。そして、目的地が決まらないとロードマップも立てられないのです。

そっか!勉強も目標が無いと何をどう勉強すればいいのか分からないってことなんですね!

あ、目的地まで『ワープ』は出来ないってことか。

『千里の道も一歩から』という言葉通りの話です。
もしも高校生で早稲田大学を目標に勉強するとすれば、まずは高校3年間分の学習を先駆けて終え、受験科目の基礎固めをして、模試などの実戦形式で合格圏を目指し、それから受験に臨むはずです。
そして、仮に早稲田を目標とするならば、一般的な学習過程では習わないレベルの勉強を進めていく必要があります。例えば社会であれば、東大でも出ないような知識までカバーする必要が出てきます。
こうした学習内容は、早稲田を目標に設定したからこそ必要になってくる勉強です。

目標設定をすることではじめて『やるべき勉強内容』のロードマップが立てられる、とも言えます。
こうした話は、大学受験に限った話ではありません。
中学・高校受験や資格試験でも同じ理屈ですし、ロードマップはそもそもビジネス・マネジメントの観点から扱われることが多い思考枠組みです。
長期目標・中期目標・短期目標から学習計画を立てる

それでは、具体的な目標の立て方の例を考えていきたいと思います。
究極の長期目標は「将来の夢」、無ければ方向性を考える
まずは、前回記事で解説した将来の夢こそが究極の長期目標になります。
つまり、人生全体を通じて何をやりたいかということです。(この点はAI技術が発達するほど人間に強く求められる部分です。)
ですが、前回も述べたように、将来の夢は誰にでもあるわけではないのもまた事実です。私自身もその一人です。

そのような方はザックリとした方向性から考えてみましょう、というのが前回の話でした。
例えば「なんとなくビジネス方面が面白そう?」と考えるならば、文学部よりも経営学部を目標に据えた方が比較的良いはずです。
あるいは、「これからはIT分野が需要高いんじゃね?」と考えるならば、バイオ系や化学系よりも情報系を目標に据えるはずです。
こうした方向性は自分自身の人生選択に直結する問題ですので、自分自身の方向性がよく分からない方は、是非とも前回記事も参考にしつつ自己分析を進めていくことをオススメします。

方向性がどうしても定まらなければ打算でも構いませんし、いっそ偏差値の目標だけ設定して合格後に選ぶのも一手です。
当面の長期目標は試験の最終合格、ここが学習計画の基点
マクロスケールの方向性を見定めたら、次は当面の長期目標の設定です。
例えば一般的な高校生であれば大学受験合格か就職内定になるでしょうし、資格試験であれば最終合格がゴールになります。
こうしたゴール地点を見据えないと中期目標も短期目標も決めようがありません。
極端な話をすると、最難関レベルの医学部を目指すならば学習計画の内容が全く違ってきます。
そうした受験生であればもちろん全科目を高い水準に持っていかなければなりませんし、1~2浪程度は普通に計算のうちに入ってきます。
一方、例えば現役で安全圏の少し上を目指しつつ滑り止めも複数併願するようなケースであれば、必要となる学習内容のペースは最難関を目指す場合に比べると確実に下がります。
こうした目標は、もちろん後で軌道修正しても構いません。
ですが、まずは目下の目標地点を決めないと走る方向もペースも分かりませんし、学習指導のアドバイスのしようもありません。
もし進学する意志が無いのであれば、仮に勉強をサボったところで何も責められるいわれはありません。
あるいは、ドイツのマイスターのように職人一筋を目指すならば、学ぶべき内容も必然的に大きく異なってくることでしょう。

逆に言うと、目標があるからこそ目標達成の手段として勉強する必要性が生じる、とも表現できます。
では、ここでは前々回記事でS君が断念した日東駒専を長期目標としてシミュレーションしてみましょう。
試しに専修大学を例に取ると、経営学部・人間科学部の偏差値55が最高で、受験科目は国語・英語+社会1科目選択となっています。
ですので、ここでの長期目標は「国語・英語・日本史Bの3科目合計の偏差値を55以上にする」こととします。
そして、試験日が2月上旬ごろですので、日程的に余裕を持って12月の模試までに合格圏に入ることを目標としておきます。

先ほども述べたように、後で軌道修正する分には構いませんので、まずは暫定でも具体的な目標を定めてみましょう。
中期目標は各時点での到達目標をザックリと割り振る
次に設定すべき目標は、中期目標です。
中期目標というのは、長期目標へ向けての途中段階でどこまで到達しておくべきかを目印として決めておくものです。通常は複数の段階ごとに設定します。
例えば、高2の3月時点で偏差値47の生徒が、上の例で挙げた専修大学の最高難度(偏差値55)を目指すとしましょう。(※最高難度を視野に入れておけば学部の選択の幅が広がるため)
そうすると、現在地点から長期目標を達成するためには偏差値47から偏差値55まで上げる必要があります。
つまり、1年間で偏差値を8上げる計画が必要ということになります。

偏差値プラス8ってそこまででもないんじゃない?

偏差値+8というのは平均点+8点とは全く違います。偏差値47→55とは平均より下の集団から平均より上の集団に行くという意味です。
※なお、ここで言う平均とは大学受験組の中の平均であって、大学入試の偏差値は一般的には高卒で就職する方を除いた計算になります。

まっ、まあ、努力してればいずれ行けるんじゃ……ない?

忘れてはならないのは、他の受験生も努力を続けている中で自分の順位を上げないといけない、ということです。

現状維持だけでなく更に実力を伸ばさないと届かない、ってことですね。だから目標に沿ったペースの計画が必要になる、と。
では、カンタンに時期を4分割してみましょう。
例えば、5月・7月・9月・11月の4期に分けて、以下のようにシンプルに長期目標を4分割してみましょう。

以下は一例としての説明ですが、各々の目標に合わせて考えてみてください。難関を目指すならばもっと前倒しの計画が必要です。

まず、目標偏差値は、単純に2ヶ月毎に2ずつ増やしてプラス8にする計算です。ここでの偏差値は、全国模試を基準に判断します。
12月の目標偏差値を56にしているのは、多少なりとも余裕を持って合格を目指すためです。
そして、図にある問題集の進捗度というのは、問題集なら何でも良いということではなく、長期目標の日東駒専の合格につながるレベルの問題集をどこまで進めたかの数値です。これも単純に4期で割っています。
つまり、240ページある問題集を3科目分進めるのであれば、2ヶ月で進めるべき問題演習は240ページ×3科目÷4期=180ページとなります。

2ヶ月で180ページ……?それって本当に出来るの?

できるかどうかは自分次第です。ですが、こうして中期目標として「見える化」しないと学習のメドも立てられないのです。

もし中期目標に間に合わなかったら……?

目標の見直しが必要になりますね。その時になったらまたスケジュールの残り日数と必要な演習量から計算し直します。
注意点として、ここでいうページ数はただ形だけ進めれば良いということではなく、内容も十分に理解することが前提のページ数になります。
ここで分からない部分は質問するなり自分で調べるなりして解決することが求められます。
そして、理解度の定着のために解き直しも並行して進めていく必要があるでしょう。
一方、目標偏差値については、この図のように直線的には成長しない可能性もあります。
例えば、単純な知識問題であれば学習量に比例して成績も伸びやすいです。
対して、国語の長文読解などのように能力が階段状に成長するような場合は、途中までは伸び悩む代わりに、あるタイミングを境に一気に成長するケースもあります。

中弛みしないように心掛けつつも、焦らないことです。
短期目標は中期目標から逆算、ほぼ自動的に決まる
続いて、短期目標です。
短期目標で一番の基本となるのは毎日の学習になりますが、加えて1週間単位の学習ペースもあります。(平日と土日を合わせて1セットで考えるため)
言い換えると、どの科目をどれだけの強度でどれくらいのペースで学習を進めるかの目安とも言えます。
これらの点は、実は先ほど立てた中期目標から逆算することによって大体のペースが決まってきます。

例えば、先ほどの中期目標に基づくと、「2ヶ月に問題集180ページ分進める」必要があるという計算になりました。
そこで、2ヶ月を8週間と捉えて、週ごとに演習量を割り振ってみましょう。
なお、ここでは8週間のうち6週間で180ページを進め、ラスト2週間を解き直しや不明点の解明などの予備としてスケジュール確保します。
すると、180ページ÷6週間=30ページを1週間で進めることになります。
更に、1週間のうち5日間を演習に当てて、残り2日間を予備日とします。
そうすると、30ページ÷5日=6ページを1日で進めれば良いという計算になります。

1日6ページなら全然できそうな感じだ。不思議。

これこそが学習計画によって『見える化』した勉強量です。
ここで問題集を進めるペースに大幅な余裕があるorあまりに厳しいならば、目標やスケジュールの条件を変えて再計算すれば良いのです。
具体的には、予備日の設定を増減させたり、長期目標自体を変えて問題集のレベルを変更したりすれば良いということです。
また、実際は科目によってやるべき学習内容も実力差も違ってくるでしょうから、実践する場合は科目ごとに目標を設定し学習計画表を作るのがオススメです。
こうして短期目標が決まれば、あとは具体的な学習メソッドや日頃の勉強の流れが問題になってきます。(この点は当シリーズを通じて解説している部分です。)
定期テストや短期決戦の資格試験では週間・日割りの目標が軸
以上の話は、受験勉強や難関の資格試験などの長期戦へ向けた目標設定の例です。
対して、1~3ヶ月で勝負が決まるような短期決戦の場合は週割り・日割りの達成目標が軸となります。
例えば、全体として600ページ分の学習を2ヶ月で進める必要があるとします。
ここで、先ほどと同じように8週間のうち6週間を問題集etcの進行にあてて、最後の2週間を復習も兼ねた模擬演習に当てるとします。
すると、最初の6週間では600ページ÷6週間=100ページを1週間で進めることになります。
そこから自動的に、100ページ÷5日間=20ページを1日あたり進めていく計算になります。そして1週間のうち最後の2日間をその週の学習内容の復習・解き直しに当てます。
そうすると、最後の2週間の復習は実質3周目の勉強となる計算になります。
資格試験であればここがひたすら過去問演習をする期間になります。

もちろん問題によって出来不出来の差が出るはずですので、そこは予備日で解決するか、いっそ飛ばして先に進んで後で考えるのも手です。
目標設定でやってはいけない失敗例

ここまでサクサクと解説を進めましたが、逆に目標設定でありがちな失敗例についても考えてみましょう。
失敗例①あいまい・あやふやで具体性のない目標設定
第一に、具体性に欠ける目標設定があります。
例えば、以下のような目標です。
- 「しっかり頑張る!」
- 「とにかく良いところに行く!」
- 「勉強ができるようになる!」
これらは具体的な目標というよりは、ただの景気付けの言葉に過ぎません。
なぜならば、後付の主観でいくらでもハードルを変えられるからです。

今日は1ページしか進んでないけどしっかり頑張ったからオッケー!

よほど重要な難所の1ページを超えたならさておき、毎日『1ページでもオッケー!』では問題集1冊分も終わりません。
目標は明確に・具体的に・なるべく客観的な数値で設定しましょう。
- 「1日あたり10ページ分頑張る!」
- 「MARCHの経済学部・商学部を目指す!」
- 「平均点超えを目指す!」
失敗例②あまりにも現実味が無い夢を目標に設定する
次に、あまりにも現実からかけ離れた目標を設定することです。
例えば、毎日の学校の授業についていくので精一杯の高校生が『努力は人を裏切らない!だから東大理Ⅲ(医学部)を目指す!』といった目標を掲げるケースを考えてみましょう。
では、この高校生が東大理Ⅲに合格するためには、現実としてどれほどの勉強が必要になるでしょうか。
実際は、浪人をして毎日10時間勉強したところで受からない人は受からないのが現実です。
なぜならば、現実には競争相手が居るからです。
ですので、目標は「現実的に手の届きうる範囲の中で」一番上を目指しておくのが良いかと思います。あるいは、限界よりもいくらか上を目指すといった感覚でしょうか。
そうすると、仮に一番には届かなくとも、結果的に以前よりも高い水準まで成長することが出来るかも知れません。
そのような場合は、仮に第一目標は達成できなかったとしても、努力目標として機能したことになります。
これは目標設定として失敗どころか成功です。大切なのは実際に成長することです。

でも、ケイスケホンダはミランの10番になって小学生の時の夢を叶えてるじゃない?

本田さんはミランの10番になるまでにどれだけのステップアップを踏んでいますか?どれほど凄まじい努力を積み重ねていますか?
※ジュニアユース→星稜高校→J1(グランパス)→五輪代表・VVV(オランダ)→W杯代表・CSKAモスクワ(ロシア強豪)→ミラン

……ぐうの音も出ない。
失敗③時系列・スケジュール感覚の無い目標設定
最後に、忘れてはならないのはスケジュール感覚です。
例えば、「偏差値を50から70に上げたいです!」という目標を設定したとしましょう。
では、極端な話、大手予備校に10年間通い詰めた末に偏差値70になる形でも良いのでしょうか。
人によっては、本当に10浪して合格を掴み取るケースもあるかも知れませんが、一般的な受験生であればそれは非現実的な話でしょう。
ではここで、先ほどのロードマップをもう一度見てみましょう。

ここで注目すべきは、時間軸を中心に目標設定を割り振っているという点です。
目標を立てる際には、「いつまでにこれくらい成長したいです」という時系列の感覚が必須です。
そこが決まらないと、スケジュールの立てようがありません。
また、10年と言わず、1年スパンか2年スパンかだけでも目標設定が全く違ってきます。
この図の例で言えば、たとえ1年間で偏差値55に到達出来なくとも、2年あればそこまで成長できる可能性は十分にあるかも知れません。
逆に、1年間で偏差値55まで到達できれば、残りの1年間でMARCH(明治・青学・立教・中央・法政)を目標に再設定することも十分に考えられます。

学習面に限らず、時間の意識は非常に重要です。
まとめ
勉強を進めていくに当たっては、大雑把であっても何かしらのゴール地点が定まらないと動きようがありませんし、どのような学習をどれくらいのペースで進めるかといった基本的な学習指導もできません。
目標設定の基本は、まず長期目標を定め、そこから各時点の中期目標に割り振り、更に中期目標から短期目標を算出していくという流れです。
これにより、日々の学習のペース配分に至るまで「見える化」できます。
ただし、目標設定というものはあくまでも学習を戦略的に進めるための目安ですので、実際の成長具合に応じて後から軌道修正するのもまた人生選択の一つです。
結果的に、さらなる上位を視野に入れるのも良いですし、逆に目標を一段階下げてみるのも一つです。
その際には、最初の目標設定のときと同じように、新しい長期目標をベースとして残りスケジュールの中期目標・短期目標を再計算すれば良いということになります。

ここで目標設定が無ければ、行き当たりばったりの学習になります。そうなると、軌道修正以前にどこに向かって勉強しているのかすら見失ってしまいます。
※なお、目標・計画の見直しや再設定という部分は、PDCAサイクルの話に繋がっていきます。
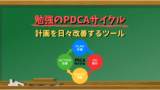
※関連記事
将来の夢が決まらない?進路希望は興味関心・適正の方向性を自己分析するところから|勉強法・教育法⑪
勉強では無駄な努力は報われない!効率的な努力こそが才能と可能性を拡げる|勉強法・教育法⑩
解き直しこそがコスパ最強の復習勉強!模試やテストに限らず問題演習から解き直す|勉強法・教育法②


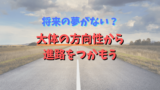



コメント