よく、「国語力の向上のためには読書が良い」という話を聞きます。
果たして、本当にそうなのでしょうか?
この点を解き明かすためには、「インプット」と「アウトプット」の学習の違いを理解する必要があります。

今回の記事は国語を前提に解説していますが、そのまま英語に置き換えても通じる話です。
(ただし英語のアウトプットを本当に正しくチェックするには添削側にいっそう高い英語力が求められます。)
インプット・アウトプットとは
まず、そもそも「インプット」「アウトプット」とはなにかをカンタンに見ていきます。
インプットは情報の入力
インプットとは、入力のことです。
PCで例えるならマウス、キーボード、スキャナ、マイク、コントローラーなど、スマホならばタッチパネルや音声認識システムなどが入力にあたります。
つまり、情報・データを入力することです。
国語でインプットといえば、国語の参考書を読むこと、英単語帳や漢字帳を使って暗記勉強をすること、授業で先生の話を聞くこと、あるいは文章を読むことそれ自体もインプットです。今この記事を読んでいるのもインプットです。
基本的に目と耳での学習です。
アウトプットは情報の出力
アウトプットとは、出力のことです。
PCやスマホで例えるならディスプレイ、スピーカー、プリンターと色々な出力デバイスがありますが、ここでは総じて演算結果の出力と言えます。
具体的には、ソーシャルゲームもポケモンGOもEXCELも音楽もVRも、全てはコンピュータが計算した結果を映像や音声として出力しているということです。
国語でアウトプットと言えば、問題を解くこと、単語や漢字を何も見ずに書くこと、もっと広く言えば作文や小論文などの文章を書くことです。
ネット上でコメントやツイートをするのもアウトプットの一環です。
インプットとアウトプットは両方大事

では、このインプットとアウトプットについて、国語ではどちらが大事でしょうか?

両方大事だと思います。
そうです。
インプットだけで能力が身につくならば皆さんはすでに漢字マスターでしょうし、日本語なんて毎日見聞きしているわけですから誰でもすでに国語マスターでしょう。
しかし実際はそうはなりません。
インプットした知識やノウハウを解答の形で出力できてはじめて国語の得点になるのです。
また、問題演習をすることで、「今の自分は何ができて何ができないか」がある程度見えてきます。効率的な復習はそこから始まります。(解き直しについては別記事で解説しています)
逆に、問題演習でアウトプットだけを練習したところで、分からなかった知識や語彙、問題の考え方などを後でインプットしないといつまでも分からないままなのです。
ですので不明点はその都度調べてインプットしましょう。

ここで大切なのはインプットとアウトプットの厳密な分け方ではありません。「インプット→論理的思考→アウトプット」という一連の流れがすべて重要だということです。
読書はインプット中心の読解力訓練
みなさんも、「国語力を伸ばすためには読書をするべき」といった話はよく耳にすることと思います。
では、インプットとアウトプットという観点から考えた場合、読書はどのような立ち位置になるでしょうか。
もちろん「読書はインプット中心」です。
読書というのは基本的には文章を読む行為なわけですから、自分の脳内への一方通行です。(※国語的には、ここで『基本的には』と書いてある点に注意)

でも、本を読んで内容を話し合ったり感想を書いたり知識として使ったりするからアウトプットにもなるんじゃないですか?

はい、そこまで行くと確実にアウトプットにつながっています。インプットした本の内容を自分なりに咀嚼してから、言葉で表現=アウトプットしているわけですからね。
インプットの訓練自体は大事
では読書でインプットするだけでは無意味かと言うと、決してそうではありません。
国語が苦手な方のなかには、本丸であるロジック以前にそもそも活字を読むのが苦手なケースが多々あるからです。例えば、何度も同じ行を読んでしまったり、そもそも文が頭の中に入ってこないようなケースです。
その場合は、ロジックの読解や解法テクニックなどの前に『文章を自分の頭にインプットする』こと自体を訓練する必要があります。
もちろん読書は語彙力や漢字力の向上にも繋がりますが、そのためには分からない言葉をその都度ググることを強く推奨します。つまり語彙や漢字のインプットです。
分からない言葉を分からないままにしてしまうとインプットにはつながり難いです。
(「ググる習慣」の詳細は前回記事を参照してください。)

読書は、まさにインプット中心の訓練と言えるでしょう。
アウトプットの訓練は読書のインプットとは別物
しかし、インプットとアウトプットは別物です。
例えば小説を3000冊読破した人が小説家になれるだけの文章力を身に着けているかというと、話は全く違います。
逆に一般の読書家よりも読書量の少ない作家も数多いることでしょう。極論を言うと、三島由紀夫のような文豪は、「読書経験の絶対量が少ない小学生」の時点ですでに天才的な文章力でした。
これは、「アウトプット能力はインプット量で決まる」わけではないことの表れです。
横道にそれますが、もし「小説家になろう」と考えるならば、読書だけではなく実際に何かしら作品を書いて訓練するべきだと言うことでもあります。
小説家に限らず詩人でもエッセイストでもブロガーでも同じ話です。
例えば、芥川賞作家の又吉直樹先生は文学好き・読書家が転じて小説家になったケースですが、又吉先生はそれまでにコラムや脚本を数多く執筆してきています。
又吉先生の成功は、むしろライティング=アウトプットを訓練した結果なのです。
「国語の試験」もまた別物

では、そもそも国語を勉強する目的はなんでしょうか?

試験で得点アップするためかな。
……じゃなかったら勉強なんて絶対にしたくない。
別記事でも述べているように、国語の試験というものは、主に論理的な読解力や論述力を判定するための試験です。
記述問題におけるアウトプットは分かりやすいかと思いますが、知識問題、択一問題での正誤判定というのもいわば判断のアウトプットになります。
つまり、記号にせよ記述式にせよ、論理力・国語力を示すための解答=アウトプットができてはじめて目的達成なのです。
そのために必要な技術や本質、学習法の切り口などを解説するのが当サイトの目的です。
私の経験上:読書は国語力に『必須では』ない
「読書はインプット訓練には効果的だが、国語力の向上には決して必須ではない。」
これだけ自信をもって言えるのには理由があります。
なぜならば、私自身が中学・高校の6年間で10冊も読書をしていないからです。
読書感想文は複数のサイトであらすじを読んで共通項の論点を絞り、上手い具合に自分の言葉で膨らませて作っていました。いわばあらすじサイト調査レポートです。
※読書感想文の裏テクニックについてはこちら参照して下さい。
読書感想文で丸写しコピペに頼らない書き方のコツ!裏技はネタバレサイトの活用|論理的思考のコツ㉖
それでもセンター現代文は本番でも100点満点でした。
つまり、私自身が読書は必須ではないことの証拠です。(注意:「必須ではない」≠「意味がない」)
大学以降は相応に読書していますが、小説や文学の類いはほとんど読みません。
ではインプットの訓練をしていなかったかというと、それも違います。
ネットサーフィンでもゲームでも時事でも、分からない言葉は片っ端からググっていました。
つまり媒体が違うだけで、知識の吸収自体はやっていました。(ノンジャンルで無節操に)
仮に国語が得意な人間でも、知識は何らかのインプットを経ないことには身につきようがありません。小学生時点の三島由紀夫も、少ないインプット量から多くを学んで名文を書いていたということです。

文章問題を読解することそれ自体もまたインプットの訓練です。
ましてや今はPC時代をはるかに超えてスマホ時代です。確かにネットの情報は玉石混交ですが、クオリティの高い文章・記事・情報も星の数ほどあります。(当ブログもその中の一つになれるよう精進します。)
従来の紙媒体のライターもネットにシフトしつつあるでしょうし、もちろん学識者や専門家の書いた記事もたくさんあります。

確かに情報を取捨選択するためには結局は国語力がベースとして問われます。しかし、それは紙の本でも同じ話です。
『デジタルだから悪い、アナログの本だから良い』ではなく、目的と、目的達成のための手段という観点から自分で調べて自分で考えることが重要なのです。

利益(学力)さえ上がるならばどのような経営手法(学習法)をとっても良いのです。むしろ手法を選ぶところからが競争です。
ただしコンプライアンス=法令遵守を守った上での話です。
まとめ
読書というのは、数ある手段のなかの一つにすぎません。
スマホでこの記事を読んだりゲームのテキストを読んだり雑学サイトを読んだりすることもまたインプットなのです。
どのような媒体からインプットするにしましても、大切なのはやはり前記事の『自分で調べる習慣』です。
いくら純文学を読み漁ったところで、ただ文面を目で追って受け身で読み流しているだけでは学習効果も限定的でしょう。
逆に読書という形を取らなくとも、知的好奇心に従って自分で調べて自分で考える習慣のある生徒さんはスポンジのように知識を吸収し、思考力も自然と成長していくことでしょう。

勉強は常に手段と目的を意識しましょう。
10を読んで1を得るか、1を読んで10を得られるかはあなた次第です。
(追記)『アウトカム』についての記事が完成しました。

「論理的思考のコツ」シリーズの順路はコチラ




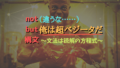


コメント