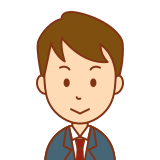
ここまでの二次関数の内容は、ちゃんと分かりましたか?

はーい、分かりましたー。
……「分かった」と口では言いつつも、実際にテストになると解けないケースに心当たりのある方は非常に多いことでしょう。
これはつまり、『分かったつもり勉強』になっていることが主な原因です。
『分かったつもり勉強』は、本人的には何となく分かったつもりになっているがゆえに、本当は分かっていないにもかかわらず理解が不十分のまま置き去りになってしまう危険があります。
こうした『理解しているつもり』『分かっているつもり』の状態を改善するためにはどうすれば良いのかについて一緒に考えていきましょう。

ポイントは、「どうやって具体的に理解度を測るのか」の観点です。
「分かった」と言いつつ何も理解できていない具体例

それでは、「分かった」という言葉だけでは意味がないという論点について、極端な例を挙げてみます。
以前、個別指導塾で私が数回だけ指導担当をした生徒さんがいました。以下、B君とします。
B君は成績も全体的に伸び悩んでいたのですが、伸び悩んでいる原因の真の根幹は学習態度にありました。
こちらがどのように説明しようとしても、B君は「分かった分かった」と話を遮ります。
しかし、実際にその場で同じ問題を演習しても解けていません。
そこで、問題演習の中で分かってないポイントを基礎に立ち返って説明しようとしました。

今間違えた部分はここが問題ですのでもう一度基礎をやり直しましょう、まずは……。

はいはい分かった分かった。

ん?今、ここが解けてなかったのでこの部分の基礎に戻って……。

もうわかったってば。

でも実際に解けてないということは…。

はいはい、分かってないってことでしょ!もう分かったってば!
終始このような調子で、とにかく「分かった分かった」と言って話を無理やり打ち切られ続けました。
問題演習自体は普通に取り組むのですが、こちらがどれだけ穏便にやんわり説明しようとしても「分かった分かった」と話を途中で中断させられました。(問題演習自体はやっていたので、根っからやる気が無いというケースとも違います。)
最後に、このままではB君本人にとって良くないと思い、意を決して言いました。

B君は「分かった」と言って人の話を遮るクセがありますが、しかしそのままだと…。

はいはい、分からないってことが言いたいんでしょ?もう分かったって。はぁ~あ。分かってることをいちいち言わないでよ。
そうは言いますが、もちろんB君の理解できていなかった部分は理解できていない状態のままで何一つ改善していません。
私は引き継ぎの際に、学習内容以前にこのクセを改善することが最優先事項と伝えました。なぜなら、このままの状態では全ての分野で成長が大幅に阻害されてしまうからです。
(ちなみに、後で他の担当講師に聞いても同じような態度とのことでした。)

これって、B君が問題過ぎるだけじゃない?

確かに極端な事例ではありますが、「分かった」と口だけで終わってしまっては意味がないという点では誰もが同じです。
これがたとえ、素直に話を聞いて素直に「分かった」と答えるような生徒さんであっても、実際に理解できていなければ足踏み状態のままだということには変わりありません。
B君の場合はそこに拒絶も加わっていたということです。
理解度の確認方法はアウトカム=問題演習・テストの結果

ここで重要になるのがアウトカム、すなわち結果・成績から具体的に判断するという観点です。
インプットとアウトプットの違いを復習

まずは、アウトカムの前提として、インプット学習・アウトプット学習について復習してみましょう。
インプット・アウトプットについては、読書と国語との関係についての記事で触れましたので、ここではカンタンに復習します。
インプット学習の具体例、ここで止まると『分かったつもり勉強』に……
インプット学習は、以下の2点に集約されます。
- 教科書や参考書、単語帳などを繰り返し読む。
- 先生の話やリスニング練習用CDを聞く。
インプットとは「入力」のことです。
ここでいう入力とは、脳に知識や情報を蓄積していくということです。
実は学習がこのインプット止まりになってしまうと『分かったつもり勉強』になりやすいです。
インプット学習は当然大切ですが、どこまでインプットできたかを測るのはまた別の話ということです。
アウトプット学習の具体例、インプットした中身を自分なりに咀嚼して表現
ここで大切になるのがアウトプット学習です。
アウトプット学習は、自分から何かしら能動的にアクションを起こす学習であれば大抵は当てはまるかと思います。
- 実際に自分の主張・考えや英語のスピーチを話す。
- 問題演習での解答や作文・小論文を書く。
アウトプット学習のポイントは、インプットした知識やノウハウを何らかの形で自分なりに表現できるかという点です。
英語の和訳も、仮にニュアンスがネイティブ並みに理解できたところで、日本語としてアウトプットできないと意味がありません。
択一式でも、知識を元に「ここが違う」「これは合ってる」という根拠から判断して答えを出す必要があります。
択一問題の王道の解き方である消去法も、選択肢のどの記述がどう誤っているか具体的に判断してアウトプットする手法です。単なるマルバツゲームではありません。
勉強の目的は成績の向上、だからこそアウトカムで理解度を測る

ではアウトプット学習もきちんとやりましょう、ということですね。

それはもちろんですが、理解度を確認する為にはアウトカムの視点まで踏み込むことが大切です。
アウトカムとは具体的な結果や成果のことであり、ビジネス分野でも研究分野でも幅広く使われる概念です。
ビジネスや研究では「そもそも成果とは何ぞや?」という部分から話は始まるのですが、学力試験の場合は最初から問題が設定されているため、ここでいうアウトカムは問題の出来具合であると言えます。テストで言えば点数や偏差値です。
先ほどの話と絡めて学習におけるアウトカムの流れを簡潔に述べると、知識や考え方をインプット→問題演習でアウトプット→問題の出来具合がアウトカムということになります。

二次関数の学習の例で具体的に考えると、このようになります。
- インプット:因数分解、平方完成、頂点、x軸との交点といった各要素について授業を聞き、参考書や解説などを読む。
- アウトプット:各パターンの問題演習をする。グラフを書く。
- アウトカム:問題演習をした結果としてどれだけの問題を正解できたか、答えだけではなく解答の過程も正しく示せているか、間違えた場合は具体的にどこを間違えているか。
ところで、勉強のそもそもの目的とは何でしょうか。
それは、大半の人にとっては成績アップ・試験合格であるはずです。
目的が成績アップなのですから、理解度の確認は実際の成績で測るのがもっとも直接的かつ合理的であると言えます。
一つの単元であれば、その単元の小問が「実際に解けるか」がポイントです。例題の1問だけをとってみても同じ話です。

言われてみれば当たり前の話だよね。

では、冒頭で「分かった」と言っていた二次関数の問題は実際に解けますか?今ここで解いてみて下さい。

あっ、えっ、えーと…………分かってなかった。
ここで問題が解けなければ、再度復習をしたり質問したりすれば良いのです。
そして、このアウトカムで理解度を測るところから解き直しのサイクルは始まっていきます。
「分かりました」ではなくその場で自分の言葉に置き換えてみる

でも、そしたら「分かりました」以外になんて答えれば良いの?

少人数の場が前提ですが、私であれば「それはつまり○○という認識で良いですか?」とその場で自分の言葉に咀嚼して説明してみます。

わざわざ聞き返すのって、迷惑じゃありませんか?

相手の性格による部分もありますが、指導側からすると、聞き手側が誤解したまま突き進んで失敗してしまうことこそが問題です。
せっかくですので、一つシミュレーションをしてみます。
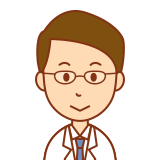
これこれこうこうして、この平方完成の形を作るのがコツですよ。

これはつまり「まず最初に2乗の形を結果ありきで作り、そこから定数項の辻褄を合わせる操作をしている」という認識で良いですか?
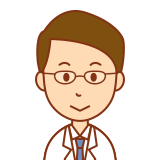
はい、そういう感じですね。平方完成で勝手に付け足した定数項の部分を後で足し引きして、変形前の式と合わせてるんですね。
この例は最初から分かってる人間のヤラセ問答ですが、ここで理解があいまいになっていれば自分の説明もあやふやになりますので、教える側もそのことに気付きます。
そうすると、教える側は追加の説明をしてくれることでしょう。(時間的余裕があれば)
これによって、生徒側はより良い理解を得られ、教える側もより良い仕事ができて、まさにウィン・ウィンの関係になります。
応用:「クリエイティブ」こそ形に出来るかが勝負

まあ、言ってることは分かったけど……おいらは「クリエイティブ」な道を目指してるから……。

それはそれで全然アリですよ。……では、試しにクリエイトしたものを見せてもらえますか?

いずれクリエイトできる……はず……迸るポテンシャルが……。
当サイトでは主に合理性・論理性といった側面を重視していますが、「創造性・独創性を豊かにする」こともまた教育目的として大切であるのもまた違いありません。
一方で、どのようなクリエイターでも具体的な形として表現してはじめて評価されるという点についてはよくよく考える必要があります。
絵画や音楽、執筆活動といった伝統的なものはもちろんのこと、近年になって大人気のYoutuberもまた動画という形としてクリエイトし世に発表しているという事実があります。
これらもまさしくアウトカムです。
具体的に五感で認識できる形としてアウトプット(制作)したからこそアウトカム(作品)として評価された、ということです。
ましてや学力試験であればなおさらです。
まとめ
「分かった」と頭では思っていても実際は理解できていないというのは人間の常です。
逆に教育指導をする立場からすると、「分かりましたか?」と聞くだけでは相手が本当に理解できているか判断がつかないということです。それは勉強に限った話ではなく、仕事上でも同じ話です。
一方で、問題演習の出来具合=アウトカムを判断基準にすると、具体的・客観的に理解度が確認できるということです。
勉強の目的は「問題が解けるようになること」ですから、言い換えると問題が解けてはじめて勉強が実を結んだとも言えます。
だからこそ、単に「分かった」では終わらせず、実際に問題が解けているかを常に確認することが最も確実な理解に繋がります。

くれぐれも、今回のアウトカムの話を「分かった」と頭の中だけで済ませないようにご注意下さい。まずはカンタンな例題からでも良いですので、問題をその都度解いて確かめてみることです。
→ NEXT

※読書を通じたインプット・アウトプット学習について
国語力アップに読書量は無関係?アウトプット訓練とインプットの違いを知る|論理的思考のコツ③
注意:本当はそこそこ以上に理解できているにもかかわらず、失敗を恐れて手が動かないケースもあります。




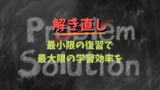
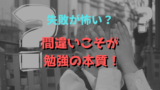

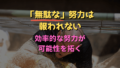

コメント