勉強を教える側に立ってみると、気づくことがあります。
それは、「教えている側の方が理解が深まる」ということです。実際に教える側に立ってみれば、大半の人がその点を大なり小なり体感するはずです。
そこを逆手に取って自分の勉強に活かす方法こそが「一人エア授業」です。
一人エア授業とは、カンタンに言えば『まるで他人に教えるかのように自分の言葉で説明する』という方法です。
これは、京大出身のロザン宇治原氏を通じて紹介されるよりも前から、知る人ぞ知る学習効果の高いアウトプット学習法でした。あるいはセルフレクチャーとも共通する手法です。
何を隠そう、私自身も気付いたら独自でやっていた手法ですので、実演も踏まえつつカンタンに解説します。

一人エア授業は社会人になってからも末永く役に立つメソッドです。
エア授業=アウトプット学習は誤魔化しが利かない
具体例:冠詞aとtheの違い、不特定多数について自分の言葉で説明

唐突ですが、具体例を一つ挙げてみましょう。
※生徒の方も実際のプレイを見て知っていると仮定します。

ああ、アレだ!「the kobold」はまさにコボルト感がスゴいんだよ。その辺のコボルトとは別格!
※例えば、ボクシングの井上尚弥選手の愛称「モンスター」を英語圏の人が「The Monster」と表現するケースなど。まさにモンスターそのもの。

でも、『同じ雑魚モンスターでも』って書いてない……?

ぐぬぬ……。何となく勘では違いが分かりそうなのにな……。

では、このケースでの「aとtheの違い」について、私の言葉で説明してみましょう。
その辺に何匹もゴロゴロ群がっているようなコボルトは端から見たらどれも違いがありません。ゲーム的に言えばパラメータもグラフィックも同じです。そのうちの1匹のコボルトを指差したとしても、他のコボルトを指したとしても、特に何の違いも意識していませんし、違いも分かりません。
これこそが不特定多数の意味です。だからこそ、どのコボルトを指しても「a kobold」です。まさに「不定」冠詞です。
さて、この中の1匹のコボルトがケンカを売ってきたとしましょう。すると、この見た目にもパラメータにも違いの無いコボルトは、「自分にケンカを売ってきた生意気なコボルト」としてその他大勢のコボルトと意識的に区別されます。プレイヤー的にも、このコボルトは敵として他と区別しています。
だからこそ「the kobold」となるのです。

ああ、そんな感じ。うん。分かってた。

それを自分の言葉で説明できるかどうかが理解度の差ということです。
※なお、今回の説明はあくまでも定冠詞theの一側面に過ぎません。
本質的な理解力は「自分の言葉でアウトプットできるか」が指標
物事が本当に理解できたかどうかは、「アウトプットできるかどうか」次第です。言い換えると、「実際に自分の言葉で説明できてはじめて理解できたと言える」とも言えます。
何となく解説を読んで『分かったつもり』になっただけでは説明はできません。
先ほどの「aとtheの違い」と言った話も、『aは不特定多数でtheは特定』のように単に丸暗記ができたとしても実際の英文で応用できるかはまた別の話です。
例えば、メタな話をすると、まず「あっ、あのコボルトの話は説明に使えるな」と適切な具体例を選ぶ時点で理解度の差が出ます。
国語や英語の論説文でも『抽象論から具体例』という流れは鉄板ですが、そのトピックを本当に理解していないと具体例も挙げようがありません。

逆に、「適切に説明できるかどうかで本質的な理解力を測る」という指導技術もあります。
※スポーツや職人技などは感覚の部分も大きいのですが、学術分野は『客観的な論理』がベースですので、他人に説明できないと論として成り立ちません。
一人エアー授業で説明することが学びにつながる
以上より、「他人に説明してみる」ことが強力なアウトプット学習になると言えます。

でも、教えるのって相手が必要ですよね。

もちろん相手が居たほうがより実践的ですが、相手が居なくても一人エア授業で同じようなことができます。
一人エア授業というのは、エアギターのように架空で授業をするということです。
まずは何より、具体的に言葉で説明する必要がありますし、理解が難しい点を明確に噛み砕いて説明する必要もあります。
こうしたシミュレーションは、授業と言いつつも自分で自分に説明する行為です。
逆に、自分自身に対して説明できないレベルの理解度では、他人に説明はできません。
試験で言えば、自分で説明できないことは答案にも書けず、採点官に評価してもらうこともできない、ということです。特に論述式の問題では重要なポイントです。

なんとなくそれっぽいことを書いて誤魔化せば、採点官がなんとなく意図を察して点数くれるんじゃないのかな?

それはただのまぐれ当たりか採点ミスです。
消去法の記事でも解説したように、択一問題でも選択肢の正誤を判断するための論理的な根拠が必要です。
そして、記述式・論述試験であれば、答案にアウトプットされた記述が全てです。公平な採点官であれば忖度などは一切してくれません。
このようなアウトプットの能力を磨くためには、実際に自分の言葉で表現する訓練が一番です。
そうした点で、エア授業というのは極めて実践的な学習法なのです。
一人エア授業の考え方は仕事にも応用できる合理的メソッド
こうした一人エア授業は、私自身も学生時代からやっていた手法ですし、社会人になってからも自然と利用しています。
勉強に限らず、仕事上のややこしい部分などがあった場合にも、まずは自分自身に説明するつもりで情報整理してみます。
そうしていくうちに複雑だった部分が解きほぐれていき、各要素に対する解決策や段取りのフローも見えてきます。
そうすると、自分自身が効果的に仕事を進められるという点はもちろん、他人にも説明できるような仕事の仕方ができます。
これは、いわゆる「属人的な仕事を減らす」ために重要なメソッドです。

もちろん、プレゼン能力自体の成長にもつながります。
大事なのはロジックを組み立てて言語化するプロセス、推理形式でも可
ここで、エア授業とは銘打っていますが、アウトプットにつながっていれば講義形式にこだわる必要はありません。
大事なのは言語化する際の思考プロセスです。
例えば、アニメやマンガで探偵が推理する際に、『いや、これはこういうことだから……そうか!つまりAがBだからCということか!』みたいな光景はよく目にすることと思います。

見た目は子供で頭脳は大人っぽい探偵とか、じっちゃんの名にかけてるような探偵とかね。

そう言われてみれば、名探偵の人達って、犯行のプロセスを整理して順序立てて言葉で説明してますね。

それこそが論理展開ということです。そして、論理的思考を磨く最善の道もまた「自分で言語化すること」です。
言い換えると、理解度が一定水準に達することではじめて、ゼロからロジックを組み立てて自分の言葉で説明できる、ということです。
逆に、理解度が不十分で知識もあやふやな状態では、ゼロから自力で説明を組み立てるのは至難の業です。
一人エア授業実演:willとbe going toの未来表現の違い

それでは、私が実際にエア授業を実演してみましょう。
お題は、「will」と「be going to」の違いです。

『willとbe going toは書き換え可能な未来形』じゃないんですか?

実際はニュアンスが違いますが、その辺りは各々の語学力や関心に応じて自主的に学べば良いかと思います。
以下、書き言葉に直さずあえて話し言葉のまま表記します。
※なお、今回は『自分が理解する用』の推理・エア授業ですので、言葉遣いは雑で良いです。
~エア授業(推理)スタート~
「will」と「be going to」の違い……。
なら、「will」ってそもそもなんだ?
これはそもそも名詞の『意志』だ、カタカナ語の『ウィル』と根は同じじゃないか。それが助動詞としても使われてるってだけだ。
ってことは、結局のところ、話者の主観的な意志ってことじゃないか。
例えば「willはその場の思いつき」って使い方、その場で思いついたなら「話者自身の主観的な意志」以外のなにものでもないじゃないか。当たり前の話だ。
そうすると、つまり、まだ起こってない未来を主観で推察してるのがいわゆる未来形のwillってことになるんじゃないかな。
あるいは、『強い意志』ってのも、結局はwillの強さが変わってるだけじゃないか。これは古文漢文の「けだし」と同じ話だ。
『本人の主観をあえて表す時』とかも、結局はwillの主観性が強調されるってだけの話だな。
結局は全部『willは主観的な意志』ってだけの話じゃないか。それ以外のケースは例外ってことで。
なら、be going toってなんだ?
これはそもそもgoの現在進行形じゃないか。
で、goってのがまさしく『ある状態へ向かって進行してる』って感じじゃないのか。
で、進行形なんだから、『今より前から始まってて、今も進んでて、未来へ向かっても進んでいく』ってのは最初から当たり前の話なんだ。
そうじゃなければ進行形は使わんだろう。
そうすると、そりゃあ「すでに決まってる予定」とも言えるし、「確定的な(蓋然性の高い)未来」とも言えるわけだ。まさに『現時点で進行してること』なんだから。
客観的って部分もそりゃそうだ。
willやPerhapsみたいな主観的なニュアンスを表す単語が入ってなかったら、そりゃあただ事実を説明する文みたいなものだろう。
じゃあ具体例で考えてみるか。
- I will take a lunch at 12 O'clock.
- I'm going to take a lunch at 12 O'clock.
「will」を使うと主観的な意志、カンタンに言えば、「行こうかな~」って頭の中で思ってるってことだ。
対して、「be going to」となったら……そうだ、もう12時にランチを取る方向性で進んでるってことだ。きっとスケジュールとして予定を決めてるような状況だ。
少なくとも、現在進行形を使ってるんだからすでにその方向性で進んでるのは間違いない。
こう考えてみると、やっぱり丸暗記だけじゃ英語は分からないんだなあ。
~エア授業(推理)終わり~
……と、このように自分の言葉で噛み砕いて説明してみると、自分の頭の中でロジックが整理されるのです。
その上で解説などを読み返してみると、字面だけでなく内容も腑に落ちることでしょう。
ちなみに、こうした独り言をベースに整理して言葉遣いも整えていけば、そのまま解説文にもなります。

もっと粗い言葉遣いでも構いませんし、バリバリ大阪弁などでも良いですよ。大事なのは自身の理解をハッキリ形に表すことです。
まとめ
物事というのは、「なんとなく頭に入ったかな」レベルでは大抵は理解度が不十分です。
ましてや、単に他人の説明を読み流すだけならば誰にでも出来ます。
対して、実際に自分の言葉で説明しようと試みると、理解の怪しい部分はごまかしが効きません。理解があやふやであれば、説明もそのまま曖昧になります。(「この人の説明、全然自信なさげで手探りだな」という場面がまさにそれです)
だからこそ、一人エア授業で自分自身の理解度を確かめることが出来ます。
実際に説明する相手が居たほうがリアクションも引き出せるので良いのですが、エア授業は一人でできますから、説明に付き合わせる相手を探す必要もありません。
さらに大きなメリットとして、アウトプットする過程の中で逆に自分自身の理解を整理していくことも可能です。
ですので、講義形式でなく推理を進めていく形式でもオススメです。
形式は特にこだわる必要はありませんし、もっと軽いノリでも構いませんので、是非とも自分で言語化する習慣をつけてみましょう。
そうすると、一生涯にわたり役に立つメソッドになります。

私のように率先して人に教えるようなタイプは、実は本人も得をしているのです。
※インプット学習とアウトプット学習の違いをカンタンに解説
国語力アップに読書量は無関係?アウトプット訓練とインプットの違いを知る|論理的思考のコツ③
※学習の理解度はアウトカムで測ることが第一です。
理解度の確認方法はアウトカムが中心!「分かったつもり勉強」を改善する|勉強法・教育法⑨


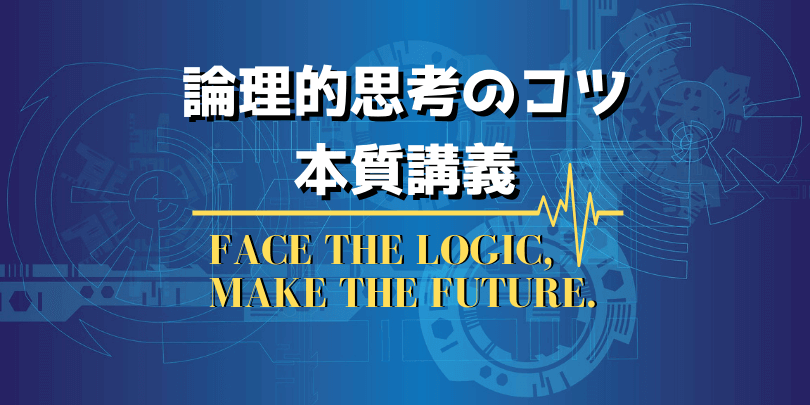

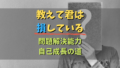


コメント