勉強について考える際に付いて回るテーマとして、「努力」の問題があります。
- 『才能が全てだから努力しても無駄だ。』
- 『彼には努力する才能がある。』
- 『努力は必ず報われる!』
- 『出来ないのは全て努力不足が原因だ!』
- 『四の五の言わずに努力しろ!』
人によってその主張も捉え方も様々です。また、話者自身の言葉の定義によっても話は違ってくることでしょう。

努力することは間違いなく大切なことだと思います。

どれだけ努力しても天才には敵わないじゃん。無駄無駄ァ!

どちらの言い分も正しいのですが、努力についての問題で本当に問うべきは「目標達成の為の手段」という観点です。
広く努力について考える場合も、前回記事で解説したアウトカム=結果・成績からの視点がカギになってきます。
『勉強は努力か才能か』ではなく、自分自身の現状が問題

まず、努力について考える前に、「勉強は努力か才能か」というよくある議論について考えてみます。
どれほど努力しても勝ち目のない大天才は現実に居る
まずはじめに、天才というのは現実に居ます。
実際、私から見て人間であることすら疑わしいレベルの大天才が居ました。
例えば、私の同級生だった万能の天才・N君です。
彼は、まるで勉強している気配がなく、実際に高校の3年間のほとんどは赤点スレスレで最下位付近を彷徨う程度の成績でした。(ただし、学力試験以外の能力はどれをとっても天才的でした。)
ところが、高3の12月辺りからようやく勉強を始めたかと思いきや、1~2ヶ月で赤点レベルからセンター試験の総合点9割を軽く超えるレベルになりました。
その勉強内容も、特別なことをしていたわけではなく、ただ手元にあった問題集をテキトーに回していただけでした。
私は努力家とは真逆のタイプで、高校までは随分と慢心し切っていたものですが、N君の天才性を見て完全に天狗の鼻が折れました。
そんな大天才のN君からしても、ジョン・フォン・ノイマンやオイラー、ダ・ヴィンチといった歴史的な超人たちが「更に上に」居るわけです。
そして、そうした稀代の大天才たちも凄まじい量の研究と学習を経てきているからこそ歴史的な業績を数々残しているということです。
確かに「大天才たちと同じ分野で1対1の学力勝負に勝つ」というのが目的であれば、どれだけ努力したところで無駄でしょう。
そもそも努力する目的は?勉強は自分自身の可能性を拡げる手段

勤勉な天才に凡人はどうやったら敵うっていうんだ……。

彼らと同じ土俵で勝ち負けを競うのであれば、どれだけ努力しても勝つのは無理でしょう。ただしこれは「彼らと競うならば」の話です。
では、そもそも勉強する目的とはなんでしょうか。
ジョン・フォン・ノイマンと学力で勝負することでしょうか。ダ・ヴィンチと万能性で勝負することでしょうか。
勉強する目的は、『自分自身の』人生選択や将来の可能性を拡げるためであるはずです。(無理に勉強させられているケースはまた別問題ですが)
世界大会でたった一人しか取れない金メダルを目指しているならさておき、勉強の分野であれば取りうる選択肢の間口は非常に広いです。
入試試験であれば、合格最低点さえ超えれば合格です。日本には大学や専門学校が無数にあります。各々の学校には学部・学科も数多ありますし、研究分野は星の数ほどあります。
職業で言えば、それこそ世の中には把握しきれないほどの選択肢があります。企業や官公庁に就職するというコースもそうした「膨大な選択肢のなかの一部」に過ぎず、今やネットを使って自宅に居ながら起業することすら可能です。

勉強における努力とは、選択肢を拡げるための手段です。
他人の才能よりも自分の今後の成長を考えて努力する
「努力しても無駄だ、天才には勝てない」と考えるのは個人の自由です。(憲法19条)
ですが、努力をしないことで選択肢が狭まるのはまさに自分自身の人生です。
自分自身が努力をしようとしまいと、他人は他人で関係なく各々努力を続けます。そして、才能のある人間もそのほとんどが大なり小なり努力しています。
ここで天秤にかけるべきは、「才能のある他人vs自分」よりも、「努力しない自分vs努力した後の自分」ではないでしょうか。
才能の差を嘆いたところで自分自身の現状は何も変わりません。
それならば、少しでも自己分析を進めて、少しでも自分自身が大きく成長できるよう努力した方が結果的に有益ではないでしょうか。
「実らない努力」が無駄どころか活かされる実例

では、私の個別指導の経験から実例をご紹介します。
当時、私が継続的に英語を指導していた高3生のS君がいました。
S君は日東駒専(日大・東洋・駒澤・専修)を目指していました。
しかし、彼は性格的には生真面目なのですが、私を含めた講師陣の見立てではどれだけフルに努力しても日東駒専は現実的ではないというのが正直なところでした。
そのため私は、日東駒専に拘らずもっと現実的に、基礎レベルから学習を積み上げて、結果的な成長具合から志望先を考え直すべきであると提案しました。
ですが、実際は日東駒専という目標から逆算した、荷が重すぎるレベルの問題集が用意されました。
そして見立て通り、S君はどれだけ真面目に努力しても理解の厳しい部分の方が多い状態でした。
そこで私は、問題集の中でもなるべく例題や基礎レベルの範囲を中心に進めていくことにしました。それも、解き直しサイクルや理解度ごとの評価分けなど、学習メソッドの習得により重点を置いて指導しました。
結果的には、日東駒専という目標については方針転換を余儀なくされました。
ですが、S君は一念発起して公務員専門学校から公務員を目指すことを自主的に決断しました。
公務員試験というのは出題科目の幅が広い代わりに、1問ごとの難易度はそれほどでもありません。
そうした方向性に合わせて問題集も元の基本レベルのものに戻したのですが、S君はハイレベルな問題集で苦労した分、基本レベルであれば自学自習で着実に成長できるようになっていました。
ハードモードの問題集で学習メソッドそれ自体を努力して習得した結果、基本レベルでは勉強の進め方が非常に上手く行くようになっていました。
また、高難度の問題集で苦労した経験からか、基本問題集ではモチベーションも自信も見違えるほど向上していきました。
基本的な学習の進め方が身についていれば、あとは各科目の努力の積み重ねの問題になります。
S君にとっては、日東駒専という目標からすると実らない努力だったと言えますが、努力して身に付けた合理的な学習メソッドや試行錯誤する意識は次の道にフルに活かされることになるでしょう。

「努力したが第一目標に届かなかった」からといってそれが「無駄な努力だった」とは限らない、と言うことです。
『努力は必ず報われる』の真意、量も質も大切
『努力は必ず報われる』という常套句があります。
ですが、『努力』と一口に言っても、人によって意味合いは違ってくるものです。
この常套句を「私なりに」解釈すると、実際は学習効果や効率性が大きく関わってくるという点が省略されているように思われます。
例えば英単語帳だけを毎日5時間読み続けたところで、英語の長文読解問題ができるようになるかは分かりません。それはインプット止まりの学習であり、アウトプット学習が抜け落ちているからです。
単語帳のインプット学習であればまだ基礎力の向上には大なり小なり繋がります。
ですが、以前の解説で紹介した例のように、「まとめノートを綺麗に書く」ことばかりに時間と労力を延々と割いたところで、肝心の中身が頭に入っていなければ無駄な努力と言わざるを得ません。(レイアウトのセンスを磨く効果はあるかも知れませんが)
イメージの湧かない方は、「もしも同じ時間と労力を使って復習・問題演習・見直し・解き直しのサイクルを進めていたら」と比較して考えてみて下さい。
一方、当サイトでシリーズとして解説した論理的思考力それ自体のトレーニング、あるいは問題演習を通じた解き直しのサイクルなどの合理的なメソッドを組み込むことで、同じ5時間の努力でも学習効果に大きな違いが生まれることでしょう。
先ほどの単語帳の暗記知識も、読解問題での実践を通じて「使える知識」になっていきます。
ここで考えるべきことは、学習効果10の努力をすれば学習効果10だけ報われるということです。
一方で、学習効果50の努力ができれば学習効果50の分だけ報われるとも言えます。
ここで、学習効果10しか出ない努力をしたところで学習効果50の報いが来ることは期待できないでしょう。
これに対して、『学習効果10の努力を5倍に増やして学習効果50を得る』というのはまさしく非効率的と言わざるを得ません。
そういう意味で、「努力は質と量に応じた分だけ必ず報われる」と言えます。

くれぐれも単純な努力量、努力時間だけで勉強を測らないようにしましょう。大雑把に言うと、「質×量=効果」です。

じゃあやっぱり最低限の努力で良いじゃん。よし遊ぼう。

あなたの場合は勉強の量も質もどっちも足りてないよね。
こうした点は、努力それ自体を美徳と感じる人にとっては特に要注意のポイントです。
同じ努力量でも、努力の仕方によっては効果が1にも10にも50にも変わるということです。
時間も努力量も限界がある、だからこそ学習効率
勉強の目的を「学力・成績の向上」と捉えるならば、努力はその手段です。
一方で、努力量・学習時間は有限です。
例えば、超一流の忍耐力をもったアスリートですら努力量には限界があります。
いかなる努力家でも、努力が過ぎればオーバートレーニング症候群を誘発します。

オーバートレーニング症候群が意味するのは、繰り返しになりますが努力量にも限度があるということです。
これは根性が足りないどころか、根性がありすぎたがゆえにオーバートレーニングを招いたとも言えます。程々のトレーニングでギブアップするような人であれば恐らくこうはならないことでしょう。
だからこそ現代のトップアスリートはスポーツ科学なども取り入れて、フィジカル・メンタル共に合理的なトレーニングを追求していると言えます。
勉強で考えても、持続的な集中力や体力には限度があります。
猛勉強が原因で心身に異常をきたすことも起こりえます。そうした諸症状から、心療内科やカウンセリングを受診せざるを得ない受験生も実際に居ます。
そうした量的な限界を超えるためのコツが学習効率です。
たとえ同じ努力量でも、より効率的なノウハウで取り組めばさらなる学習効果が期待できます。
集中力の持続時間や疲労回復を考えると、人によってはむしろ勉強時間を減らしてリラックスタイムを増やした方が学習効果が高まるケースすらあることでしょう。
だからこそ大手予備校などの情報やノウハウの蓄積に商品価値があるとも言えます。
教育のプロに指導を受けるということは、「お金で学習の効果・効率を高める」ということです。これがいわゆる教育格差と呼ばれるものの核心部分です。
これは単純に『努力が足りない』の一言では片付かない話です。

もちろんただ塾に通っているだけで話を聞き流していては意味がありません。逆に、独学でも自分で自己改善して学習効果を上げる努力が出来る人は、自力で高い成果を上げることも可能です。
まとめ
努力そのものを尊ぶのは個人の価値意識の問題ですので人それぞれです。
どのような学習法であれ、『努力をする前の自分よりは』確実に成長できることでしょう。
ですが、目標達成のための手段という観点からすると、同じ努力量でも効率的に進めたほうが有利であるということもまた事実です。
加えて、物事を効率化する能力それ自体が将来の仕事・ビジネスにも直結していきます。それこそが近年よく聞かれるようになったソリューションの意義でもあります。
勉強も同じです。
- 努力が明らかに不足している人は、まずは努力量を増やすことを検討しましょう。
- もともと努力家の場合は、努力のし過ぎが逆に集中力の低下や慢性的な疲労の蓄積を招いていないか、心身に変調をきたしていないか確認しましょう。
- 努力量が多い人も少ない人も、学習効率の向上などの「努力の質」も追求しましょう。
- 才能による差は、出来る限りの努力を経た上で結果的に生じるものです。
勉強は手段であって目的は学力・成績の向上なのですから、手段を質・量ともに向上させることこそが重要なカギです。
量と質のどちらか一方の問題ではなく、「勉強の質×勉強量=学習効果」になります。
より良い学習ができれば、たとえ当初の第一目標には届かなかったとしても、努力の過程で本当に成長できていれば次の目標にも活かされます。
これはつまり、努力によって自分自身の可能性が広がったことと同義です。
才能による限界は否めませんが、努力をすることで「以前の自分よりも」可能性を拡げられることもまた事実であり、大切なのはその努力が自分自身にとって実際にどのような成長・結果に繋がるかという観点です。

そして、効率的な学習メソッドについて論じてきたのが当シリーズ『効率的な勉強法・教育法のオススメ』です。
※あわせて読みたい関連記事
勉強の目的は成長への自己投資!経営ビジネス的な観点から学習を捉え直す|勉強法・教育法㉒
理解度の確認方法はアウトカムが中心!「分かったつもり勉強」を改善する|勉強法・教育法⑨
綺麗なまとめノート作りの罠!勉強にノートはいらない、手段の目的化は時間と労力の無駄|勉強法・教育法⑥



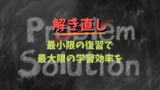



コメント