当記事では、以下のような方を対象に、読書感想文のテクニックについて解説します。
- 読書感想文に時間を割かれたくない、評価もさほど気にしない。
- 課題図書を読みたくないが、代行業者にはお金を払いたくない。
- 真面目に取り組むつもりだが、読書がとにかく苦手で先にヒントがほしい。
- 課題本は全て読むが、読書感想文の精度を更に高めたい。
活字を読むことそれ自体が苦手な方であれば、読書するに越したことはありません。課題図書が特に指定されていなければ、各々が興味の湧いた本を読んで好きに書けば良いです。それが経験値アップの第一歩になります。(→参考記事)
一方で、学校側から課題図書が指定される場合も多いことでしょう。(特定の1冊であれ選ぶ範囲を限定される場合であれ)
ですが、私が思うに、興味のない本を嫌々読んで莫大な時間を費やすのは非効率的です。
※活字の苦手な方、読書嫌いの方こそ、自分の興味が沸く書籍から手を伸ばしていくべきです。そうして興味の幅が広がっていくにつれて、必要に応じて自発的に読書するようになるのが本来の流れであるはずです。
よって、当記事では、基本的に「課題図書を読まない」前提で読書感想文の時短術をご紹介します。
当記事の手法を一言で表すとするならば、「あらすじサイト調査感想文」です。

過去記事でも述べたように、私自身が課題図書を読まずに読書感想文を書いていました。その時の経験則に基づいて解説します。
注意:読書感想文や作文のパクリは盗用・剽窃につき厳禁
まず、本題に入る前に、必ず守っていただきたい最低限のルールがあります。
それは、ネット上の文章を丸コピペしないということです。
他人の書いた文章を自分の作文として提出するのは、盗用・剽窃にあたるため厳禁です。これは、一部の言葉尻だけ改変しても同じ話です。
大学であれば、盗用・剽窃は退学処分が下されてもおかしくないレベルの不正行為です。
ちなみに、作文の例を公開している管理者自身が「条件の範囲内で著作権フリー」と明記している場合、その利用条件さえ満たしていれば丸写ししても構いません。
この「利用条件さえ満たしていれば」というのがカギで、必ず事前に読み込む必要があります。
例えば、普通は「コンクールに出品する用途では認めない」というような条件が課せられていることでしょう。
読書感想文は、学校経由でコンクールに出品される場合もあります。コンクールに出品するということは、それを自分の作品として世に発表するのと同様の行為であり、「パクリがバレて先生に怒られる」という次元では済まない問題となりかねません。
著作物については、「同級生の数学の宿題を写す行為とは根本的に異なる」ということを肝に銘じる必要があります。
また、ネット上に公開されている情報の丸コピペは基本的にバレると思っておいたほうが良いです。いずれにしましても、丸写しは全面的に非推奨です。

こうしたルールを守れる方だけ、記事の続きに進んで下さい。
読書感想文は課題図書を読まなくても書ける!?
未視聴のアニメ・マンガでも大体のあらすじは分かる
まずは話の前提として、自分で鑑賞せずに作品の内容を理解することは可能です。
例えば、「自分が鑑賞したことのないマンガやアニメ」でも、ネタバレサイトや感想・考察サイトを読んで大体のストーリーや話の山場が分かるという経験はあるかもしれません。映画やゲームでも同じです。

あるある。ワンピとかむしろネタバレ回避したいのにネットで勝手に情報が入ってきてしまう。
確かにネットであらすじや考察だけを読んで済ませるというのは、『作品それ自体を味わう』という要素は抜け落ちています。
ですが一方で、実際にその本を読んでなくとも「情報としての」あらすじは大体把握できるというのもまた事実ということです。

むしろ考察サイトの方がよほど細かく作品を読み込んで解説していることも多いでしょう。
課題図書も同じ、及第点レベルで良ければ読まなくても書ける
書籍はマンガやアニメよりも文字の情報量は多いですが、それでもネットでググってストーリーラインを大体理解することは可能です。
もちろん作品の枝葉末節の部分は大半がカットされることになりますが、作品内容のコアな部分はネット上の誰かがまとめています。(マイナー過ぎる作品ですら紹介されている場合も)
むしろ枝葉末節をカットしてもらった方が読書感想文としてまとめやすくなります。

むしろ読書好きの方がまとめた書評の方がよっぽど上手く情報整理されていたりするものです。
当記事では、その具体的なテクニックについて解説していきます。
読書感想文の時短裏ワザ・クオリティ向上テクニック
ネタバレサイトのあらすじをどれだけ拾えるか、検索ワード候補
読書感想文の時短を目指すためには、まず何よりもネット検索で情報収集することが先決です。
その際の、検索ワードの候補を列挙してみます。
- 「○○ ネタバレ」
- 「○○ あらすじ」
- 「○○ 要約」
- 「○○ 感想」
- 「○○ 考察」
まずは、1・2・3で可能な限り複数のネタバレ・あらすじ情報をキープします。(私であれば10サイト以上は流し読みします)
そして、それらにザッと目を通して、その中から更に良さげなサイトを絞っておきます。だいたい5サイト程度もあれば十分かと思われますが、荷が重ければ3サイト程度でも構いません。

そっか!マンガの話と同じで、あらすじサイトが内容を代わりにまとめてくれてるってことか!

その通りです。ネタバレをする以上は、作品の根幹になる部分を優先して紹介しますからね。
なお、検索ワード4・5の「感想」「考察」というのは、読書感想文のネタを膨らませるヒントになることが多いです。(あくまでも参考であり、丸パクリは厳禁)
複数サイトを比較して正確性を上げる、レビュアーの偏見や誤読を排除
次は、こうしてピックアップした「複数の」サイトを精読して比較していきます。
複数のサイトを比較する理由は、誤った情報やレビュアーの個人的な偏見を極力排除するためです。
読書感想文の仕込み段階でまず大切なのは、本の内容・あらすじの「客観的な情報」です。そのためには、可能な限り正確な情報が必要となります。

情報の正確性を高めるための比較です。だからこそ、1~2サイトだけ読んで信用するのはオススメしません。
サイト主の主観的な感想よりも客観的な本の内容をチェックする
では、「客観的な情報」と「主観的な感想」というのは、具体的にどのようなことでしょうか。
例えば、以下のようなレビューがあったとしましょう。
この文はいずれも明らかに個人的な感想です。動作の主体が「私」=レビュアーとなっているからです。(後者の文は「(私は)思いました」と真の動作の主体が省略されている)
では、次の文をご覧ください。
上の文で言えば、前半部の「メロスは作中でA→B→Cと心境の変化を経て覚醒した」の部分です。これは、本文中の登場人物の心理描写になります。国語的に言えば、本文に書いてあることです。
一方、後半部の「人間の素晴らしさを感じた」というのは、このあらすじを書いたレビュアーの感想です。
これはまさに、過去記事で解説した文章読解のコツと同じ話です。
確かに、読書感想文の場合であれば、主観的な感想も「参考には」なります。(もちろん自分の言葉でリライトするのが前提)
ですが、まずは「レビュアーの感想」と「客観的な内容の説明」を切り分けて考えることが大切です。
なぜなら、ここでは課題図書を読まずして本の内容を知ることが目的だからです。

まずは本の中身だけをドライに書いたネタバレあらすじを読み、内容を大体把握してから考察や感想を参考に読むのがオススメです。
複数サイトに共通するトピックこそがメインテーマ、読書感想文の軸
こうして複数のサイトを比較しつつ読んでみると、レビュアーが違っても共通するトピックというものが浮かび上がってくるはずです。
『走れメロス』であれば、「人を信じること」、そしてクライマックスである「諦念と絶望から覚醒して走り出す」部分に当たるでしょう。
そうして複数のサイトが共通して力点を置いている部分こそがメインテーマです。
複数のレビュアーが同じように誤読をするというのはまず考えられませんので、そうした箇所はメインテーマとして決め打ちしても構いません。(仮に誤読だったとしても「ありがちな誤読」になるので不自然ではない)
このような共通項をピックアップするだけで、読書感想文の主軸がほぼ出来上がります。

スイカの真ん中だけスプーンで食べるみたいな読み方ですね。

長文読解でも一番大事なのはスイカの真ん中=本文の主旨です。
まずはメインテーマを軸として要約を大体まとめます。まとめると言っても、あらすじサイトの情報を整理するだけです。
そして、その主旨の部分に対して個人的に思いついた考えや感想をメモしておいて、『自分の言葉』として感想文に落とし込むことになります。
ここで書くメモは、単語の羅列レベルでも構いません。思いつきでも良いですので、とにかく自分の言葉を捻り出すことです。
こうすることによって、物語の核心にあたる部分を狙い撃ちして『自分の言葉で』書けます。
理解の自信が無ければ課題図書を高速で読み流す
課題図書を既に購入している場合は、参考資料として役に立ちます。
特に、先ほどのメインテーマ絡みの部分を理解できている自信が無ければ、あらすじ上で重要な場面を狙って高速で読み流します。そして、重要なシーンに入るたびに少し真面目に読みます。
すると、あらすじで簡潔に書かれていた部分がより具体的に理解できることでしょう。
なお、課題図書が手元に無い場合でも、激安の古本が売ってあれば買うのも一手です。気分が乗れば普通に読んでしまうのも一つです。
課題図書を一通り読むならば、あらすじ→本編→ネタバレの順番
ここまで、「課題図書を読まない」という前提で解説してきました。
ですが、以上の方法は課題図書を一通り読んで真面目に読書感想文を書く方にとっても役立ちます。
まずは前述のようにあらすじサイトを読んでいきます。
ネタバレを気にしないならば、最初からネタバレ有りのサイトを読んでしまっても構いません。逆にネタバレを気にする方は、「○○ ネタバレ無し」でググると良いです。
そうして、文章のマクロな全体像を把握した上で読み進めていきます。これは、文章理解という点では圧倒的に有利な読み方です。
(ちなみに、マクロな全体像を自力で把握することがパラグラフリーディングの核心です)
そして、読み終えた後に再度ネタバレサイトを読み返していきます。そうすることで、内容理解の正確性を高めることが出来ます。
読書感想文のライティング段階での書き方のコツ
読書感想文の「定番の文章構成」をアウトラインでご紹介
大体の情報が整理できれば、いきなり清書に入る前にアウトラインを書いてみましょう。
アウトラインというのはつまり、ザックリとした文章構成と捉えて頂いて構いません。

以下、だいたいの作品に当てはまるようなオーソドックスな展開をご紹介します。
1 要約(メインテーマを中心にザックリと)
2 気になったポイント(なるべくクライマックス部分に絞る)
(1)クライマックス前後での主要人物の心情変化・行動、事件など(本文の内容)
(2)主要人物の行動や心情変化に対して、個人的にどう思ったか(個人の感想、考え)
(3)作品外のリアル社会や自分の身の回りで何か連想することを考察(個人的な話も可)
3 自分の感想・結論まとめ(学んだこと、強く感じたこと、気付き)
記事の前半部で述べていた情報の正確性や客観性というのは、2(1)までの話です。
逆に2(2)以降は、「心にも思っていない綺麗事」であろうと、「架空の体験談」であろうと、課題の要件さえ満たせるならば何を書いても良いです。(公序良俗に反しなければ)
評価を気にしないならば、尚のこと字数さえ埋めれば終了です。
この辺りの核心部分が具体的に落とし込めれば、後の清書は手グセで書き進めていけば良いです。
評価を特に気にしないならば、要約でなるべく字数を稼ぐ方針でも結構です。半分強が要約でも、間違ったことを書いていなければ非難されるいわれはありません。
なお、真面目に読書感想文を書く場合でも、小論文と同じで本文の情報を要約整理してから「自分の考え」を述べるのが王道です。それにより、「何に対しての感想か」が明白になるからです。
パソコンやタブレットで清書する、無ければスマホでも
清書の際には、ワードなどの文書作成ソフトを使うことをオススメします。
なぜならば、字数の調整、誤字脱字の訂正、文の挿入などが手書きよりも圧倒的に容易だからです。ワードなどが無ければ、Windows標準装備のメモ帳でも構いません。(ただし改行位置は手動)
そうしてデジタル原稿が完成すれば、あとは手書きで写すだけです。
なお、「PCやタブレットは無いけどスマホユーザーです」という方であれば、スマホで原稿を書くのも一つの方法です。
私自身が昔からデスクトップPCユーザーであるため、スマホでの文章作成は非常に不便のように感じられるのですが、フリック操作などに慣れているのであれば構いません。
ネット上の文章を丸写しせず、自分の言葉にリライト=書き換えていく
最後に改めて念を押しますが、ネット上にある文章を丸写ししてはいけません。
そこで必要になってくるのが、自分の言葉にリライト=書き換えていくことです。
特に、一般的な動詞や形容詞は自分の言葉でドンドン置き換えていきましょう。その方が、コピペ感も抜けていき自然な文章に近づきます。
例えば、普段から文章の苦手な方が以下のような文を写してしまうと、語彙力や知識のギャップから一気に「怪しい感想文」になってしまいます。
(※以上は、メロスのマイナスの側面を排除した綺麗事です。読書感想文であれば逆にマイナスの部分をピックアップするのも一つです。)

よし、この文章をそのままコピペしちゃえ!

……文体が違いすぎて一発でバレるわよ。

友人知人やネット上の文章を写してしまうと、一気に「他人の文体」になってしまいます。
では、試しに先ほどの文の言葉や言い回しをリライトしてみます。
これだけでも印象が違ってくるかと思います。むしろ、もっと崩した文章を書いても構いません。
逆に、本文に出てくる固有の表現はそのまま書き写すべきです。例えば本文中の固有名詞まで書き換えてしまっては、一気に「ウソの感想文」になってしまいます。
まとめ・マクロ視点や情報リテラシーの訓練として
以上の内容をカンタンに復習すると、以下の通りです。
- ネタバレサイト・あらすじサイトを複数ピックアップする。
- 複数のサイトを比較して、情報の正確性や客観性を高める。
- 「サイト主の主観的な感想」と「本文の客観的な説明」とを切り分ける。
- 各サイトの共通項を見つけ出し、メインテーマとして読書感想文の主軸に据える。
- 課題図書が手元にあるならば、高速で流し読みするのも一手。
- 先にアウトラインでザックリとした文章構成を書く。
- パソコン・タブレット・スマホで原稿を一通り書いてから手書きで清書する。
- 必ず自分の言葉にリライトしていき、自分に合った自然な文章を心掛ける。
※提出期限ギリギリの方は、以上の工程を大雑把なやっつけ仕事でやって字数を埋めるということです。正確性は犠牲になりますが、提出しないで0点になるよりは遥かにマシです。
なお、このような手法は丸写しや宿題代行とは異なり、れっきとした国語の訓練にもなります。具体的に言えば、マクロ視点から文章全体を理解する能力の訓練になります。
加えて、「情報を比較検討して利用する」という点では情報リテラシーの向上にも結びつきます。
もちろん真面目に読めばインプット訓練になりますが、ここで私が話したノウハウは、情報リテラシーを上手く使うことによって作業効率を大幅に向上させることの実例です。
当記事の手法は読書感想文の時短だけでなく、結果的に正攻法で書く場合でも使える技術です。

課題図書が全く気の進まない本であれば、読書感想文は要領良く済ませて他に興味関心のある分野に時間と労力を割きましょう。
NEXT →
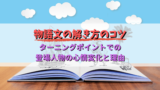
※読書による学習効果はインプットとアウトプットから考える
国語力アップに読書量は無関係?アウトプット訓練とインプットの違いを知る|論理的思考のコツ③
※読書感想文の時短術と同じく、勉強は「合理化」が大切です
勉強の目的は成長への自己投資!経営ビジネス的な観点から学習を捉え直す|勉強法・教育法㉒


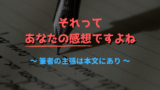



コメント