世の中には、様々な学習教材がありますし、効率化の方法もあります。
あるいは、教材や学習サイトの中に何かハッと気付くような重大なコツが書かれていたりすることもあるでしょう。
しかし、そうした学習法や情報はただの道具であり手段に過ぎません。
それらは「実践」してはじめて役に立つ知識です。
勉強のやり方が上手く行かない方は、「とにかく何か上手い方法が無いか」と探し求めることと思います。
しかし、そうした「聖杯探し」で更に迷うことになる前に、深く胸に刻み込むべき言葉があります。
いつやるか?今でしょ! ――林修

流行語大賞にも選ばれて、一時期は凄かったですね。

えー、それってもうとっくに流行終わってるコンテンツでしょ?

そのように流行り廃りで捉えるべき言葉ではありません。
「今すぐ行動」習慣が10年後の自分をも変えることになるのです。
このページ → 「『今すぐやる』必要性は?」という方向けのアドバイス
2ページ目 → ToDoリストの具体的な使い方の例
本論の前に:ADHD(注意欠陥多動性障害)の先延ばし癖
当記事は、「先延ばし癖で迷っている方、悩んでいる方に対してロジックと具体的手法で力強く後押しする」という観点から解説しています。
ですので、単純にこれまで解決の糸口が掴めていなかった方、あるいは意志力が足りなくて背中を押して欲しい方にはお役に立てるかも知れません。
ただし、ADHD(注意欠陥・多動性障害)に該当する方の場合は話が変わります。
ADHDとは、不注意・多動性・衝動性が「日常生活に困難を生じるレベルで」高い状態のことを意味します。そうした場合は、一般的な先延ばし癖とは話が違ってきます。
もし心当たりのある方は、注意が逸れる前に今すぐ家族の人にADHDの話を教えて下さい。あるいは今写っているこの画面をそのまま見せて下さい。
一般的に、ADHD(注意欠陥・多動性障害)に該当する場合は然るべき専門家の協力を仰ぐのが最善の道です。
元塾講師である私の経験上、個別指導塾でも特別なノウハウや知識の積み上げが無いと適切な指導を行なうのは極めて難しいです。なぜなら、講師一人ひとりの裁量に委ねられてしまうからです。
お客様側からすれば確率の低い講師ガチャを引くようなものですし、そもそも特別なノウハウを持った講師がその塾に一人もいないかも知れません。
ですので、まずはネットで情報収集をし、然るべき専門機関で支援を受けるのが最良です。あるいは、都市圏の方であればADHDに特化した教育機関などもあるかも知れません。
また、幸いとして、近年はネットの発達により特別なノウハウに基づいて設計された学習がオンラインでどの地域の方でも受けられるようになりつつあります。

このように、選択肢は徐々に増えつつありますので、あとはそうした選択肢を知ることが大切です。
※なお、アイハーブのトゥルーフォーカスでADHDが緩和されたというレビューも多々見掛けますが、効果には個人差があり、あくまでも専門家のアドバイスを受けられるのが理想です。
「今すぐ実践」で今から成長できる

それでは、さっそく本論に入っていきましょう。
この記事を今読んでいるのも「今この時」の実践です。
「人間は忘れる生き物である」という認識を具体例で掘り下げる
勉強について考えるにあたり、まず「人間は忘れる生き物である」ということを強く再認識することが大切です。
そもそも記憶を忘れないのであれば、知識問題は誰でも100点を取れて当たり前のはずです。
しかし、現実は全く違います。
学んだ知識、あるいは以前解けた問題が解けなくなるというのは、まさしく「忘れた」ということにほかなりません。
記憶に関して、一つカンタンなテストをしてみましょう。
では、頭の中でこの通い慣れた道をたどってみて、そのルートに何があるかを一つ一つ挙げてみてください。目立つランドマークだけではなく、建物の並びから信号の位置、街路樹一本一本に至るまで全てを思い出してみてください。
単純な位置関係だけでなくディティールまで思い出してみてください。建物や街灯の装飾はどうなっていましたか?街路樹はどのような枝ぶりでしたか?道路標識は?看板は?店の名前は?

そんなの覚えてるわけがない。

今、「知らない」ではなく「覚えてない」と言いましたよね?

覚えてないですし、思い出せません。

要するに、「知っているはずなのに覚えていない」ということです。常時歩きスマホでもしてない限りは、確実にあれもこれも見たことがあるはずですよね。それにもかかわらず思い出せないということです。

ちょっとタイム!確かに通学路とか毎日見てるけど、そんなのいちいち覚えようなんて意識はしてないし……。

では、3日間の猶予をあげますので、意識して覚えてみてください。
その上で3日後にまたテストしましょう。

……無理です。すみませんでした。
意識していないことは毎日見慣れたものでも思い出すのが困難です。
意識して覚えようとしても人は簡単に忘れます。
これこそが勉強を考えるに当たってのスタートラインです。

前回記事で解き直しのサイクルをオススメしたのはこれが理由です。
大事なコツを掴んだら今すぐ実践!重要な情報は今すぐ保存!
ブログでも何でも良いですので、あなたがなにか重要な情報を今知ったとします。
例えば前回記事の「解き直し」が勉強の重要なコツだと感じたとします。(実際のところ、仕事上の成長や業務改善においても大切な姿勢です。)

忘れないうちに今すぐ試してみようかな。昨日の問題集は、っと。あと机に付箋を貼ってメモしておいて……ブックマークしといて……。

おお、解き直しだけしときゃ良いのか!……まあいいや、後でやろう。そんなことよりマイクラの続きやろっと。
……あれ?なんか大事なことを忘れてるような……まあいいか。
もしもこの2人のスペックが同じだった場合、果たして今後どちらの成績が伸びるでしょうか。
どちらがより効率的で楽に成績を伸ばすことが出来るでしょうか。
今すぐ試しに10分から20分やってみて少しでもコツを掴むのと、後回しにして結局記憶が薄れた状態から復習するのとではどちらがより能率的に勉強を進められるでしょうか。

これはただの一例にすぎません。実際はあらゆる科目、あらゆる学習分野、あらゆる作業、あらゆる練習で差が付きます。
10分でも暇があるのであればその時にすぐ実践してみれば良いですし、どうしても暇が無ければブックマーク内に「重要」フォルダを作って記事を追加しておいて後で読めば良いのです。本であれば重要箇所に付箋を貼っておくなどの方法もあります。
「明日からやろう」は厳禁!スケジュールやToDoリストを使う

いやいや、明日から本気出す!でも今日は安息日だから。

まあ、それはそれで良いのではないでしょうか。
……本当に明日やるのであれば。

彼が勉強してるとこなんて見たことないですけどね。
このような事態に陥る人が後を絶たない理由は、明日になっても「明日やる」になるからです。
「明日からやろう」の無限ループでは永遠にその「明日」はやってきません。

でも、先生も結構先延ばしにしてるような気が。

私の場合は「明日やる」ではなくスケジュールを決めます。
「明日から頑張る」の繰り返しでは永遠に実行段階には辿り着けません。
ですが、例えば今日が2019年1月28日だったとして、「2019年1月29日17時30分にこの問題をやる」と決めればいかがでしょうか。
この1月28日からすれば同じ明日ですが、先ほどの「明日やる」とは決定的に違います。
その違いとは、今その時点で具体的に日時を指定しているという点です。
本当に何か用事があって「今すぐやる」が実行できないとしても、エンドレス後回しにならないような対策を今すぐ講じておけば良いのです。

勉強する!するが……今回、まだその時と場所の指定まではしていない……つまり……俺がその気になれば勉強するのは10年20年後ということも可能だろう……ということ……!

ということにならないようにスケジュールに落とし込みましょう!
もちろんToDoリストなどにピックアップする形でも良いです。
もちろん時間的余裕があるならば常にすべてを「今すぐやる」のが一番の理想です。
ですが、常に暇があるとは限りませんので、「どうしても他にやることがある」時の対応策としてToDoリストやスケジュール帳に具体的かつ速やかに書き込んでリマインダーとする、ということです。
リマインダーとは、つまり「記憶を思い出させてくれるもの」全般のことを指します。まさに「人間は忘れる生き物である」という発想から生み出された考えです。
もちろんリマインダーの存在自体を忘れないように習慣的に確認して実行しましょう。
四六時中スマホを触れる環境にあればスマホアプリなどを活用しても良いですし、使えなければ持ち運びのしやすい小型メモ帳のようなものを用意するのが良いです。
既にスケジュール帳を常用している場合でも、活用できていないページがあるならばそこを利用する形も良いです。カレンダーの部分を自分なりに上手く活用するのも一つの方法です。

大事なのは、普段から活用できるかということです。
方法を改善して効率化していくのは習慣化できた「後」の話です。
「今すぐやる」習慣が自分の数十年分の将来を変える
では、「今すぐやる」、「今日やる」習慣を身につけると、何が変わるでしょうか?
冒頭の記憶の話を踏まえると、記憶のフレッシュな状態でコツを掴みやすくなるということです。
物事のコツを掴むことはどのような分野においても極めて重要なことです。
時によっては「覚醒」とも呼べるような変化につながることもあるかも知れません。スポーツではよく聞く話かと思いますが、それは知的領域でも同じです。

実際に個別指導する側として、生徒さんに合ったアプローチを模索しているうちにコツを掴んで急激に成長速度が加速した例は数多あります。

……つまり先生がスゴいということですか?

いえいえ、いかにコツを掴んで頂くかが個別指導塾のそもそもの目的の一つですから、あくまでも職務です。私にも分からない何かが生徒さんのツボにハマって劇的に変わることも多々あります。
コツをつかめるチャンスやタイミングは、いつどこで出会えるか分かりません。だからこそ普段から実行力を高めてチャンスを逃さないことが大事です。
いわば、「勉強のコツを獲得する為のコツ」こそが「今すぐやる」習慣とも言えます。
そして、「今やる習慣」はこのような瞬間的な違いだけでなく、数十年スパンで違いを生み出します。
例えばAさんは「明日から本気出す」と言い続けて結局1ヶ月が経ったとします。
一方で、Bさんは慣れないながらも「今すぐやる」習慣を1ヶ月続けたとします。
これだけでもAさんとBさんの間では30日分の成長の差が生まれます。
これが1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年……と続くとすれば、果たしてどれだけの違いが生まれるでしょうか。
つまり、成長速度も将来の可能性も全く変わるということです。
中途半端にだらだらと続けず、オンとオフを切り替えて効率的に

でも、「すぐやる!すぐやる!」ではずっと働き詰めで疲れ果てちゃいそうですね。

安心して下さい、そうではありませんよ。
実際のところ、私自身ゆっくりしてる時間の方が長いでしょう?

あっ、そう言われればそうですね。
でも先生は何かやる時になったら急にせかせか行動しますね。

大切なのはオンとオフのスイッチです。つまり「やる時には今すぐ集中的にやる、やらない時には中途半端にやらない」ということです。

そうそう!遊びも全力でやるのが一番!

あなたこそだらだら遊び続けてやるべきことをやってないような……。

そこに気付くとは……やはり天才か。

見れば誰でも分かります。
これらの点は、前回記事で触れた学習効率にも直結する話です。
つまり、勉強時間ばかりを無理に増やしたところで、学習効率が低下の一途をたどっては本末転倒ということです。
だからこそ、効率性も一緒に高めるためには、「勉強する時にはする」「遊ぶ時には遊ぶ」というメリハリが大切になってきます。
そして、こうしたメリハリをつけるために必要な第一歩こそが「今すぐ行動する」という習慣であり、具体的に何をするべきかを明確にするのがToDoリストです。
「今やろうと思ってたのに」:本当に今勉強する準備行動をしていたか

そろそろ宿題したら?

今やろうと思ってたのに!やる気なくなったから寝るわ。
教育熱心な親御さんと反抗期のお子さんとの間では特に多いケースかと思われます。
私個人は「本人が勉強する気ならすればいいし、したくないならしなければいい」というドライな考え方ですし、実際問題として勉強するよう命じるのはモチベーション面で逆効果になるケースの方が圧倒的に多いように見受けられます。
ですが、ここではそのような親子間の問題は除外して、頭では勉強しようと思っていても「今やろうと思ってたのに」とついつい言い訳してしまうケースについて本人側の視点で考えてみましょう。
ここで一つ自問すべきは「本当に今から勉強する準備をしていたのか、予定を立てていたのか」という点です。
そのような準備に取り掛かる前段階だった場合でも、具体的にいつどこでどの教材をどのような方法で勉強する予定を組んでいましたか?また、その時間になったら実際に行動に移していましたか?
本当に「今すぐ勉強するつもり」だったのであれば、これらの問いには明確に答えられるはずですし、そもそも実際に行動に移しているはずです。
予定を組んでいたのであれば、その時点でも「○時△分頃からこれこれこのように勉強する予定です」と具体的に言えるはずです。
逆に、これらの問いにハッキリと答えられず、実際に何の準備行動も取っていなかったのであれば、現実的には「今から勉強する気は無かった」のと同じ状態ということになります。

ここで、「だから勉強しなさい」と主張するつもりは全くありません。
頭で考えるだけでは行動にならないというシンプルなロジックです。

次ページでは、ToDoリストの具体例について解説していきます。



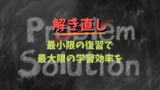


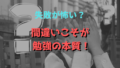

コメント