
『勉強にメリハリをつけましょう』って言われても、じゃあどうすれば良いのかってのがわからん。

それが分かってたら最初から苦労しないよね。
……というお困りの声は古今東西変わらない部分です。
現代において特にメリハリの阻害要因となるのは、スマホやPCをはじめとしたインターネット依存症です。
依存症まで行かずとも、勉強中に大なり小なりネットが気になってしまう方も多いことでしょう。
当記事では、勉強の集中力を阻害する代表例であるスマホについての対応策を足掛かりに、勉強のメリハリのつけかたについて広く考えていきます。
まずはカンタンに続けられるところからコツを掴みましょう!

ポイントは、意図的にスイッチのオンオフを切り替えることです。
ありがち失敗例:勉強中にスマホが、スマホ中に勉強不足が気になる

まず最初に、もっともメリハリの利いていないNG例を紹介します。
もっとも望ましくない例を一行で表すと、以下のとおりです。
具体的に言うと、SNSであれば相手の既読や返信、ネット上の反応などが気になることでしょう。
ソシャゲーの無課金・微課金勢であれば体力や行動ポイントの回復時間が気になることでしょう。一定以上のガチ勢であれば、ランキングやイベント報酬が気になるといったところでしょうか。
このような状態になると、まず勉強の集中力が削がれて学習効果が下がることになります。
一方で、気分転換も中途半端になり、勉強から離れてストレス解消になるはずの遊びが逆に不安の種となり……。
これこそが最も非効率的な負のスパイラルです。
具体的な数字で例えるならば、本来は『勉強100+気分転換100』になるはずが『勉強50+気分転換50』になってしまう、といった具合です。
ネット依存の度合いによっては『勉強30+気分転換30』……と更に効果は下がっていくことになるでしょう。

ここで述べたいのは『ネット禁止』ということではなく、「遊ぶなら遊ぶ、勉強するなら勉強する」というメリハリです。
具体的な行動を通じて集中力にメリハリをつける
ここで大事なのは、あいまいな形ではなく「明確に分かる形で」スイッチを切り替える、ということです。

『勉強する時には勉強に集中、休むときは勉強せずに休む』というのを具体的な形に落とし込む、とも言えます。
メンタリティ自体を変えるよりも物理的にオンオフを切り替える
集中力の改善について考えるとき、もっとも直球な方法はメンタリティそれ自体を変えることです。
しかし、実際のところ、個々人のメンタリティを直接変えるのは非常に難しいことです。

ここで述べているのは日々の気分の波についてではなく、個々人の根本的な精神構造や性格の話です。
根本的なメンタリティが大きく変わるパターンを類型化してみると、一般的には以下の3通りにまとめられるかと思います。
- 精神疾患や脳疾患など
- なんらかの衝撃的な出来事をキッカケに短期間で劇的に変わる
- 長い期間を経て少しずつ変化を積み重ねていく
1はさておいて、2のパターンのような出来事にはいつどこで出会えるかが分かりません。
そうなると3の地道な積み重ねが基本路線になってくるのですが、メリハリがつけられないと積み重ねることもまた難しい……という事態になってしまいます。
ゆえに、メンタリティの部分を変える努力よりも、集中力のスイッチを物理的に作っていく方が先決であり、圧倒的にカンタンです。

五郎丸ポーズで有名になったルーティンも、物理的な行動を通じてオンオフを切り替えている一例です。
※なお、ルーティンの話はそれだけで膨大なテーマになりますので、興味のある方は是非とも研究して取り入れてみて下さい。当記事ではそれ以外の具体的な方法について考えていきます。
勉強中はスマホを電源オフ→物理的なルール化が意識のスイッチにも
勉強のメリハリを付ける第一歩は、スマホ電源オフをルール化することです。
スマホ等の電源をオフにするというのは、物理的に誰でもできる上に効果の高い方法です。
なお、PC・タブレットがメインの方は、スリープモードなどの対応を取ると良いです。
「勉強中にどうしてもネットが気になって困る」というような人は、どれだけアプリをアンインストールしようとブックマークを断捨離しようと、いつの間にかまたネットやアプリを触っているのではないでしょうか?

あるある。中毒性のヤバいゲームを頑張って消しても、気付いたらまた再インストールしてる。まさに時間泥棒。

それならば、「勉強中だけは電源オフ」というところから始めましょう。急にすべてを変えようとする必要はありません!
気に入ったアプリもゲームもSNSも、「勉強時間外で」好きにやれば良いのです。
そのかわり勉強中には電源ごと切ってしまうことで、物理的なスイッチが意識的なオンオフの切り替えにもなります。
まずはこのように誰にでもできる最低限度のルールを実行することです。
電源オフ・スリープモードにすら出来なくて悩んでいるのであれば、インターネット依存症の専門機関に相談することを検討した方が良い段階です。もはや自力では解決できないということを意味するからです。
(人によっては、より根源的な心理的要因が見つかるかも知れません。)
※なお、「勉強中にネットを遮断する」というのは、以前の記事で紹介した「即ググる習慣」とは相反します。
ですが、ネットが気になるあまり勉強自体が疎かになってしまっては本末転倒ですので、キッパリOFFにしましょう。
そのかわり、疑問に思った言葉や分からないトピックをその都度メモしておいて、1日の学習範囲が一通り終わった後ですべてググりましょう。そこで集中が解けても、すでに一定の学習量をこなしているならば構いません。
なお、ググるべき検索ワードもToDoリストで忘れないように記録するのがオススメです。
誘惑に負けるならば物理的に学習スペースから隔離する
ここまで、勉強への集中を乱す代表例としてスマホを取り上げました。
ただ、これらはスマホに限った話ではありません。
つまり、誘惑に勝てないと分かっているならば、そうした誘惑を最初からすべて物理的に隔離すれば良い、ということです。
ついゲームをしてしまうならば、ゲーム機ごと隔離すれば良いのです。マンガを読んでしまうならば、マンガ部屋を隔離すれば良いのです。
スマホをどうしても触りたくなるならば、ロッカーに入れておくという手段もあります。
学習スペースにそのようなモノがあるならば、他の部屋に隔離しておけば良いのです。
あるいは、そもそも最初から学習スペースに気を惹くモノを置かなければ良いのです。

お願いします!どうかニンテンドースイッチだけは手元に……。

はい隔離。後で返すから、今は勉強のスイッチを入れましょう。

……後で絶対スマブラやろう。
一日の学習量を先に決める、逆にそれ以上は勉強しない
次に、勉強を始める「前に」一日の学習量の目安を決めてしまいましょう。
予定の組み方については、過去記事を参照して下さい。
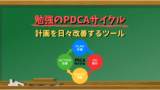

メリハリに悩んでいる人は尚のこと、勉強時間で学習量を測らない方が良いです。
なぜなら、どれだけ集中が切れていても1時間は1時間として同じようにカウントされてしまうからです。
具体的に言うと、スマホ片手にSNSとソシャゲーをハシゴしながら上の空で勉強していても丸々勉強時間にカウントしても良いですか?ということです。
それならば、1時間だけ全力で勉強してあとは遊び倒すスタイルの方が遥かに効率的ですらあるかも知れません。
加えて、「出来る限り勉強する」といったような具体性に欠ける目標設定も非推奨です。
特にメリハリの苦手な方がそのような目標設定をしてしまうと、早々に中断して遊び始めるか長々と続けて息切れするかのどちらかになりがちだからです。

息切れしても、続けられるのなら良いんじゃないですか?

いいえ、息切れ状態で続けたところで、学習効率が激減しては意味がありません。それに、三日坊主で終わっては本末転倒です。
仮に医学部を目指す努力家タイプのように延々と勉強が続けられたとしても、学習のパフォーマンスは疲れとともに落ちていくことでしょう。
ましてやそのような努力家でなければ、無理なく続けられるような学習スタイルを身につけるのが先決です。
だからこそ、「最初に決めた分だけ勉強する」ことから始めた方が良いです。
これにより、集中して終わらせるべき学習量が具体的に見える化しますし、さらに明確なゴール意識にもつながります。
もしも自分で決めた学習量が足りないと感じたならば、先ほどのPDCAサイクルのように、次の日から増やせば良いだけです。もちろん逆もしかりです。
自習室、学習環境も意識的にメリハリをつけるスイッチに使える
前回記事では、自習室のデメリットを中心に解説しました。
確かに、自習室や図書館で勉強することが必ずしも良いこととは限りません。人によっては、むしろマイナスの影響の方が大きいかも知れません。
ですが、自習室や図書館という場所そのものが意識を変えるスイッチになっているならばそれはそれで有効です。
そうした施設に限らず、学習環境それ自体をオンオフのスイッチに結びつけることもまた物理的にできる手段の一つです。

もちろん自習室でもグダグダになっていては意味がありません。
勉強するときだけ特別な何かをする、日常と切り分ける
学習環境をスイッチに使うというのは効果自体は高いですが、時間的な都合という問題があります。
それに対して、勉強するときだけ特別な何かをするという、もっと手軽なスイッチの切り替えもあります。
例えば、『試験本番は午後ティー』というのもまさに意識のスイッチの切り替えです。(ただしカフェインについて熟知していないと逆効果)
こうしたことを普段の勉強にも取り入れれば良いということです。
- 勉強するときだけ特定の音楽を聴く。
- 勉強するときだけドクターペッパーを飲む。
- 勉強するときだけブレスレットをつける。
特別な何かというのは、周りに迷惑さえ掛けなければ何でも良いです。
ですが、一点注意すべきは、「普段はやらないこと」をするということです。
なぜならば、普段の勉強しないモードと切り替えることが肝心だからです。
ストップウォッチは必需品、試験本番のトレーニングにもつながる
先のPDCAサイクルでも解説したように、学習予定はページ数や問題数などの具体的な分量で決めるのがオススメです。
その上で、「その学習内容を何分以内に進めますか?」という所要時間の設定が必要です。
学習量を決めたところで、勉強が進まず時間だけが過ぎてしまっては無意味だからです。

個人的には、ストップウォッチは必需品です。問題集などに時間の目安が書いてあるならば、最初は目安通りに時間を測るべきです。
結果的に解けないならば、それはそれで構いません。あとで見直し・解き直しをして改善していけば良いだけです。
それよりも、タイマーで測っている時間中は全力で進めるという習慣づけが第一です。
時間を測ることで、当然ながら集中力のメリハリの訓練にもなりますし、実は試験本番のための超・実践的なトレーニングにもなります。
時間感覚も、はじめはよく分からなくとも、続けていくうちに少しずつ身についていきます。
注意:スマホ封印・解約までやるのはITリテラシー的に非推奨
一方、スマホ・ネット禁止ルールが先鋭化すると、ネット環境を長期間にわたり完全封印したり、さらにはスマホ解約にまで踏み込む方も居ます。
ですが、ネットを生活から完全にシャットアウトするのは、今後のIoT時代に逆行するため推奨できません。
なお、ここでいうIoT時代というのはすなわち、社会のすべてがIoT技術を前提とした構造になる、ということです。
そこで前提となってくる能力はITリテラシーです。
リテラシーというのはカンタンに言えば読み書きのことですが、今後の社会は読み書きと同じようにITを使いこなす能力が前提になる、ということです。
言い換えると、それはデバイスを自分自身の身体の延長として使いこなし、ITを感覚的に理解することである、とも言えます。
ITリテラシーが生活の中で身についていれば、そこを土台として専門知識や技術を上積みしていくこともできます。
それはすなわち、将来の仕事やライフワークにも直結するということです。

ネットを完全封印するということは、世界規模の莫大な情報ソースから切り離されることと同義です。
勉強の目的は、広く考えるならば「自己成長のため」であるといえます。
そうした観点からすると、本当に求めるべきはITを有効活用して自分自身の成長速度を加速させることではないでしょうか。
以前の記事で推奨した即ググる習慣というのもその一環です。
休みたいなら休憩して良い、大事なのは学習ペースの継続性
ここまで、集中力をオンにするための方策について考えてきました。
ですが、逆に集中力をオフにすることもまた大切です。
人によっては年中バイタリティに溢れているようなタイプも居ますが、ごく少数です。
そのような方は、きっと当記事にたどり着く暇すらなく自発的に活動を続けていることでしょう。
大抵の人間は、意識を張り詰めすぎるとそれ以上の反動が来ます。
いわゆる燃え尽き症候群などはその一例で、真面目に頑張り続ける人間ほど反動は重くなります。
そうして頑張った分以上のものを失ってしまっては元も子もありません。
一方、そこまで行かないようなタイプであれば、三日坊主で終わってしまうことでしょう。4日以上続いたところで、反動ですっかり勉強に嫌気が差してしまっては更に学習意欲が無くなってしまいます。

私の経験上、普段から努力しないタイプほどオンオフの加減が分からず短期間で息切れしてしまいます。
ここでカギとなってくるのは、自分に合った学習ペースです。
仮に1日30分の努力だったとしても、1ヶ月で900分=15時間になります。
それも、毎日30分だけメリハリをつければ、単なる15時間という数字ではなく全力で集中した密度の濃い15時間ということになります。
これだけあれば、模試の演習と復習を毎月1周回せる計算になります。

1日30分だったらなんか出来そうだな。

私ならもっと増やせそう。30分×3とかにすればむしろ時短かも。

『あっ、これくらいだったら出来そう』というラインから始めれば良いのです。
まとめ
カンタンにおさらいすると、以下の通りです。
- 内面や性格を変えるよりも、物理的に出来ることから先に取り組む。
- 気が向いたらルーティンも取り入れてみる。
- 勉強中はスマホetcの電源OFFルールで物理的にネット環境を遮断する。
- 自習室が自分に合うならば集中のスイッチとして利用する。
- まず一日の学習量を決める、それ以上はやらない(そしてPDCAサイクルへ)
- ストップウォッチで所要時間を計測しつつ実践的に勉強する。
- ITリテラシーが将来性に直結するため、ネット環境自体は捨てない。
- 集中力をオフにすることもまた大事、自分に合った学習ペースを押さえる。

大切なのは、やろうと思えば出来ることから始めるということです。
大切なのは、こうしたカンタンなことから実践するということです。実際に自分でやらないと意味はありません。
そして、実際に試みた上でどのような展開になるかは個々人のメンタリティによる部分が大きいですので、自己観察を通じてさらに自己改善していきましょう。
※記事中でご紹介した関連記事
語彙力を鍛える方法は『ググる習慣』!ネット検索で日常から知識力を深める教養生活|論理的思考のコツ②
勉強の先延ばし癖は今すぐ克服!タスク管理とToDoリストで行動改善|勉強法・教育法③
勉強の計画倒れはPDCAサイクルで改善!具体例で分かりやすく解説|勉強法・教育法⑬







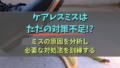

コメント