前回記事では、具体的な目標設定を通じて、大まかな勉強量を見積もっていきました。

でも、頑張って計画を立てても、計画通りに上手く進まないのが世の常なんですよね……。

計画を立てっぱなしで放置すれば計画倒れするのは当然です。そこで登場するのがPDCAサイクルです。

PDCAサイクル?初耳ですけど、サイクルを回すってこと?
それでは、PDCAサイクルを使った学習計画の回し方について具体的に解説していきます。
PDCAサイクルとは、その具体的な意味
PDCAサイクルの基本的な意味
まず、PDCAサイクルは、バリバリのビジネス的手法です。
PDCAというのは、以下の頭文字を組み合わせたものです。
- Plan=計画
- Do=実行
- Check=評価
- Action=改善

ビジネスの場合は利益を上げることが目的ですから、カンタンに言えば「利益アップを阻害している要因を改善しよう」というのがPDCAサイクルの狙いです。
勉強でいえば、利益というのはズバリ成績アップのことです。

以下、PDCAの意味を勉強の流れに当てはめてそれぞれ説明します。
Plan=計画:スケジュールに学習量をザックリと落とし込む
まず、「Plan=計画」は学習計画の話で、文字通りの意味です。
例えば、1年後の受験を目指すならば1年単位の計画になりますし、定期試験であれば1~2ヶ月プランになることでしょう。
前回も説明したように、ここで大切になるのはスケジュール感覚です。
例えば「いつまでに、どれだけの問題集を進めるか」と言ったように、具体的な学習量で計画します。紙の本を使うのであれば、ページ数や単元が単位になります。
※前回記事で立てた学習計画の例、図の『問題集進捗』が具体的な学習量の目安


学習時間で計画を立てるのはオススメしません。なぜなら、集中力ゼロ状態での勉強も学習時間としてカウントされてしまうからです。
Do=実行:計画に基づいて勉強を進める
次に、「Do=実行」は日々の勉強のことです。
ただし、PDCAサイクルでいうDoというのは、Planで立てた学習計画に基づいて淡々と勉強を進めるイメージです。

ここで計画を使わないのであれば、そもそも計画を立てた意味がありません。計画倒れ以前の問題になります。
逆に言えば、Doを前提とした現実的なプランを立てておく必要がある、ということでもあります。
Check=評価:学習内容やテストの成績を自己分析、PDCAの核心
そして、「Check=評価」は勉強内容や試験の成績などの自己分析です。
勉強であれば、計画通りに勉強が進んだか、あるいはなぜ当初の計画通りに上手くいかなかったのかを具体的に分析することです。
試験の成績であれば、実際の成績が目標と比べてどうだったか、もし目標に届いていなければ具体的にどの科目のどの分野が実力不足だったかを分析することです。
実際のところ、このCheckこそがPDCAサイクルの核心になります。
なぜならば、Checkで問題点を見逃してしまうと、次のAction=改善につながることなく放置されて同じ失敗を繰り返すからからです。

ここが計画倒れを改善するための第一歩です
Action=改善:Checkで分析した課題の具体的な改善策
最後に、「Action=改善」は、Checkで見つけた課題に対する具体的な改善策を講じることです。
例えば、先ほどのCheckで『勉強が上手く進まなかった原因はスマホの触りすぎだ』と分析したのであれば、勉強中はスマホの電源ごとオフにするといった対策が考えられます。
あるいは、『英語の長文読解が実力不足だ』と分析したのであれば、長文読解の問題集を別途進めれば良いという話になります。

先ほどのCheckで問題点を見つけられたとしても、具体的な解決策が無いと問題箇所はそのままになってしまいます。
そして2周目ののPDCAサイクルへとループしていく

PDCAというのはカンタンに言うと、『計画を進めたら後でちゃんと見直して改善しよう』という感じですね。

基本的にはそうですが、PDCAサイクルの真骨頂は『サイクルを回し続ける』部分にあります。
つまり、「P→D→C→A→P→……」と、PDCAの流れがループしていくということです。
PDCAサイクルの図を見てみると、Actionから次のPlanにつながっていることに気付くかと思います。

例えば先ほどのActionの説明で、『勉強中はスマホOFF』『英語の長文読解の問題集を進める』という改善策が出ました。
こうした改善策を次のPlan=学習計画に具体的に入れるというのが「サイクル」の意味です。
前者であれば学習環境の具体的な見直し、後者であれば長文読解用の問題集を次のプランから追加するということです。

そうして2周目のPDCAサイクルが回ったら、3周目のPDCAサイクルで更に改善するという流れになります。
世の中には、完璧な計画は存在しません。
計画はあくまでも不確実な将来に向かって走り出すための目安です。
そこでPDCAサイクルを使うことにより、計画を着実に改善していくことができるのです。
そうして、元の計画は次第に「使える計画」になっていきます。
1日単位のPDCAサイクルで復習勉強を回す

大体の意味はなんとなく分かったけど、具体的にどうすればいいかよく分からないかなあ。

最初はザックリとした進め方で全然構いませんので、とにかくサイクルを実際に自分で回してみましょう。
PDCAサイクルのポイントは、サイクルを回して少しずつ自己改善していく点にあります。
ですので、いきなり長いスパンのPDCAを回すよりも、まず最初は一日単位でPDCAサイクルを回していく方が分かりやすいかと思います。
一日のPlan:今日進める学習量を具体的に決める
まず最初のPlanとして、「今日1日でこれだけの勉強を進めよう」と決めることです。
このとき、先ほども述べたように、勉強時間で予定を決めるのはオススメしません。
例えば、一つの難問に引っ掛かって何の進展もないまま2時間が過ぎるのと、難問は後回しにして2時間で問題集を20ページ進めるのとでは、同じ学習時間でも学習量は全く違うはずです。
なお、一つの難問を深掘りしていくのもそれはそれで一つの学びですが、問題集のページを進めていかないと現実問題として復習が間に合いません。
ですので、問題集にしても参考書にしても、「このページからこのページまでを今日中に進める」と言ったような具体的な量で決めてしまうのが理想です。

分からない問題は余った時間で調べるか、先生等に質問すれば良いのです。そうした解決策もまた計画の一環です。
※なお、Planの具体例は↓の記事を参照して下さい。
勉強の目標の立て方は長期→中期→短期目標で!簡単な目標設定の例|勉強法・教育法⑫
この記事で述べているように、全体として必要な学習量をザックリでも良いので見積もった上で機械的に週割り・日割りしていくのが最も分かりやすい方法です。
一日のDo:まずは予定通り勉強を進める、分からない問題はチェック
Planの次のDoは、とにかく勉強することです。
ポイントは、Planで計画した学習内容に沿って進めるということです。
そのためには、ある程度考えても解けない問題は飛ばして次の問題に進むことです。
※なお、答えが出ないなりにも考えを組み立てていくことは大切です。見直すべきは、思考が止まったまま時間だけが過ぎていくような状況です。
例えば「5分間手が止まったら飛ばす」のようなルールを作るのも一つです。
そのかわり、飛ばした問題は後で分かるようにマークしておきましょう。

この「難しい問題に囚われないで後回しにする」という立ち回り方は、試験本番でも重要な解答テクニックです。
一日のCheck:プラン通りに進んだか、そして学習内容自体のチェック
一日の学習が終わったら、次はCheckです。
まずは、そもそもPlanで決めた学習内容を全部こなせたか否かを確認します。
その際、分からなくてスキップした問題はそれはそれで構いません。それが勉強の常です。
もしも早々に全て終わってしまったならば、そのまま今のサイクルを続けても良いですし、次のプランで演習量を増やすというのも一つの選択肢です。
一方、事前の計画通りに進まなかった場合は、具体的にどれだけの問題が残ったかをチェックします。
その上で、なぜプラン通りに学習が終わらなかったのかを分析します。
ありがちな原因は以下のような感じではないでしょうか。
- ついつい勉強せず遊んでしまった。
- 一つの問題に長く引っ掛かってしまった。
- 計画した勉強量が多すぎた、時間の見積もりが甘かった。

あ~、あるあるだわ。特に1番目が。
ここまでは内容以前の形式的なチェックの部分です。
それに対して、学習内容自体のチェックも必要です。
まず、問題演習で解答・解説が手元にある場合は、丸付け・採点だけでなく間違った問題の見直し・解き直しまで進めているでしょうか。
その場で解き直しをしても解けないのであれば、それは理解できていないのと同じです。
それに加えて、先ほどのDoの段階で分からなくて飛ばした問題にマークを付けているはずです。
そこで、解き直しをしても解けない問題にも同じようにマークしておきましょう。

ここでマークが付いている問題こそが改善すべき課題点です。
こうして、今日一日の学習内容の自己分析が終わります。
一日のAction:Checkで見つけた課題点への具体的な改善策
それでは、忘れないように先ほどのチェックで挙がった課題点の改善策を考えましょう。
まずは形式的な部分です。
- ついつい勉強せず遊んでしまった →つい遊ばないような学習環境を作る!
- 一つの問題に長く引っ掛かった →ストップウォッチで1問あたりの時間を決める!
- 計画した勉強量が多すぎた →次のプランで量を減らす!
続いて、学習内容の部分です。
先ほどマークをつけた問題を、具体的にどのように解決しますか?
今から自分でググって調べてみるのも一つですし、週末にまとめて調べるのも一つです。
あるいは、先生などに質問するのも一つです。

一回で上手く解決できなくても構いませんので、必ず何らかの対処をしましょう。そこから試行錯誤することが肝心です。
次のPlan:前のActionで出た改善策を踏まえる
そして、次の日は2周目のPDCAサイクルに入ります。
Planの基本的な立て方は1周目と同じですが、必ず先ほどのActionを織り込みましょう。
学習環境を変えるならば、確実にスケジュールを組みましょう。
ストップウォッチを使うならば、今すぐ準備して実際に今日から使いましょう。
学習量の調整が必要であれば、実際に予定に落とし込みましょう。
また、昨日分からなかった問題を先生に質問すると決めたならば、実際に質問しましょう。先生の時間の都合が合わなければ次の機会を伺いましょう。

まずは何よりも、先延ばしせずに実行することです。2周目でも上手く行かなければ、次のサイクルでまた改善策を検討すれば良いのです。
そして1週間単位のPDCAサイクルを構築する
1日単位のPDCAサイクルの感覚が分かったら、次は1週間単位でPDCAサイクルを回すことです。
PDCAの各々でやるべきことは先ほどの1日単位のサイクルの例とほぼ同じです。
また、学習プランの立て方は前回記事と同じく、必要なトータルの学習量を週割り・日割りするのが基本です。
ですが、前回紹介した、期間に応じて等分で割り振る方法はあくまでも暫定的な目安です。
実際のところは、人によって各曜日のスケジュールの都合が違ってくることと思います。また、休日の使い方ともなると勉強以外にも様々な選択肢があることでしょう。
だからこそ、PDCAサイクルの中で実際に走りながら計画や勉強の流れを修正していくのが有効な手法になってきます。
そうしていくうちに、例えば「月曜・水曜は勉強せず、火曜・木曜・金曜で授業内容の復習を進め、土日で解き直し」というような曜日ごとのパターン化も可能になってきます。
まとめ
以上、PDCAサイクルについて具体的に解説しました。
学習計画というものは当初の見積もりから立てられたものに過ぎません。
実際に計画通りに進めようとしても、現実と計画とのギャップが必ず生じることでしょう。
だからこそ、当初の計画のまま進んでもいずれ計画倒れするのは半ば当然の話です。
それに対して、PDCAサイクルは現実と計画とのギャップを埋めるツールです。
下手でも大雑把でも全然構いませんので、何よりもまずは自分自身で実際にサイクルを回してみることが最も大切です。
そして、そのサイクルの中で生じた問題点を分析して改善策を講じていくことにより、学習計画が現実の勉強スタイルに合うように軌道修正されていきます。
また、日頃の自分自身の勉強の仕方から見直していくことで、勉強の進め方それ自体も改善していくことが出来ます。
※是非とも次回記事のCAPDサイクルも参考にしてみて下さい。
※なお、基本的な目標の立て方については、以下の記事を参考にしてください。
※PDCAサイクルの前に、解き直しの重要性を理解することが大切です。
解き直しこそがコスパ最強の復習勉強!模試やテストに限らず問題演習から解き直す|勉強法・教育法②
※学習計画以前に、先延ばし癖を改善する必要があります。
勉強の先延ばし癖は今すぐ克服!タスク管理とToDoリストで行動改善|勉強法・教育法③


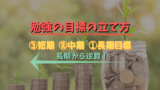



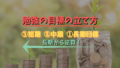


コメント