本日2019年4月1日、新元号「令和」が発表されました。
新元号に対する受け取り方は多数だと思います。
その中でもビジネスやゲーム理論に触れてきた方には、ある単語が連想されたかもしれません。
それは、「零和」ゲーム(ゼロサムゲーム)という概念です。
(実際、ネット上でも同じような連想を抱いた書き込み等が多数見られました。)

「ゼロサムゲーム」は、これからの令和時代に向けて改めて考えるべき重要な概念です。
ゼロサムゲームは綱引き、自分の利益が相手の損失
ゼロサムゲーム(零和ゲーム)とは、誰かにとっての利益が他の誰かにとっての損失となり、トータルの損益はプラスマイナスゼロの状態になる、というような概念です。
ゼロサムゲームの例は、枚挙にいとまがありません。
その中でも、もっとも象徴的な例が「綱引き」です。
綱引きは、周知の通り、中心点からどれだけ自チーム側に綱を動かすことが出来たかで勝敗が決します。
例えば、『紅組対白組』の綱引き合戦であれば、以下のような具合になります。
- 中心点のまま:紅組0―0白組
- 紅組がリード:紅組50cm―△50cm白組
- 白組が逆転 :紅組△100cm―100cm白組
このように、綱引きは何をどうやっても「紅組のマイナス=白組のプラス」の関係が不変です。(逆も然り)

えっ?紅組がマイナス20センチで白組がプラス30センチとかにはならないの?

……差し引き10センチ分の綱はどこから出てくるの?

あ、そっか。そういうことか。

常にトータルはプラスマイナスゼロ、これこそが零和ゲームです。
※なお、この『紅組対白組』という構図は、二項対立にも通ずる概念です。
令和時代、零和ゲームでなく日本人の和の時代へ
ゼロサムゲームからシナジー効果を追求する時代へ
こうしたゼロサムゲームの考え方を現実の社会経済に当てはめてしまうと、要するに『限られた資源の奪い合い』という世界観となってしまいます。
あるいは、『他人に損失を掴ませて自分が利益を得る』ような構図も零和ゲームの特徴です。
ですが、現実では必ずしもゼロサムゲームが当てはまるとは限りません。
というよりも、むしろゼロサムゲームにならないような創造的な経済活動を目指すことこそが令和時代に強く求められる方向性です。(なお、いわゆるクリエイティブ業に限らず、マイナス要因を除去するような仕事もプラスサムに貢献します)
そして、そこから更に踏み込んで考えるべき概念が、シナジー効果(相乗効果)です。
シナジー効果とは、カンタンに言えば「1+1が2ではなく3にも10にもなる」、という相乗効果です。

別の何かを組み合わせることによって、単純な足し算を超えた化学反応が生まれる、とも言えます。
マンガ作りの具体例でシナジー効果をカンタン解説
例えば、マンガの制作を例にシナジー効果について考えてみましょう。
仮にAさんとBさんが居たとします。
Aさんは美術的センスが非常に高く、デッサン的な上手さはもちろんのこと、マンガ的な演出表現も実に上手いです。
しかしAさんはシナリオ作りが致命的に苦手です。
一方、Bさんはマンガのシナリオの展開やコマ割りなどを考えるのが非常に得意です。
しかしBさんは致命的に絵の技術が低いです。
AさんもBさんも、単独で有名漫画家になるのは非常に難しいです。
ですが、もしAさんとBさんがネットを通じて知り合って共同制作をするとどうなるでしょうか。
ネットコミュニティの中では、群を抜いた存在となるでしょう。
そうしてトントン拍子に行けば、大手週刊誌に連載が決まるかも知れません。
シリーズが長く続けば、累計発行部数で数千万部を突破するかも知れません。続編や新作にもつながるかも知れません。
AさんもBさんも、これで知名度が高まれば、更にコラボの幅が広がることでしょう。
ここで考えるべきは、こうして制作された共同作品は単純にAさんとBさんを足し合わせただけの効果なのかということです。
具体的に言うと、もしAさんとBさんの共同作品が2000万部売れたとすると、「Aさん1000万部+Bさん1000万部=2000万部」なのか、ということです。
Aさんが単独でマンガを描いたところで、シナリオが致命的に面白くなければ1000万部到達は遥かに難しいことでしょう。
同じくBさんが単独でマンガを描いたところで、落書きのような絵では見向きもされないことでしょう。
そもそもAさん・Bさん単独では大手週刊誌の連載も勝ち取れなかったでしょうし、そうすると二人ともその他大勢の中に埋もれたままだったかも知れません。
このように、1+1が100にも1000にもなることこそがシナジー効果の強みです。
IoT技術・AI技術の発達でシナジー効果は更に倍加する
これからの令和時代で間違いなく中心となるのは、IoT技術やAI技術の発達です。
例えば先ほどのAさんとBさんの例においても、インターネットを媒介とすることにより、従来と比べて容易に結びつきやすくなります。
全国各地の人材、才能がクラウド的にもっと結びついていけば、AさんとBさんのようにシナジー効果を生むためのマッチングが更に容易になっていきます。
その上、デバイス類の発達により在宅ワークが更に一般的になれば、もはや自宅にいながら全国各地の人々と協働することも可能です。これらはもちろん企業間のつながりも容易になるということです。
また、VRやホログラム技術の発達などにより、物理的・空間的な制約も更に無くなっていくことでしょう。
そこに、AI技術も全面的に絡んできます。
平成の時点でも、例えば将棋の藤井聡太先生は将棋AIとの対局・研究を通じて加速的に成長していったという話は有名です。
これはまさに、AI技術が人間の可能性の拡大に直結したことを意味します。
加えて、このようなAI技術は本来のポテンシャルからするとまだまだ黎明期に過ぎません。
将棋AIや囲碁AI、画像処理AIなどは、狭い専門分野に機能を絞った特化型AIです。
近年の自動運転技術ですら、画像処理・GPS・物理演算などの数種類の技術の組み合わせです。
それに対して、SFの自律型アンドロイドなどのように、多種多様な機能を統合して一つの知的生命体のように振る舞うAIを汎用型AIと呼びます。
果たして、単体でも人間を遥かに凌駕する特化型AIが、ビッグデータを活用しつつ相互に結びついていくと、いったいどれほどの相乗効果が生まれるでしょうか。
これまでの時代と比べると、まさにケタ外れの成長速度となっていくことでしょう。
もちろんその成長に人間もコミットしていくことになります。
人間同士のつながり、人間とテクノロジーのつながり、AI同士のつながり……。
そうして、全分野・全世界が更に高度なIoT技術で結ばれ、未知数レベルのシナジー効果を生み出す時代が到来することになります。(『人類の進歩を止めるような事態』さえ起きなければ)

そこでは、ゼロサムゲームなどと言っている場合ではありません。和を通じて爆発的な成長が生まれる時代になることでしょう。

乗るしかない、このビッグウェーブに!
まとめ
平成時代は、リーマンショックなどをはじめとして、資本主義の負の側面が強く露呈した時代であるとも言えます。
奪い合いの発想ではいずれ破滅が待っているだけ、ということです。強欲資本主義に未来はありません。
そこで大切になるカギが、まさに日本人のいう「和」です。
おだやかに、過度に争わず、IoT時代の新技術とも調和し、和合のもとに成長していく……。
そうした「和」がシナジー効果を増強し、「加速的な成長」と「経済のパイ全体の調和的な成長」を両立させることもできるはずです。自然環境との調和、いわゆる持続可能性もここに内包されます。
※もちろん談合を推奨しているわけではなく、より創造的かつ建設的に化学反応を起こしていくということです。

『零和ゲーム』の雨を晴らしていくことこそ、これからの令和時代に求められることではないでしょうか。


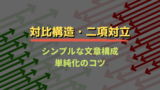



コメント