ルーズリーフは、勉強において非常によく使われる媒体です。
一方で、特に学校教育などにおいてはルーズリーフの使用は是非が分かれることと思います。
対して私の場合は、以前の記事でも述べたようにまとめノート自体がそもそも不要であるというスタンスです。
↓の記事で警鐘を鳴らしている問題点は、ノートに限らずルーズリーフにもそのまま当てはまる課題です。
とは言え、そんな私でも、ルーズリーフは「使い方さえ適切ならば」非常に有用なツールであると考えます。
そこで当記事では、ルーズリーフまとめに対する対比として「コピー用紙書き捨て」という勉強スタイルをご紹介します。

「やはりルーズリーフでまとめたい」という方にも参考になるように考えていきたいと思います。
ルーズリーフのメリット、ノートとの使い方の違い
まずは、ルーズリーフの特色について考えていきます。
ルーズリーフの真価はファイリングの自由さ、ページの組み換え
まずは何よりも、ファイリングの自由さがストロングポイントです。
シンプルに言えば、①ページ削除、②ページ挿入、③差し替え、の3点が容易に出来るという部分です。
これらは、ノートと比較すると分かりやすいです。
- ①ノートでページ削除したい場合は、物理的にページを破る必要があります。それによって他のページにも被害が生じかねません。また、ページ数も有限です。
- ②ページ挿入をしたい場合は、プリントや付箋を貼るといった擬似的な方法になります。
- ③ノートでページの差し替えをする際は、上記①②を組み合わせる必要があります。
その点、ルーズリーフは1枚1枚が独立しているため、ページの並びの組み換えが容易に可能です。
加えて、④ファイリングする枚数も自由、という側面もあります。
ノートであれば最初からページ数が決まっていますが、ルーズリーフであれば1ファイル辺り数ページから数百ページまで枚数を自由に変えられます。
ノートは時系列順が強み、ルーズリーフは日付を書いても散逸する
ノートについて触れたので、次はノートのストロングポイントについて挙げてみます。
ノートの場合
ノートの場合は、記録が時系列順に並ぶという点が良くも悪くも特徴的であると言えます。
先程のルーズリーフとの対比では、ノートはページの組み換えが難しいという側面が浮き彫りになりました。
ですが、逆に言えば、時系列順が大切になる場合はノートに優位性があると言えます。
分かりやすいのは学校の定期テストで、どれだけ高い意識で自学自習をバリバリ進めたところで、出題範囲は授業で実際に進んだ内容となるのが普通です。
その際には、実際の授業内容を追って復習していく必要があります。ゆえに、学校の授業内容を押さえるためにはノートの方が分かりやすいです。
勉強以外で言えば、アスリートの練習ノートやクリエイターの研究ノートなども時系列順が活きる例です。

ああ、サッカーノートとかね。「毎日の練習を見返して改善につなげる」とか何とか。

パティシエだったら、レシピ研究の足跡とかもわかりますね。
逆に言えば、順番を気にする必要がなければルーズリーフの方が便利ではないか、ということです。
ルーズリーフの場合
対して、ルーズリーフの場合は、先述の通り1枚1枚がバラバラです。
よって、順番が前後しやすいという点が逆にデメリットにもなりえます。
例えば先程の学校の授業の例で言えば、意識的に管理しないと順序がバラバラになりがちです。(この点も学校でノートを使うよう指導する大きな理由の一つだと推察されます)
これに対して、「必ず日付とページ数を記入しておく」というセオリーもありますが、それでも都度ファイリングしておかないと1枚1枚がバラバラの状況は変わりません。
よって、順序が大切な記録でルーズリーフを使う場合は、日付・ページ数記入&都度ファイリングの2点を併せて守った方が良いということになります。

ページ数のナンバリングは、同じ日付で複数枚に分かれる場合に付ければ良いかと思います。(9月18日の1/2、2/2など)
あえてコピー用紙で書き捨て勉強法をオススメする理由

では、ルーズリーフとノートをうまく使い分けましょう、ってことですね。

それはもちろんですが、私としてはむしろコピー用紙を使って書き捨てていく勉強法をオススメしたいと思います。
※以下は、私なりの個人的なスタイルです。
そのままご自身の学習に取り入れて頂くのも良いですし、「やはりルーズリーフなどでまとめたい」という方でも、対比することでルーズリースのさらなる有効活用につながれば幸いです。
ルーズリーフは「1枚にキレイにまとめる」という意識が働きやすい
まず私が最も気になる点は、ルーズリーフを使うと「キレイにまとめよう」という意識が働きやすい、という部分にあります。
確かに、キレイにまとめることが目的であれば、1枚単位で完結させられるルーズリーフは非常に使いやすいです。PCで言えば、スライドの1枚1枚のようなものです。
よって、「ファイルとしてキレイにまとめて後で何回も見返したい」という場合にはうってつけであると言えます。(あるいはプレゼンなどでも)
しかし、以前の記事でも述べた話と同じように、こと勉強においてはいくらルーズリーフを綺麗にまとめたところで頭に入らなければ時間と労力の無駄になります。
よって、勉強の手段であるはずのルーズリーフまとめが目的化してしまうならばいっそ辞めてみることをオススメします。

代わりにインプット学習には参考書類を使い、メインは問題集をバリバリ解き直すスタイルを試してみてはいかがでしょうか。
解き直しこそが効率最強の復習勉強!模試・テスト・問題集のサイクル|勉強法・教育法②
勉強はメモを書き捨てまくるべし!情報整理は理解の後に来るもの
勉強で大切なのは、アウトプット学習です。
過去記事でも述べたとおり、インプット学習で分かったつもりになったところで、自力でアウトプットできなければ問題は解けません。
読書量は国語力アップに無関係?アウトプット訓練とインプットの違いを知る|論理的思考のコツ③
理解度をはかる方法はアウトカムの確認!「分かったつもり勉強」を改善する|勉強法・教育法⑨
よって、問題を解く際にはメモを書きまくるべきであり、紙面をケチるのはNGです。
一方で、ルーズリーフを使うとつい「大事に紙を使おう」という意識が働きがちになるように私には見受けられます。(現役時代の同級生しかり個別指導塾での生徒さんもしかり)
ですが、ことアウトプット学習においては理解があやふやであろうと何だろうととにかく思考を書き付けるべきです。
それならば、いっそコピー用紙に書き捨てる学習スタイルをオススメしたいと思います。
紙質のレベルから言えば、500枚入り600円のコスパ品でも十分すぎます。計算過程でも思考整理でも、とにかく書き捨てていくべきです。
コピー用紙でも保管は効く、穴あけパンチでファイリングも可能
なお、「単に保管できれば良い」というのであればコピー用紙でも構いません。
むしろ社会人的には紙書類=コピー用紙です。
クリアファイルやポケットファイルにそのまま入れるのはもちろん、穴あけパンチを使えば30穴のファイリングすら可能です。

それだったらもうルーズリーフで良いんじゃ?

その辺りは個々の学習スタイル次第ですね。
「書き捨てていく途中でファイリングしたいものがちょくちょく出てくる」という方にはオススメです。
なお、どれだけ保管したいかによって用紙のクオリティを考える必要はあります。あまりにも安かろう悪かろうの紙質の場合は、耐久度が低い可能性もあります。
とは言え、別に長年保管する必要は無いというのでなければ、先程挙げたようなコスパ品のコピー用紙でも十分です。よほど保管状態が悪くなければ数年以上は軽くもつはずです。(少なくとも私の環境下では普通に保存が出来ています)
罫線なしのフリーハンドは自由度が高く、試験本番の実戦向け
これは好みの違いもありますが、罫線に囚われず自由に紙面を使えるというのは個人的にメリットに感じます。
確かにWordやExcelなどのようにレイアウトを整えたいのであれば、罫線入りや方眼紙の方に分があります。
ですが、とにかく思考を自由に書き留めたいのであれば、むしろ罫線なしの方が制約無しにスラスラ書けると私には実感させられます。(書ける、というより書き捨てられる)
加えて、試験本番で罫線入りのメモ用紙や方眼紙が配られることは少ないはずです。(定規禁止の場合すらあります)
それを考えるならば、むしろ罫線なしのメモ用紙のほうが実践的であると言えます。

なお、ルーズリーフにも罫線無しのものがありますので、興味のある方はそちらをお求め下さい。
ただしインクジェット用紙の場合はボールペンの詰まりに注意
ただし、上等なインクジェット用紙を使う場合はボールペンのインク詰まりに注意です。
この点は、ボールペンの特集記事で一部触れた部分です。
勉強のボールペンはジェットストリームがオススメ!インクのかすれる替芯は予備で対策│勉強アイテム・文房具①
ここで三菱鉛筆の公式サイトから該当箇所を引用してみます。
インクジェット用紙は、にじみ防止などの剥離しやすいコーティング剤が紙面に塗られています。ペンで筆記すると、このコーティング剤が剥がれてペン先にたまってしまい、書けなくなることがあります。
ただし、シャープペンにはほぼ関係ありませんし、万年筆でもよほど紙質の相性が悪くなければ滲まず普通に書けるはずです。(インクの裏抜けを気にする方は注意が必要ですが)
まとめ
以上より、勉強に使う紙媒体はメリット・デメリットを考えて選ぶのをオススメします。
ルーズリーフを使うべき局面というのは、ファイリングして自由に管理したい場合、あるいは罫線も使ってレイアウトを1枚毎にキレイに作りたい場合です。
対して、うまく管理が出来ないとバラバラに分散してしまうリスクもあり、また「キレイにルーズリーフをまとめよう」とするあまり手段が目的化してしまう恐れもあります。
一方で、アウトプット学習を重視するならば、コスパ品のコピー用紙をまとめ買いして書き捨てまくる方が効率的であると私は考えます。
そして、ルーズリーフに別途まとめたいという方でも、コピー用紙にアウトプットして思考整理し、理解した後でルーズリーフにまとめる、といった手段も取れます。

大切なのは、各々の学習スタイルや目的に合わせて紙媒体を使い分ける、という発想です。


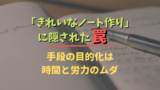




コメント