文法知識を使った長文読解……に入る前に、一つ前の記事をもう少し深掘りしましょう。
「それは明らかにあなたの感想ですよね?」
ロジックの中身に入る前に見直すべき重大な問題です。
ポイントは、「それって本当に筆者が本文で主張しているのか?」という観点です。

ここから4記事は読解問題のコアの部分を解説しますので、難しいと感じてもまずは一通り読んだ上で、後でまた読み返してみてください。
例題:論説文は筆者の主張が第一

では、前回の記事の例題に少し肉付けします。
次の文章を読んで問いに答えよ。
②その主眼となるのが、温室効果ガスの削減である。二酸化炭素の削減もこれに含まれる。温室効果ガスを削減することによって、温暖化が食い止められると識者は主張している。
③この点について、よく議論する必要がある。
問1、以下の選択肢の内容が筆者の主張として適当か否か答えなさい。
(1)地球温暖化対策を推進していくべきである。
(2)温室効果ガスを削減することによって、地球温暖化が食い止められる。
「(1)地球温暖化対策を推進していくべきである。」
×です。
本文では、「世界的に問題となっている」こと、そして「(温室効果ガスの削減について)議論すべき」とは言っていますが、温暖化対策それ自体を推進すべきとは一言も言っていません。

本当だ!よく見たら一言も言っていませんね!

えっ?そうか?なんか「温暖化対策しよう」的な感じの文じゃない?

先ほどの例題をもう一度よく読んでみて下さい。

うーん……ん?そうかなあ?
実のところ、この問題は一見カンタンそうに見えて実は国語の設問の核心部分に当たります。
もしこの本文を読んで「筆者自身が」地球温暖化対策を推進するように主張していると解釈するならば、それこそが主観的な忖度です。
現時点ではこうした点が分からなくても全然構いませんので、是非ともこのまま記事を読み進めてみてください。
この問題(1)も前回の記事で説明した『本文に書いてないから』という点がポイントなのですが、もうひとつ注意すべき点があります。
「あなたの意見は聞いていない」のです。
「筆者が本文で書いていること」を聞いているのです!
例えば地球温暖化問題については、当然のことながら懐疑派も居ます。地球規模の問題は科学的にはまだまだ分からないことの方が多いからです。
そこで、そうした懐疑派の書いた論説文が問題として出題されたとしましょう。
もしもここで、あなたの中では「地球温暖化対策は当然推進すべきだ!」というのが常識であったとしても、あなたの感想と筆者の主張には何の関係もありません。
この問題(1)で言うと、『地球温暖化対策を推進すべきだ』という意味合いの言葉を筆者自身が主張していなければ、それは筆者の主張ではないということです。
それを踏まえて、例題をもう一度読み返してみましょう。
②その主眼となるのが、温室効果ガスの削減である。二酸化炭素の削減もこれに含まれる。温室効果ガスを削減することによって、温暖化が食い止められると識者は主張している。
③この点について、よく議論する必要がある。

地球温暖化対策について述べているのは「世界的に問題となっている(=ただの一般論)」と「識者の主張」の2点だけであって、筆者自身は「議論する必要がある」としか主張していません。
※それでも腑に落ちない方は、「もしもこの文章が以下のように続いていたら?」と考えてみて下さい。つまり『ただの前フリ』は筆者自身の主張とは別物ということです。

例文がこのようにド直球に分かりやすく続いていれば、何となく読み進めていても後で気付くかも知れません。
ですが、読解問題が苦手な方も一定以上得意な方も、長文になればなるほど筆者の主張が何なのか整理がつかなくなってくるといった状況に心当たりはあるはずです。
地球温暖化に関する長文ともなれば、例えばあの国でこういう取り組みをやっているとか、温暖化でこういうことが起きるとか、持続可能性などの別の観点を新たに出してくるといった、具体例や話題の転換が山ほど入ってくることでしょう。
その中で、A説やB説といった様々な説も本文には出てくることでしょう。(もちろん本文で挙がった説がイコール筆者の主張になるとは限りません。むしろ反論の材料に使われるかも知れません。)
そうして本文の情報整理ができなくなってくると、なんとなく勘で答えてしまいがちです。
そこで、出題者は『受験生のあなたが』勘で考えそうなことを狙って選択肢に混ぜるのです。冒頭の例題も同じ発想で作っているのですが、もちろん罠です。
「次の文章を読んで問いに答えよ」の条件設定に『あなたの感想』が入る余地はありません。
「あなたの考えを答えよ」という問題ですら、本文のロジックを受けて論理的に返す必要があります。
『国語はロジック』なのです。

でも「あなたの考えを述べなさい」って問題もありますよね?

それは問題文がそのように指示しているから設問に従うというだけです。その時でも、必ず本文の内容を踏まえた上での主張でないと「次の文章を読んで」問いに答えたことにはなりません。
なお、解答欄に余裕があるならば、ヘタに字数稼ぎをするよりもいっそ1行目に筆者の主張の核心を書いた方が加点されます。
ただし、もちろんそれらはロジックのキホンを積み重ねていくことで成り立つものです。(最初からすべて出来る人は例外的です。)
物語文こそ『センス』に要注意
上の例文は論説文なのでまだ分かりやすい方です。知識を蓄えて問題演習をしていけばいずれ長文でも徐々に対応できるようになるはずです。
問題は物語文です。
「物語文はセンス」から「物語文はロジック」への発想の転換

「国語はセンス」の発想で物語文に取り組むのは私としてはオススメしません。というよりも、センスを磨く訓練はロジックの訓練より遥かに難しいことではないでしょうか。
……というあるあるパターンに心当たりのある方は、いっそのこと今日からセンスを切り捨ててAIマシーンのように読んでみましょう。できるできないは後回しで、そのように意識付けて読む努力をしてみましょう。
登場人物の心情を論理的に整理するのです。情報として整理するのです。
物語文における『心情』とは本文に書かれた表現から客観的に推論できることただそれだけなのです。(それが出来なければ設問の方に不備があります)
「メロスの心情として正しいものはどれか」と問われたら、本文に表現されているか否かが判断基準なのです。

逆に情緒面を理解するのが苦手な方も、同じように心情を文章から分析する練習を積むのが良いと思います。国語の問題である以上は何かしらの文章表現が手掛かりとしてあるはずです。
参考:物語文における私の思考プロセス実演
では、実際の私の思考プロセスを部分的に文字起こししてみます。
以下は、「これが正解です」という解説ではなく、私の一個人的な考察過程です。
よって、「ふーん、こんな読み方もあるのか~」とサンプルを見る感覚で読んでみてください。
なお、著作権が切れているため青空文庫で読めます。

そりゃあ「王様がムカつくから」でしょ。

それは読み手であるあなたの感想ですよね。
では激怒したまさにその時の具体的な描写はどこか?それがこの文。
聞いて、メロスは激怒した。「呆れた王だ。生かして置けぬ。」
<この一文の論理的解釈>
激怒の対象:王(Who)
激怒の理由:『聞いて、』(Why)
→(王の)何を聞いて?
→王がたくさんの人を殺した話
これが本文の記述的に一番ド直球の解答。字数制限が短いならこれでファイナルアンサー。
字数に余裕があるならば、激怒に至る理由の補強材料としてそこに「邪悪に対しては、人一倍に敏感であった」という客観的な人物描写を入れる。(※あくまでも本文に準拠)
「邪悪に対しては人一倍に敏感」→「邪智暴虐(≒邪悪)な王」についての話を聞く→だからこそ「激怒した」、と感情変化につながる因果関係の補強になる。
<模範解答>
なお、もう少し先で「人の心を信じること」がメロスと王の具体的な争点となっている(「人の心を疑うのは、最も恥ずべき悪徳だ」)ことが分かるため、問題の本文にそこまで含まれていれば老爺の発言の中の「(※王が)人を、信ずる事が出来ぬ」という論点も結果として拾える。
(時系列的には激怒した時点の後になるが、メロス本人が後から自身が激怒した理由を遡って追加説明したといえる。)
そうすると、このような解答も考えられる。
また、「罪の無い人を殺したから」という論点も、本文でメロス自身が主張しているため入れても良い。
……以上で行なっているのは、ただ書かれている本文を直接的な根拠として解釈・分析しているだけです。
物語文も、論説文と同じように技術的・論理的に解答に至るものです。
以上の模範解答(自称)でも、解答の根拠に私自身の主観的な感想の差し挟む余地はありません。あとは、解答欄や字数制限が足りない場合に取捨選択をしていくことになります。

もしも自分自身の解答の根拠を本文から示せなければ、それこそがあなたの主観的な感想ということになります。
具体的な技術論については、当シリーズの今後の記事でトピックごとに一つ一つ分解して説明していきます。

実際はいきなり最終形の答えへのプロセスがみえるというより、本文に沿って分析していくうちに少しずつ見えてきます。
なお、これは私の見解なのですが、Amazonなどのレビューの場で主観的な感想を述べる場合においてさえ、まずは客観的な内容分析を前提として踏まえる方がレビューとしての説得力が高いと思います。
まとめ
後半のメロスの例題については、読み手のみなさんにわかりやすく問題解説するというよりも、むしろ「自分の感情を排除してロジカルに読む」ことの実例として私の思考プロセスをフレッシュな状態で文章化してみました。
(長文読解の問題の解説を読んでもよく分からないのは、まさにこの『読解する時の思考プロセス』の部分が大きいはずです。)
このような方針で実際にセンター現代文がほぼ満点で安定していました。つまり、国語は当たり外れの問題ではないということです。センター国語で本当に疑義の残る問題というのは、あってもごく少数です。

センター試験の場合は択一問題ですので、消去法、つまり本文と矛盾する選択肢を弾いて残った選択肢を比較してどちらがより本文に即しているかで判断するのがベターです。
まず択一が出来ないと記述式を解答するのはより困難なはずです。
最初の例題の「(2)温室効果ガスを削減することによって、地球温暖化が食い止められる。」は次の記事で解説します。
NEXT →

※物語文の特集はコチラ


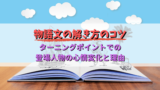



コメント