最近、大量のスプレー缶を屋内でガス抜きしたことが原因で、爆発事故が起きました。
当時は、メディアの媒体を問わず大々的に報道され、安全管理の周知も行なわれました。
しかし、それから2ヶ月足らずで、今度は福岡でカセットボンベのガス抜きが原因となり再び爆発事故が起きました。
(追記)2019年7月、今度は大阪府高槻市において、2人が死亡、2人が意識不明の重体という大事故が起きてしまいました。
これらの事件を教訓に、具体的な廃棄処分方法の再確認を行ないましょう。

このままでは行政サイドが規制の導入に踏み切らざるを得なくなる可能性もあります。当記事を機に、是非とも安全確保を徹底しましょう。
札幌・福岡・大阪、3つのガス爆発事件
札幌市消臭スプレー缶爆発事故、原因は屋内での大量ガス抜き
まずは、事の発端となる2018年12月16日の爆発事故についてです。

要約すると、以下のような流れになります。
- 札幌市のアパマンショップにて、除菌消臭スプレーの在庫が大量に余っており、「何らかの事情」からそれらを急いで廃棄する必要が生じた。
- そのため、密閉された室内で約120本分のスプレー缶のガス抜きを行なった。
- そして、湯沸かし器を使用しようと点火したところ、屋内に充満したガスに引火して大爆発を起こした。
- 結果として42人が重軽傷を負い、建物も大破した。

被害者の方の命に別状が無かったことだけが何よりも幸いでした。
ここでのポイントは、通気性の悪い屋内でガス抜きをしたという点です。
それにより、狭い空間の中で室内のガスの密度が異常に高まったということです。
今回の一件は全メディアで大々的に取り上げられ、その際に安全な処分方法の周知徹底もなされました。
その1ヶ月半後、福岡市早良区カセットボンベの爆発事故
そして、先ほどの事件からたった1ヶ月半後に、今度は福岡市早良区で同じような爆発事故が起きました。
http://news.livedoor.com/article/detail/15966885/(リンク切れ)
現時点で判明してる流れは以下のとおりです。
- 福岡市早良区のマンションの一室にて、室内で卓上コンロ用のカセットボンベのガス抜きを行なっていた。
- 室内に充満したガスが、何らかの原因で引火し爆発した。
- 結果、作業をしていた2人が負傷したが、命に別状は無かった。
札幌市のケースは臭いも特に発生しない消臭スプレーでしたが、福岡市のケースではカセットボンベが原因です。つまり、可燃性ガスそのものです。
そもそも爆発以前に、通気性の悪い屋内で大量にガスを撒くと中毒症状を起こす危険性もあります。
ましてや、同様の大事故が起きて日も経たないうちに爆発事故が再発してしまいました。
大阪府高槻市、スプレー缶3000本ガス抜きの末に爆発事故、死傷者多数
(追記)そして2019年7月6日、さらなる爆発事故が発生してしまいました。
- 大阪府高槻市の倉庫で、通信販売会社の社員がスプレー缶3000本を廃棄するためにガス抜き作業をしていた。(※産廃処理業者の倉庫で『何故か』販売会社の社員も作業している)
- 2019年7月6日、ガス抜き作業中に爆発が起き、作業員のうち2人が死亡、他の2人が意識不明の重体となっている。その中には、通信販売会社社員の「13歳の子ども」も含まれている。
- これらのスプレー缶は、台風で水没したために販売できなくなった商品であった。(ビジネス的に言えば、廃棄に費用が掛かるばかりで何の儲けにもならない)
- 警察はこの会社に対して業務上過失致死の疑いで捜索を進めている。
詳しくは現在捜査中とのことですが、個人的に疑問に思うのは、「なぜプロの処理業者に全て委任せず自社社員とその子どもが処理していたのですか」という点です。(婉曲)
このあたりも安全管理体制上の過失の重さに関係してくることでしょう。
……当記事は当初ユーザー側の視点から安全意識を高める目的で書いていましたが、たった半年で更に大規模な爆発事故が起きた上に、事故を起こしたのが販売側の大手企業であるというのが何ともやるせない気持ちになります。
具体的な処分方法、ガス抜き時の安全確認

考察はさておき、まずは何よりも安全な処分方法について再確認しましょう。
廃棄処分方法:第一にお住まいの自治体でググって確認を
まず第一に確認すべきは、ご自身のお住まいの自治体ではどのような方法になっているかという点です。
穴あけはすべきか、ゴミの分別はどのようになっているのか、特別な回収場所があるか、といった点は各自治体により異なってきます。
例えば、「スプレー缶 長崎市」でググると、以下のように特設ページがヒットします。ちなみに札幌の事故の3日後に更新されています。
長崎市では、穴開け禁止に変わっており、分別については燃やせないゴミの区分から更にスプレー缶類だけ隔離してゴミ袋に詰めるように、との指示があります。また、大量に廃棄する場合は、拠点回収も行なっている模様です。
このように、まずは「スプレー缶 ○○(お住まいの市区町村名)」で検索してみて下さい。
なお、現時点では中身のガス抜きは地域に関係なく必要です。
穴を開けて捨てる地域でも必ず事前にガス抜きを行ないましょう。
安全なガス抜きは「屋外」「通気性」「火の気が無い」の3点チェック!
続いて、2回のガス爆発事故の直接的な原因となった「ガス抜き作業」について、具体的に確認しましょう。

私自身も含めて『自分はもう分かってる』と思っている方ほど再確認が大切です。人に具体的に説明できるレベルが理想です。
屋外で行なう
まずは何より、屋内でガス抜き作業を行なわないことが大前提です。
今回の爆発事故により、密閉された空間でのガス抜きがいかに危険かは周知のとおりです。
室内でのガスの密度が増せば増すほど、爆発力は上がっていく傾向にあります。
ですので、必ず屋外でガス抜き作業を行なうようにしましょう。
通気性・風通しの良い屋外
同じ屋外でも、通気性の悪い場所であれば危険性は変わりません。
例えば、空気の滞留しやすい奥まった場所で大量のガス抜きを行ない、その場でうっかりタバコに火を点けようとすると何が起きるでしょうか。
ライターを着火した瞬間、引火して爆発する恐れもあります。
風通しという点で言うならば、近隣への配慮も大切です。
風向きや立地次第では、近隣住民へ迷惑がかかる可能性もあります。あるいは、異臭騒ぎから警察や消防が出動する自体になってしまう可能性も否定できません。
また、向かい風の方向に噴出すると自分自身に掛かってしまうため、細かい部分ですが留意が必要です。
屋外だから安全とは限りませんので、必ず周辺環境も確認しましょう。
近くに火の気が無いか確認
先ほどタバコの例でも触れましたが、近くに火の気がないか必ず確認しましょう。
近くで焚き火や調理が行なわれていませんか?
例えばキャンプ地でそのままガス抜きをする際には、近くで火を扱っている可能性は十分に考えられます。
また、大切なことなので2回言いますが、タバコはつい習慣で無意識に手が伸びてしまう場合もあります。風通しの良い屋外であればなおさら絶好の喫煙チャンスですので、尚のこと注意して下さい。
むしろ、タバコやライター類は必ず屋内に置いておくよう厳守するのが安全です。

どれだけ風通しが良くとも、ガスの目の前でタバコに着火しては元も子もありません。
なお、自分だけでなく周りの歩行者にもご注意下さい。
そして見落とされがちなのは、静電気です。静電気が原因の火事はスプレー缶の件に関係なく例年発生しています。
湿度が低く乾燥している日や、静電気の起こりやすい服装にも注意しましょう。
具体的なガス抜き方法は必ずラベルの説明文を読んで確認
環境面の安全確認が出来たら、次はガス抜きです。
スプレー缶の側面に具体的なガス抜き方法の説明が書いてあるはずですので必読です。
基本的には、通常使用するときと同じように空中に向かって押しっぱなしにして出し切る形です。その際、なるべく大気中に拡散するように出しましょう。近隣の方の所有物や公共物などにスプレーが吹き掛からないように注意です。
商品によっては、フタの裏側がガス抜きキャップ代わりになっていたりと、何かしらの配慮がなされていることも多いですので、それらも説明文をよく読んで説明どおりに使用して下さい。
泡状のものや液体成分の多いものなど、大気中に散布できないものの場合は、ビニール袋の中に紙類を敷き詰めてその中に噴射します。新聞紙が余っているのであればそちらで良いですが、紙の新聞を取ってない世帯も多いはずですので、トイレットペーパーなどを敷き詰めるのも一つです。
噴射し終わったら、ビニール袋をそのまま火の気のない屋外に置いて更にガス抜きします。それから自治体の区分に応じて袋ごと捨てて下さい。
ここで、ガス抜きが終わったら缶を振っても何の音もしなくなっていることを確認しましょう。まだ中身が残っている可能性もあります。
ガス抜きが終わった後の缶類の廃棄については、先ほど確認した自治体の情報に従って廃棄しましょう。

「分かりきっている」と思っている方ほど説明を読みましょう。
在庫が大量の場合、自信が無い場合は遠慮なく問い合わせ
今回の爆発事故のように残っているスプレー缶の在庫が多い場合、あるいは自分で廃棄処理をする自信が無い場合は、遠慮なく関係各所に問い合わせをした方が安全です。
先ほどの長崎市の例のように地域センターがある場合はそちらに問い合わせてみましょう。あるいはメーカー側への問い合わせも考えられますが、他社製品についての質問は原則として出来ませんのでその点は注意しましょう。
今回の事故の件のように本数が多い場合は、お住まいの地域の処分業者を探して依頼するのも一つです。

爆発事故による損害を考えるならば、ここで手間を惜しまない方が結果的に有益です。
思考実験:安全対策の為に法規制の検討もありうる

今回の事故は、法律・行政の側面からも注目すべき事態です。
以下、思考実験を通じて安全管理の大切さを再確認してみます。
どれだけ危険性を周知徹底しても人的事故は無くならない
今回の件で改めて考えさせられるのは、周知活動をどれほど行なっても危険行為をする人間は出てくるということです。
1回目の札幌市の事故のニュースをリアルタイムで見ていた方には分かると思いますが、当時は屋内でのガス抜きがどれだけ危険な行為か、また安全な処分方法についての周知も併せて各メディアで連日に渡って報じていたはずです。
周知活動に加えて、そもそもショッキングな爆発現場が全国で流れ続けていたはずです。映像のインパクトというものは言葉で説明するよりも遥かに印象が強いものです。
それにもかかわらず、たった1ヶ月半で2回目の爆発事故が起こってしまいました。
このことが意味するのは、どれだけ周知徹底を行なっても事故は無くならないということです。より広い観点から見れば、ヒューマンエラーの問題です。
以前、勉強法・教育法についての記事で、「人間は忘れる生き物である」という話について解説しました。
冒頭でご紹介した爆発事故のように、1ヶ月半でも忘れてしまう人がいるわけですから、更に時間が経てばなおさら今回の事故も風化していくことになります。
安全対策の問題は行政府にとって最重要課題
もしもこのような爆発事故が続いたならば、行政府はどのように考えるでしょうか。
行政府は、まず国民の身の安全性を第一に考えるのが大原則です。なぜなら、憲法上の人権として第一に求められるのは生命・身体の安全だからです。
そうすると、何かしらの具体的な安全対策を検討することになる可能性も十分に考えられます。(もちろん現状維持の可能性もあります。)
では、もし行政が動いた場合、具体的にどのような安全対策が考えられるでしょうか。
今回の福岡市の事故は、現状の周知・広報活動だけでは不十分であるということの証明となってしまいました。
もし広報活動の方向性で行く場合、前回の札幌市の事故における大々的な報道を超えるようなPR活動が必要ということです。
そのためには、いったいどれほどの規模でPR活動を行なう必要があるでしょうか。それによってどれだけの労力と税金が必要になるでしょうか。継続的に周知を行なうのであれば、時間も必要になります。
それでも、いずれまた爆発事故が起こっても不思議ではありません。実際、福岡市で再発してしまったからです。
事故が続けば各種の法規制が検討される可能性も
では、今後、仮にこうした爆発事故が続いて社会問題化したら行政府はどのように動くことが予想できるでしょうか。
例えば、スプレー缶やガスボンベの類いを購入する際には店頭で毎回安全確認を周知徹底することが義務付けられるかも知れません。そうすると、店側も消費者側も非常に煩雑で面倒なことになってしまいます。
あるいは、製造側に爆発事故の起こりにくいような設計を法的に義務付けるかも知れません。これはつまり、一般消費者側を最初から信用しない方向性です。
ですが、そうした設計が本当に可能なのか、仮に可能であっても製造側に開発コスト等が余計に掛かってしまうという問題もあります。開発コストが余計に掛かるということは、商品価格も上がりかねないということです。
また、廃棄処分の際に、いっそガス抜きを義務付けず、スプレー缶類のみ別ルートで特別に回収して、専門業者側がガス抜きも行なった上で廃棄する、といったスキームも考えられます。
ですが、その場合は、そうした回収ルートの構築、周知、そして専門業者側の人件費や各種施設など、莫大な予算が必要になります。
手っ取り早いのは、購入段階での規制です。一度に購入可能な本数を制限してしまえば、そもそも大量のスプレー缶が手元にあるような状況自体を減らすことも可能です。
ですが、複数回にわたって購入するケースは把握が困難ですし、札幌市の件はBtoB、つまり業者間の取引ですのでそうした規制は難しいです。
極端な話ですが、一番確実なのは免許制です。しかし、便宜性を考えるならばまず有り得ないことと思います。まずは何よりも、事故が再発しないことを願います。

とにかく面倒なことになるのは分かった。

こうした面倒なことが増えないように、私達自身が少しばかり面倒な安全対策をきちんと行なうことが大切ということですね。

スプレー缶を捨てる時は周りの人とも一緒に確認したいと思います。
まとめ
ガス爆発事故は取り返しのつかない人的被害に繋がりかねません。
今回の2つの爆発事故で負傷者の命に別状が無かったのはただの幸運です。それでも負傷者を多数出している時点で大事故です。
死亡事故が起こってしまいました。
このまま爆発事故が続いてしまった場合、スプレー缶類全般に対して規制が導入されてしまう可能性も否定できません。
法規制が導入されてしまうと、結果的に困るのは私たち消費者の側です。もちろん企業側のビジネスにも支障が生じます。
そのように行政が法規制や煩雑な手続きの導入を検討せざるを得なくなる前に、一人ひとりが安全管理を強く意識することが大切です。
(追記)消費者としての意識を高めるというのは当然ですが、企業側のモラルも問われる事例となってしまいました。

まずは自分自身が正しい知識を身に付け、それらを周りの方にも周知ができるようになること、それが一人ひとりのできる最善の方法です。


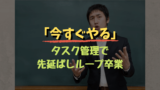
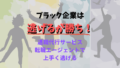

コメント