これから、「センター9割~満点レベルの視点から見た国語教科書の解説」シリーズを連載していきたいと考えています。
そこで、まずは当シリーズのスタートに至った理由、そしてその根底にある「情報化社会と国語教育を取り巻く状況」について触れてみたいと思います。

国語教育も「高度情報化社会」とともに進化していく必要がある、と考えています。
著者=サイト管理者である私について
著者である私、三兎セッコにつきましては、当サイトの趣旨の中でも触れています。
基本的には、「誰が書いているかではなく何が書かれているか」で判断して頂ければ幸いです。
……と言いたいところですが、あのGoogleさんが「専門性・権威性・信頼性」の重要性を公式にアナウンスしていますので、国語力に関する部分に絞って簡単にまとめます。
- 早稲田大学法学部卒業
- センター国語190/200点、総合点800超/900点
- 社会科学系ジェネラリスト、国家一種(官僚)の筆記試験合格
- 個別指導塾講師の経験者、小1から高3までの英語・数学・国語・社会の指導を経験
加えて、学校教育を前提とした場合、バリバリの論理国語に特化した法学部OBという点も特徴的と言えるかも知れません。
なぜなら、法学部出身者が国語の教員免許を取得するのは非常に困難であるからです。(ダブルスクールに近いようなことをしないと取得できない)
ですが、本来は法学的な思考こそ受験国語と親和性が高いと私は考えます。その理由は、「国語はロジック」の記事でも触れています。(※重要なのは出身学部というより論理的思考力それ自体)

なお、論理的思考の解説シリーズは既に連載済みですので、興味のある方は以下を参照して頂ければ幸いです。
IoT時代・AI時代にこそ論理的読解力が問われる
近年では、人工知能(AI)の発達により、文章の自動作成機能なども現実化しつつあります。
日本語文の場合はAIの精度がまだまだ高くない状況であると言えますが、それももはや時間の問題です。
一方で、AIには代替できない能力があります。
それは、人間自身の読解力です。
AIがどれだけ自然に文章をインプット・アウトプット出来るようになったところで、人間である自分自身の読解力はAIには代替できません。
AIに出来ることと言えば「分かりやすい言葉に置き換える」といったことですが、それでも最終的に文章を読んで理解するのは自分自身です。(そもそも分かりやすい言葉に置き換えた時点でそれは元の文とは別物ですが)

でも、攻殻機動隊みたいに脳に直接プラグを刺せばどうにかなるんじゃね?電脳世界と接続してIQ300に!

それはもはや今の人類とは全くの別種族だと思います。
※ここで「なら読解も記述も全てAIに任せよう」となってしまえば、いよいよ人間はAIの言いなりとなってしまうことでしょう。これではどちらが機械なのか分かりません。
「情報の無料化」が教育格差を埋める…とはいかない国語
近年における高度情報化社会のもう一つのテーマとして、情報の無料化というものがあります。
スマホ時代、更にIoT時代へ向かっている今日このごろ、学習分野の様々な分野においてフリーで情報提供されつつあります。
- 英語であれば、数多のバイリンガル・マルチリンガルがネイティブレベルの解説を無料で公開しています。
- 数学であれば、純粋に趣味や教養として数学を学び続けている人も多く、英語と同じように様々な解説情報が公開されています。
- 地理歴史も科学も、各方面の専門家がプロ・アマ問わずいくらでも居り、少なくとも小中高のレベルであれば間違いなく誰かがネット上で解説していることでしょう。
極論を言えば、Wikipediaというたった1サイトだけでも凄まじい量の知識が眠っているというのが現代の環境です。
そして、教える側の人間も、情報共有・交換により更にブラッシュアップが可能となっています。
一方、国語の場合は、著作権の問題があります。
近年では、過去問題集ですら著作権上の問題で国語の長文問題を掲載できないケースが出てきています。
※「学校が入試問題として作品を利用するケース」と、「その入試問題の長文を第三者が利用するケース」とでは、著作権法上の扱いが異なります。
日本が法治国家である以上は、近年の著作権保護を重視する流れは当然のことです。
一方で、「日本の子どもたちの論理的読解力・国語力の向上」という観点から言えば、これは大きな問題です。特に、高いお金を払って進学塾や予備校に通えるような生徒さんとそれ以外の生徒さんとの間で教育格差が拡がる一因にすらなりえます。
よって、当シリーズでは、お手持ちの教科書をベースに、「受験国語の大得意な私視点から見た読解のポイント」について解説していきます。
著作権の関係から引用は最低限に留めますので、是非ともお手持ちの教科書を読みながら一緒に考えてみて下さい。
ネット社会における「新しい国語学習」の提案

以下、ネットを利用した長文読解の教育・学習方法について、私の試論を書き留めてみます。
出題元の著作権者に許諾を得る(使用料を支払う)
まずは、長文問題の元となる文章の著作権者に正式に許諾を得る、という王道の方法が考えられます。
ですが、これは出版社レベルですら現実的には難しい問題となっています。先程述べた「過去問に長文を収録できない」というのがまさにそれです。
ましてや、ネット上で公開して取り扱うというのは非常に難しいことでしょう。
この方針に関しては、執筆業界・教育業界の全体を巻き込んだ社会的な議論が必要なのかも知れません。
著作権切れの古い作品を利用する
続いて考えられるのは、著作権の保護期間が切れた作品を長文問題として利用する、という方法です。
これがコンプライアンス的に最も簡単な道です。
※「走れメロス」が重宝されるのも、実はこの著作権切れと文章の短さの2点が主な理由です。(太宰の文章力は言うまでもないこととして)
問題は、著作権の保護期間が作者の死後70年後まで続くという部分です。
よって、2019年現在から考えると、1949年以前に亡くなった作者の作品しか使えないと言うことになってしまいます。そうなると、時代背景が今と大きく異なってしまい、現代文というより「近代文」になりがちです。加えて、言葉遣いの違いもあります。
論説文については、現代の知見とは異なる部分も多くなってしまいがちですので尚更です。
長文問題用の文章を有償・無償で提供してもらう
続いて、長文問題用の文章を提供してもらうという案も考えられます。
有償であれば外注もありえますし、あるいは「小説家になろう」系の方や他のブロガーの方とのコラボなど、色々と考えられます。
ただ、国語学習に適しているような文章かどうかは別問題であるという問題があります。
加えて、一定以上の論理力・文章力を備えた文章というハードルもあります。
※総合学習の要領で一般教養とセットで国語力を磨くのであれば、非常にアリだと思います。ただし、受験対策であればやはり実際に過去問で使われるような文章を使うのが望ましいです。
私が自分で書く
あるいは、私自身が題材の文章を書くという手もあります。
社会科学系や一般教養系の論文試験にはめっぽう強かったですので、そうしたジャンルであれば書けるかもしれません。
ただし、各分野の専門家レベルの文章は書けないという問題があります。これは文学作品においても同じです。
一定以上の試験レベルを想定するのであれば、どうしても「餅は餅屋」になってしまいます。
クローズドなネット空間で既存の過去問を講義する
続いて、SNSやバーチャル空間などを利用して、クローズドなコミュニティの中で過去問などを講義するという手段も考えられます。
例えばVR上で私のアバターが居て、全国各地の生徒さんもアバターとして参加して、国語も双方向型でオンライン集団授業が出来るといった要領です。
ただ、これもまたコンプライアンス的に難しい問題となります。この点についても、もっと大きな組織レベル・社会レベルで考える必要があります。
オンライン家庭教師・リアル家庭教師・塾etc……
もちろん、オンライン家庭教師やリアルの個別指導塾などの対面授業であれば、手元に教材さえあれば何でも解説できます。
ただ、こうした既存の方法では、経済格差の問題は依然として残ります。
とは言え、経済的に余裕があるご家庭であれば、オンライン家庭教師などのプロに頼るのが最善の道であることが多いでしょう。
教科書解説シリーズのスタート
そこで考えたのが、「本文はお手持ちの教科書を読んで頂きながら、読解のコツ・ポイントを解説する」というスタイルです。
本当は、私が実戦モードでメモを書き込んだ問題文を全文掲載できれば理想です。
なぜなら、本気で国語の読解力を身につけるならば、助詞・助動詞の一字一句レベルで解釈することが前提になるからです。
文法は現代文の読解問題の基礎としても重要!中学国語の品詞から分析|論理的思考のコツ⑯
ですが、前述の通り、著作権の問題があります。
よって、次善の策として、論理的に読解するに当たってのヒントや受験国語に役立つコツを中心に解説していきます。
基本的にはご自身で教科書をよく読んで頂きつつ、理解を深めるプラスアルファとして当シリーズがお役に立てれば幸いです。


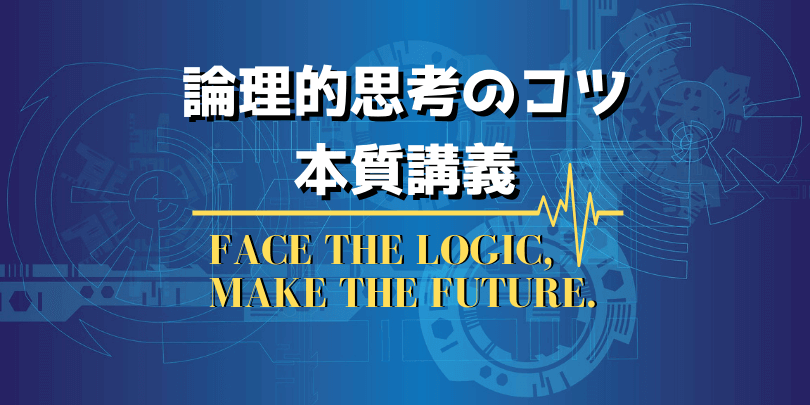
コメント